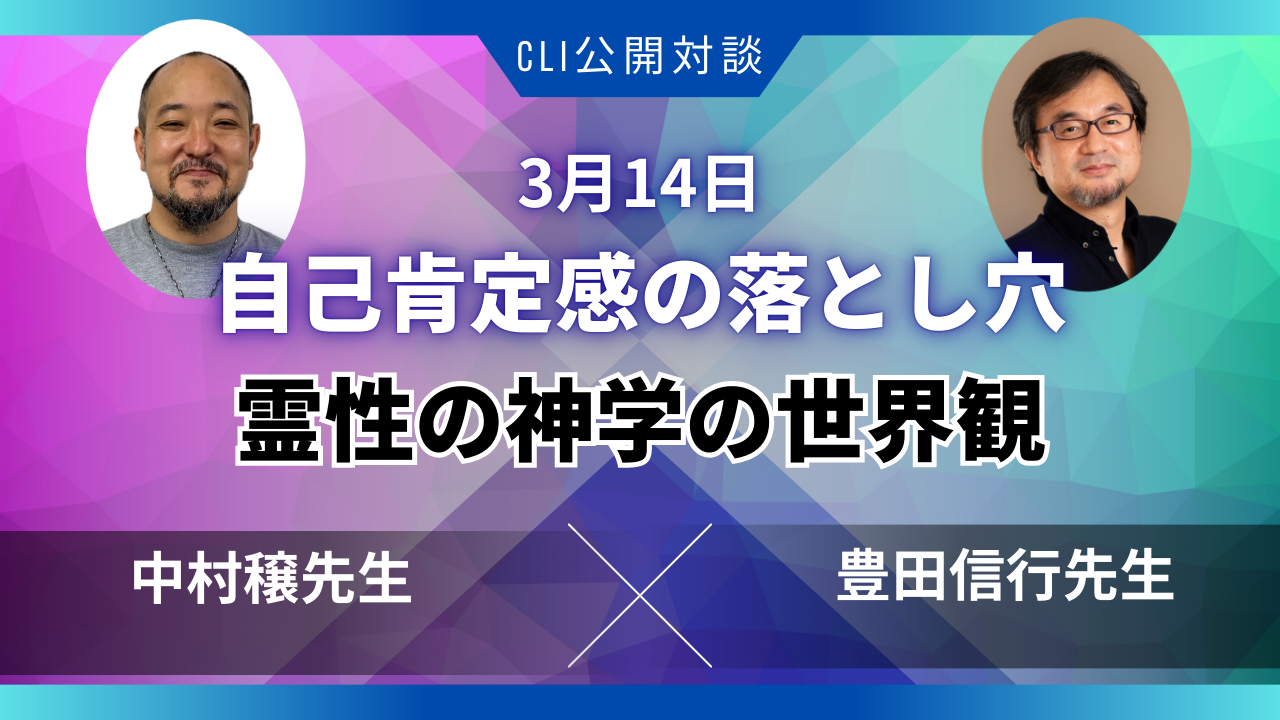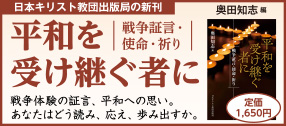【Web連載】ボンヘッファーの生涯(9) 平和へのまなざし(後編)キリスト教と戦争 福島慎太郎 2025年12月4日
平和と自己理解
前回では、キリスト教と戦争の関係を歴史的にたどり、アウグスティヌスの「正戦論」からツヴィングリ、アナバプティスト、そしてボンヘッファーへと受け継がれる「暴力と信仰」の葛藤を考察した。そこでは、教会が平和を語る前に、まず自らの歴史と責任を見つめ直す必要性を指摘した。
今の時代こそ、「平和」という〈マクロ〉な理想を語ると同時に、それを支える「自己理解」という〈ミクロ〉な内的営みに取り組むことが求められている。そしてボンヘッファーはまさに、その二つの領域を徹底的に問い続けた人物でもあった。
「神学なき教会」とボンヘッファーの警鐘
1914年に結成された「世界連盟」は、ヨーロッパとアメリカのプロテスタント教会の代表者による国際組織で、平和運動や教会の一致を目的としていた。
1932年、当時26歳で連盟の幹事を務めていたボンヘッファーは「世界連盟の運動の神学的基礎づけへの試み」と題する講演を行った。彼は、政治的ナショナリズムの高まりを前に「左から右から波が押し寄せても、揺るがぬ神学的な錨が欠けている」と警告した。
少々語気の強さを感じるかもしれないが、この翌年にヒトラーが首相に就任するなど、社会情勢はすでに「(第一次世界大戦の)戦後」から「(第二次世界大戦の)戦前」へと移り変わろうとしていた。また他のヨーロッパ諸国を見ても、例えば、オーストリアでは1931年にウィーン信用銀行が破綻、同年スペインではブルボン王朝が崩壊するなど、西欧全体として国家の揺れ動きに見舞われている時期であった。
その只中で、ボンヘッファーは本講演の序盤において、繰り返し「神学」を生み出す必要性について論じている。ここで彼が言う「神学」とは、聖書を起点に、教会と信仰者が自らの言葉と行為の根拠を問い直す営みを指し、社会的状況に対して右か左かを選ぶことではなく、いかなる時代にあっても語るべき「言葉」を備えるための内的訓練を意味する。
また「語る」という営みには、必ず対象がある。語る者と聞く者との関係性が成立して初めて、言葉は力をもつ。ゆえに神学とは、〈マクロ〉な世界への洞察と、〈ミクロ〉な自己理解という二つの側面を往還する実践的な行為にほかならない。
そして神学の言葉や教会の実践が、仮に〈社会的・政治的影響〉を与えたとしても、その中心命題は「御言葉が聞かれうるような条件を確保」するための「道備え」であるとボンヘッファーは考えていた(ボンヘッファー『倫理』から)。
「山上の説教」とボンヘッファー
変わりゆく時代の中で、ボンヘッファーは教会が〈本質〉を問う必要を訴えた。
彼はこう語る。「われわれが語り、聞いているキリスト教とは何か。それは本質的に、山上の説教の内容であるか」
「山上の説教」(マタイ福音書5〜7章)は、キリストが弟子たちに語った〈神の国の倫理〉を含む説教である。ボンヘッファーにとって、これは信仰の核心だった。
1935〜36年、彼は「自分は信仰を知らなかった。だが山上の説教によってすべてが変わった」と友人に語り、翌年、『キリストに従う』を出版している。
その詳細についてはいずれの連載で取り扱うが、ここではボンヘッファーが「服従」の重要性と出会ったということを覚えていてほしい。というのも、該当箇所であるマタイによる福音書第5章を開くと、キリストの周囲には人々が集まっており、その中から、キリストの言葉に聴従しようと弟子たちが一歩彼のもとに近づく光景が広がっている。
そこからボンヘッファーは、信仰とは宗教的形式や倫理規範を守ることではなく、「キリストの言葉に呼びかけられ、それに応答して従うこと」だと語る。それは「平和」という文脈でも同じ様に、「平和をつくる者は幸いである」という山上の説教に含まれている本フレーズを実現するために、まず人々は神の言葉を聴くことが求められると考えていた。
ちなみに本講演では、ボンヘッファーの「山上の説教」への〈解釈〉についてはほとんど触れられていない。それが骨組みとして顕になるのは、やはり『キリストに従う』においてである。講演と書籍の出版には約5年の間隔が空いており、神学的立場を同一視することは出来ないだろうが、末尾の「終わりの覚書Ⅰ」において、彼の「山上の説教」に関する言及をいくつかまとめておいたので、関心のある方はぜひご覧になっていただきたい。

絶対平和主義
ボンヘッファーは「この世理解」において、ルター派神学の「二王国論」を克服しようとする。
この世界の中の、聖なる、神聖な領域だけがキリストに属しているのではなく、この世界の全体がキリストの領域なのである。
彼が〈平和〉を捉える時の射程には〈世界〉全体が含まれている。そこで教会と信仰者は、時代の動きに敏感でありつつ、どの状況でも語るべき言葉を持たねばならない。そして同講演で彼が語った「『今ここで』妥当する拘束的な言葉」とは、まさに現実において響く神の言葉を意味している。
また戦争について、ボンヘッファーは「戦う者の両方が確実にみずからを絶滅することになる」と、一切の武力行使を認めなかった。むしろ「今日の戦争、あるいは将来起こるかもしれない戦争は、教会によって全面的に拒否されなければならない」と主張する。これは「絶対平和主義」の一つの形である。
彼にとって戦争がもたらすものは「真理や正義が暴力によって犯され」、結果的に「啓示を見えなくしてしまう」という〈堕落〉の世界観そのものであった。もっとも、彼にとって平和も単なる理想ではない。それは神の国の到来までの「破壊されうる保持の秩序」に過ぎず、だからこそ、教会はその儚さを自覚しつつ、〈今ここで〉実践する責任を負うと語った。
哲学者イマヌエル・カントが『永遠平和のために』において「地球は球体であり、限られた空間で人間は互いに我慢し合わなくてはならない」と述べている。これは実践的現実主義に根差した世界の〈剥き出し〉の様相を的確に表している。
ボンヘッファーもまた、そのような世界を「罪」や「堕落」という神学的概念を通して認識していた。一方で、それと同時に神の平和の到来を信じつつ、それを〈いまここ〉で証しする責任も見出していた。「われわれは、確信をもって、神の平和に、究極の『平和の創造』をゆだねると同時に、われわれもまた、確信をもって、戦争を克服するために平和を創造すべきである」
ここでは終末的希望を神に委ねると同時に、先述の通り、その「道備え」をするために教会と信仰者には実践が求められるということが語られている。
今、教会は何を語るべきか
こうしてボンヘッファーは、「山上の説教」を土台とした「従う信仰」から「語る教会」へと神学を展開した。それは『キリストに従う』の中で「服従する者たちは目に見える教会である」と記されている通り、神の言葉を聴く者が、今度はその言葉をこの世界で証しする者となるのである。
その意味で、教会は「国家の行為の批判者」であるとボンヘッファーは語っている。ここでの「批判」とは、政治的立場を表明することではなく、「真理」――すなわち「キリストが救い主である」という〈福音〉を明らかにすることである。
福音を明らかにする営みを教会では〈宣教〉と呼ぶが、ここでは端的な救霊の枠を超えて「神による世界の回復」を告げ知らせる営みまでを含んでいる。それは、「山上の説教」における〈聴き・従う〉信仰が、神の回復の〈希望〉を担って、今度は〈語る〉かたちで世界へと開かれていくプロセスでもある。
信仰の聴従と教会の宣教は、同一の神学的運動の両端にある。ゆえに教会が〈語る〉とは、単に教理を主張することではなく、この世界において神が今も働いておられることを〈証し〉する行為である。
またボンヘッファーにとって〈教会〉とは、「神の現実」が現れる場であり、そこから発せられる言葉は、世界を回復へと招くための言葉である。今日の教会もまた、その声をもって〈平和〉の出来事に参与するよう招かれているのではないだろうか。
総括――神学に預言性をもたらす
哲学者カール・ヤスパースは、本来あるべき哲学を「予言者的哲学」と呼び、時代を生きる人々に〈生〉の意味と価値の秩序を与える言葉の必要を説いた。
神学もまた、そうした〈預言的性質〉を携えるべきであろう。ボンヘッファーの神学が今日においても力を持つのは、彼が「信仰の従順」と「言葉の証し」とを結びつけ、神学を単なる思索ではなく「現実を変革する言葉」として捉えていたからである。
その意味で、彼にとって神学とは、観念的体系ではなく、「神の現実がこの世界で語られるための道備え」であった。
私たちもまた、時代のただ中で神の声を聴き、それに応答する言葉を紡ぐ使命を負っているのではないだろうか。そして、そこで生まれる言葉こそ、世界における神の現実を告げ知らせる「預言」となるのである。その営みを〈神学〉と呼び、その土台には〈信仰〉が求められる。この往還の中にこそ、教会が未来へ向かって歩むための希望が息づいている。
【参考文献】
・ディートリヒ・ボンヘッファー、森野善右衛門訳『告白教会と世界教会』(新教出版社、1968年)
・同上、『現代キリスト教倫理』(新教出版社、1978年)
・同上、森平太訳『キリストに従う』(新教出版社、1966年)
・CDジャーナルムック編集部編『ALL THE SONGS OF つんく♂』(シーディージャーナル、2023年)
・ハンナ・アーレント、志水速雄訳『人間の条件』(筑摩書房、1994年)
・イマヌエル・カント、池内紀訳『永遠平和のために』(集英社、2016年)
・宇都宮芳明『ヤスパース』(清水書院、2014年)
・ジョン・H・ヨーダー、佐伯晴郎他訳『イエスの政治─聖書的リアリズムと現代社会倫理』(新教出版社、1992年)
・Sattler, M. (1973). The legacy of Michael Sattler (J. H. Yoder, Ed. & Trans.). Herald Press.
・Anabaptist Community Bible. (2023). Study notes on the Holy Scriptures. Herald Press.
終わりの覚書Ⅰ――アナバプティストとボンヘッファーの聖書解釈
〈聴く〉こと、〈解釈する〉こと
ボンヘッファー『キリストに従う』の中に、彼の聖書解釈に関する興味深い記述がある。要約するとこうなる。「もし父親に『おやすみ』と言われたら、子どもたちはもう寝る時間だと気づく。一方で疑似神学に囚われている者は、あれこれと分析を始めるだろう」
この場合の「疑似神学」とは、キリストの言葉を、〈生〉の営みの中で〈聴く〉より先に、理論や体系として〈解釈〉する態度を指す。ボンヘッファーは〈神〉が父であり、〈人間〉が子であるという関係性を重視し、その中から聖書を読むことを推奨した。
実は、このようなボンヘッファーの指摘はアナバプティストの解釈と、ある程度の親和性がある。前回号をお読みの方であればその共通性をすでに直感しているかもしれない。
そこで、本節では「山上の説教」の解釈を中心に、彼らの聖書観・信仰観を少し比較してみたいと思う。なお、一口で「アナバプティスト」と言っても、無数の教派と歴史があるので、ここでは何人かの神学者の見解を統合している「指標」として、参考程度に読んでほしい。
「山上の説教」における比較
まず〈基本姿勢〉として、アナバプティストは「山上の説教」を文字通りの〈実践のための命令〉として解釈する。対して、ボンヘッファーは〈キリストとの関係における現実〉として捉える。
〈キリストとの関係における現実〉とは”抽象的な倫理”ではなく、キリストの言葉を聴く上で実践することができる”新しい生の現実”の到来として読むことを意味する。
次に、「山上の説教」における〈教会観〉と〈社会観〉について、アナバプティストは、時に〈世〉と分離・逸脱しても、なお遵守すべき〈清められた共同体〉として整えられていくことを目指す。他方、ボンヘッファーは〈世〉との関わりの中でそれらを体現することを掲げ、そのために教会と信仰者は地上に派遣されているのだと考えた。
そして、〈倫理の位置付け〉について、アナバプティストは「イエスの命令を文字通り受け止める(守る)」ことで〈形成〉されると考え、ボンヘッファーは「イエスに従う」ことで〈発生〉すると捉えていた。
ここにボンヘッファーが「平和」を捉える上で、「山上の説教」を例に挙げた理由がある。つまり、倫理規範や理想平和といった類のある種「究極的な事柄」は神によって実現されるのであり、信仰者はそれを体現する〈通り良き管〉なのである。そのためには何より、神の言葉を聴く姿勢が求められる。
もちろんアナバプティストが自力救済や自己解決を前提としていたわけではない。むしろ帰結点はボンヘッファーとほとんど同じであろう。本節はそこに至るまでの〈切り口〉の違いについて論じたものである。
「理想と現実の境目を定めているのは、人間なんでしょうね」
筆者のメンターに、オネシモ和解KD(Onesimus reconciliation kappadelta)というアナバプティストやメノナイトの牧会者による、教会形成と平和研究を目的とした国際的ムーヴメントの創始者のお一人、石戸充氏がいる。
以前、彼にこのような質問をしたことがある。「右の頬を叩かれてすぐに左の頬を差し出すのは無理だと思う。それは理想論ではないか」――彼はすかさず尋ねた。「それは『山上の説教』の記述ですね。では、同じ説教の中にある”祈り”という行為も理想ですか?」
筆者は「祈りは日常で行う、実践可能な現実的行為です」と答えた。すると、彼は一言こう言った。「その理想と現実の境目を定めているのはおそらく人間なんでしょうね。でもイエス様は、人間が理想としていた『神の国』を現実とするために、この世界に来られましたよね」
端的に、アナバプティスト的な聖書の読み方とはまさにこれであろう。旧約聖書において人々が理想としていた〈神の平和〉の究極的な形である「神の国」を、キリストは〈現実〉とするために人の形をとられた。ゆえに、その活動の始まりは「時が満ち、神の国は近づいた」(マルコによる福音書1章14節)という一言から始まったのだろう。
そしてキリストの言葉を聴く人々にもまた、それらを〈理想〉ではなく〈現実〉として捉え、〈具体化〉していくことを神は期待しているのだろう。その意味で、聖書を読むとは、実はとても簡素な営みなのかもしれない。
一口に「キリスト教」と言えども、その教会の姿や聖書の解釈は古今東西、数多ある。もちろん目に余る逸脱した解釈については議論せねばならないだろうが、少なくとも教派神学の違いについて、私たちは〈亀裂〉ではなく〈個性〉として、まず互いに味わい尽くしたいと思う。

今夏、筆者はオネシモ和解KDに招かれ北米研修へ。写真はその際訪れたアズベリー神学校。
終わりの覚書Ⅱ─現代文化を通して眼差す「未来志向」
つんく♂の詩的感覚
アイドルを応援する営み――いわゆる「推し活」の経済効果は年間8,000億円を超えると言われている。そんな現代のアイドルブームを語る上で、ハロー!プロジェクト(ハロプロ)は欠かすことはできないだろう。
保育園の頃、体の線が細かったことから女子グループに混ぜられ、松浦亜弥「♡桃色片想い♡」を無理やり踊らされたことはいまだにトラウマである。一方、現在は僕自身もハロプロのヲタクとなり、20年以上の時を経て場所はライブハウスに変わり、今では笑顔で振りコピ(アイドルのダンスに合わせて一緒に踊ること)をしている。俯瞰すればまあまあ恐ろしい光景である。
2011年は未曾有の大災害が発生した年であった。社会は混乱に見舞われ、個人は明日をどのように生きればよいかと模索し続けていた。
震災の半年後、モーニング娘。からつんく♂の作詞・作曲によるシングルが発売された。それが「この地球の平和を本気で願っているんだよ!/彼と一緒にお店がしたい!」である。この作品の興味深い点は、楽曲が二つあるもののミュージックビデオは一つになっているところで、つんく♂曰く「二曲で一つの作品が完成する」ことを意図したという。
〈生〉における根源的欲求
つんく♂の歌詞では、〈マクロ〉と〈ミクロ〉――つまり大きな世界と小さな日常を行き来しながら〈生きる実感〉を取り戻そうとする詩的な営みが随所にほどこされている。実はこの視点こそ、人が社会の中でどのように生き、他者と関わっていくべきかという〈未来志向〉の本質を突いているのではないだろうか。
本曲タイトルでは「地球の平和」という〈マクロ〉な願いと、「彼とお店がしたい」という〈ミクロ〉な願いが同時に響いている。そして両作が共鳴することで一つの世界観が完成するというつんく♂の視点は、まさしく〈生〉における根源的欲求──すなわち、壮大な理想とささやかな日常が交わるその瞬間にこそ、人間の〈生〉のリアリティがあり、〈現実〉が〈希望〉として息づくのだと物語っている。
〈回復〉された世界を目指して
哲学者ハンナ・アーレントが述べるように、人間は他者との関係性の中で世界を形づくる存在である。それは、〈社会〉を見つめることは〈自分〉から始まり、また〈自分〉が生きるとは〈社会〉という場の中で語り、関わるということにほかならない。
その意味で、つんく♂の詩に見られる〈マクロ〉と〈ミクロ〉の橋渡しは、人類が「ともに生きる未来」を描き出すための創造的な手がかりを与えてくれている。
平和を祈ることと誰かを想うこと――そのどちらもが、同じ〈生〉の営みの中にあるという視点は、聖書が語る「和解の福音」、すなわち神と人、人と人との〈関係の回復〉を告げるメッセージにも通じているのではないだろうか。
平和とは単に戦争の不在を意味するのではなく、他者への思い、隣人へのまなざし、そして日常の交わりの中に芽生える〈関係の回復〉の営みそのものである。マクロな「世界平和」とミクロな「隣人愛」が響き合う場所にこそ、神の平和(シャローム)の現実が垣間見えるのだ。
最後に勝手ながら、同事務所つばきファクトリーの豫風瑠乃さんのパフォーマンスは要チェックであると宣伝しておく。

福島慎太郎
ふくしま・しんたろう 名古屋緑福音教会ユースパスター。1997年生まれ、東京基督教大学大学院を卒業。研究テーマはボンヘッファーで、2020年に「D・ボンヘッファーによる『服従』思想について––その起点と神学をめぐって」で優秀卒業研究賞。またこれまで屋外学童や刑務所クリスマス礼拝の運営、幼稚園でのチャプレンなどを務める。連載「14歳からのボンヘッファー」「ボンヘッファーの生涯」(キリスト新聞社)を執筆中。