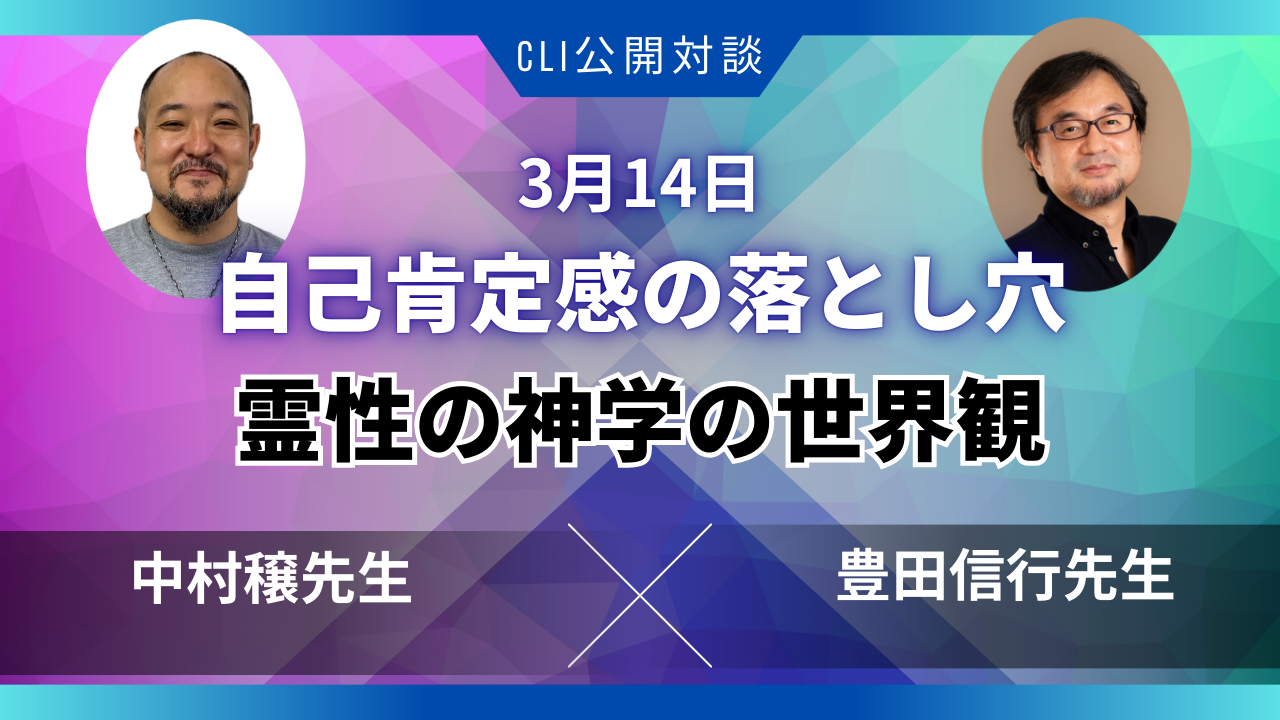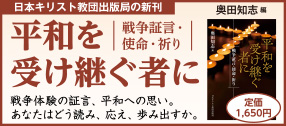同志社150周年式典 良心と召命の源流に聴く 「共に知る、共に変わる」へ 2025年12月8日

学校法人同志社の創立150周年を記念する式典が2025年11月29日、国立京都国際会館(京都市左京区)で行われ、卒業生ら約1600人が集った。アドベントの季節に開かれたこの集いは、単なる周年の祝賀にとどまらず、祈りと良心、そして召命の物語として、参加者の信仰の原点を静かに照らした。
式典に先立ち、茶道・裏千家家元の千宗室氏(同志社大卒)が、新島襄の肖像画に献茶した。新島の妻・八重がつくった赤い茶わんが用いられたという。京都の歴史とキリスト教教育の歩みが重なるその所作は、世俗と信仰が分断されるのではなく、日々の文化の中にも神の恵みが浸透しうることを思い起こさせる場面となった。
同志社の源流は1875年の同志社英学校にある。新島と宣教師デイヴィス、わずか8人の生徒から始まったこの学校は、1873年に「キリシタン禁制の高札」が撤去されて間もない時代に、最も保守的とされた京都で産声を上げた。学長の小原克博氏は同日、記念講話「同志社150年の歴史と精神を語り継ぐ」の中で、世界がクリスマスへ向かうこの時期にあって、「クリスマスの物語と同志社の物語は響き合って」いると語った。暗闇の中の小さな希望の光として語られる幼子イエスの誕生になぞらえ、新島の挑戦もまた「暗闇にゆらめく実に小さな光」だったという。
しかし、光は容易に消えなかった。戦争の時代にはキリスト教主義の撤回圧力が高まり、教師が検挙され、経営の危機に立たされたこともあった。多くの学生や教職員が犠牲となった歴史を前に、小原氏は「150年の歴史には日本近現代の激動の歴史が刻まれている」と述べた。信仰に根ざした学校が時代の嵐の中で耐え抜く姿は、教会が歴史の痛みを抱えながらも希望を語り続ける歩みと重なる。
来賓として祝辞を述べた立教大学総長の西原廉太氏(キリスト教学校教育同盟理事長)は、同盟の源流が1899年の「文部省訓令第12号」に抗し、キリスト教教育を守ろうとした連帯にあることを提示。1910年の第1回総会の会場が同志社であったこと、さらに1922年の新たな同盟会設立の場も同志社であったことに触れ、「つまり、文字通り、同志社は日本のキリスト教教育の源流」であり「礎であり続けてきた」と語った。
西原氏は、新島が国禁を犯して脱国し、アメリカで学び洗礼を受け、liberal educationや人格教育の重要性を確信した歩みを振り返りつつ、創立者たちのミッションとは神の「呼びかけ」(calling)に応えて学び舎を築き教壇に立つことであったと強調した。創立者の祈りを継承する今日の私たちの使命は、この「呼びかけ」に対する「応答」を時代ごとに再現し続けることだという。
こうしたメッセージは、新島襄が晩年に公表した「同志社大学設立の旨意」に改めて光を当てる。新島は明治21年、20を超える新聞・雑誌に「旨意」を発表し、大学設立への協力を全国に求めた。文章は、同志社諸学校に至る経緯を語る前半と、「今なぜ大学が必要か」「いかなる大学であるべきか」を熱く論じる後半から成り、今も入学式で朗読される。
新島は私立大学を「人民の手に拠って設立」しようとした。当時、大学と呼ばれるものは官立の東京大学のみ。これに抗して、全国の賛同する人々が自発的に連なる「結社」として大学を構想した。この理念は「同志社」――志を同じくする個人の約束による結社――という校名に刻まれている。信仰の共同体が「志を同じくする」者たちの自由な応答によって形づくられてきたことを思うとき、この「人民の手に拠る」構想は、教会論的な響きすら帯びる。
小原氏は記念講話で、大学設立への志を凝縮する新島の漢詩「借大箒期掃邦土 十年計画未休神」を紹介した。大きな箒で古い日本を掃き清め、新しい社会をもたらしたい――その願いは教育による社会変革の夢であると同時に、神の国のビジョンに向かう信仰者の祈りにも似ている。
さらに、同志社の精神が抽象理念ではなく、生きたエピソードと結びついている点を強調した。門番の松本五平を新島が「五平さん」と呼んだこと、そして創立10周年記念で「諸君よ、人一人は大切なり」と涙ながらに訴えたこと。ここに表れているのは、キリスト教主義とは知識の伝達ではなく、隣人を尊び、封建的な価値観に抗して人間の尊厳を守る生き方そのものだという確信である。
150周年の節目に同志社が掲げるビジョンは「共に知る、共に変わる With a Good Conscience」。良心の原義が「共に知る」にあるという指摘は、教会が「共に」み言葉を聴き、祈り、悔い改め、歩みを新たにしてきた歴史を思い起こさせる。
(関西支社 後宮 嗣)