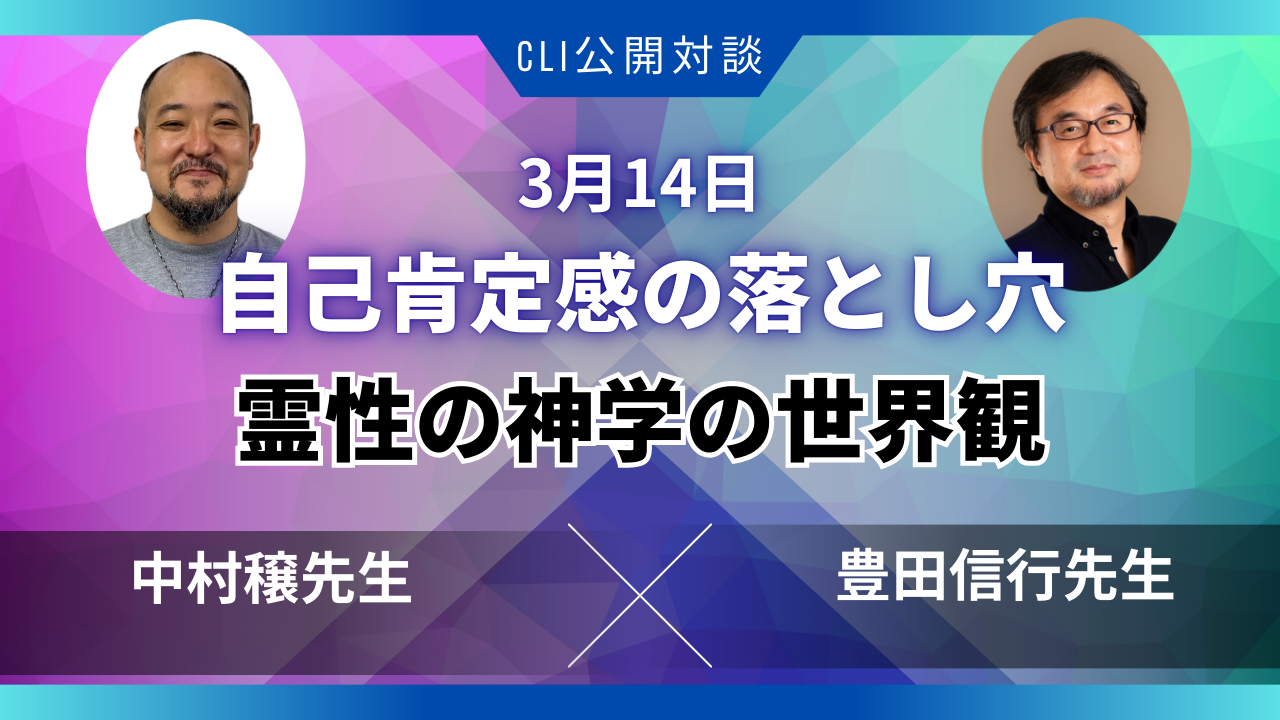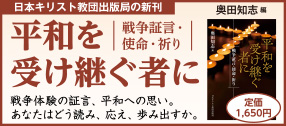【映画評】 軽妙に描かれる世代間トラウマの重さ 『旅の終わりのたからもの』 2026年1月11日

ルーシーはニューヨークで活躍するジャーナリスト。しかし結婚生活は破綻し、ダイエットは上手くいかず、幻覚症状に悩まされ、人生に行き詰まりを覚えている。家族の過去にその解決を求め、貯金をはたいて一路ポーランドへ。両親がホロコーストの生存者なのだ。しかし同行した父、エデクは能天気に観光地ばかり巡り歩き、ルーシーのルーツ探しを妨害する。互いの気持ちを知らない父娘は、道中衝突が絶えない。
『旅の終わりのたからもの』はホロコーストそのものでなく、それが後の世代にもたらす影響にスポットを当てた異色のロードムービー。第一世代のトラウマだけでなく、第二世代に伝わった「世代間トラウマ」を描く。見ていて辛いのは、第二世代のルーシーが「何があったのか知りたい」と切望する一方で、第一世代のエデクが「忘れたい」「語りたくない」と願っている点だ。前者は過去を知ることが癒しになると信じ、後者は過去を封印することで平静を保っている。
その違いは、エデクがポーランドに残してきた(残さざるを得なかった)家族の遺品への態度にも表れる。ルーシーにとってそれらは亡き祖父母との唯一の接点だが、エデクにとっては「ただの食器」であり「ただの衣服」だ。思い出の品々への愛着を頑なに否定する、そのエデクの冷淡な態度は、おそらく彼のホロコーストの経験に由来する。そこではユダヤ人の命に価値はなく、その所有物は容赦なく奪われたからだ。
しかし、そうやって家族の遺品を「ただの食器」や「ただの衣服」と断じてきたエデクが、ルーシーとの交流によって徐々に変わっていく。それはエデクにとってルーシーが「ただのユダヤ人」や「ただの人間」でなく、唯一無二の存在だからに他ならない。一方のルーシーにも変化が訪れる。父の痛みに触れ、その一部を引き受けることによって、逆説的に彼女も解放されたように見える。ここに、第一世代と第二世代のトラウマが衝突しない、むしろ相互理解へと向かう道筋を垣間見ることができる。
深刻な痛みを抱える二人が、しかしユーモアを忘れず、むしろ能天気にさえ見える点にも注目したい。原作者のリリー・ブレットはデビュー作から、ホロコーストの第二世代についてユーモラスに描いている。両親がホロコーストの生存者である彼女もまた、第二世代なのだ。そして笑いを交えた語り口で深刻な痛みを表現するのは、当事者の防衛的な心のはたらきとして珍しいものではない。
ホロコーストはもちろん重く深刻なテーマだが、その痛みを軽妙にユーモラスに描くのもまた、それが重く深刻であるがゆえだろう。当事者はいつも沈痛な面持ちで生きているわけではない。それぞれに生活がある。楽しいときもあれば笑うときもある。そんな当たり前のことを当たり前に描写する点でも、本作はホロコーストを扱う映画として異彩を放っている。
(ライター 河島文成)
2026年1月16日(金)kino cinema新宿ほか全国ロードショー
配給:キノフィルムズ
© 2024 SEVEN ELEPHANTS, KINGS&QUEENS FILMPRODUKTION, HAÏKU FILMS