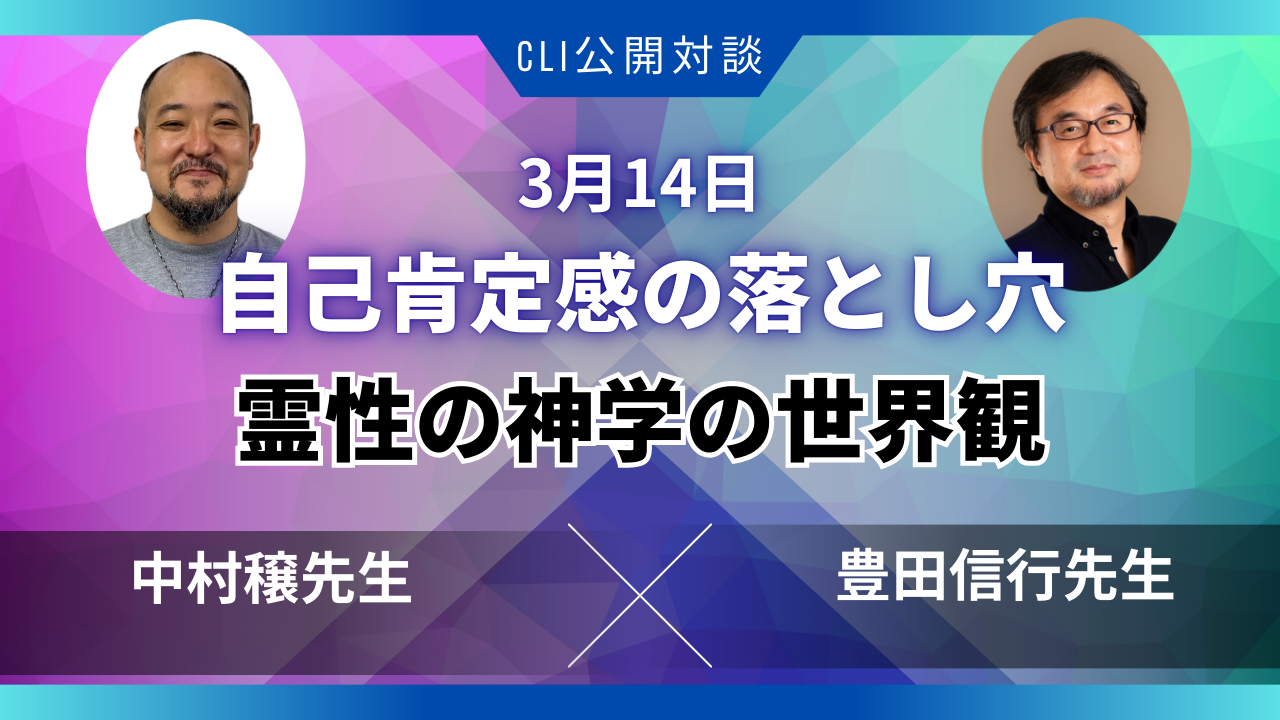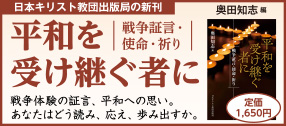【映画短評】 忘れてしまう日々、忘れられない場所 『終点のあの子』 2026年1月22日

高校に上がった希代子は明るい地毛を黒く染め、周囲から浮かないように注意している。無難な友人たちと平凡に付き合う、特に楽しくないが平穏な学校生活。そこに外部生の朱里がやってくる。自由奔放な朱里は周囲から完全に浮いているが、希代子は彼女にすっかり夢中に。しかしある事件をきっかけに、その思いは憎しみに変わる。
『終点のあの子』は柚木麻子の同名小説を原作とする青春映画。純粋無垢なイメージが付けられやすい女子高校生たちの、しかしまったくそうでないリアルな世界が描かれる。キラキラした笑顔と裏腹に、妬んだり嫌ったり、すり寄ったり突き放したり。希代子と朱里だけでなく、登場人物は誰もが誰かを傷つけ、誰かに傷つけられる。時に容赦なく残酷に。
しかし、そこに明確な悪意があるとは言えない。みんな自分が何者か分からず、揺れ動き、迷っている。大人をほぼ排除した、性差も年齢差もない、女子高という同質の輪の中だからこそ、その揺らぎと個々の異質さが際立つ。少女たちは時に意図的に、時に無自覚に相手を傷つけ、後悔し、謝りたいと願いながら、時だけが過ぎていく。
そこまで濃密だった人間関係が、しかし卒業によって分解し、ほとんど記憶に残らない点もリアルだ。序盤に登場する「フォーゲット・ミー・ノット」という青い絵の具が、終盤に存在感を増す。その青は勿忘草の花の色で、花言葉は「私を忘れないで」。
希代子には忘れられない場所がある。小田急江ノ島線の終点、片瀬江ノ島駅だ。その海岸で希代子と朱里はそれぞれ別のものを見つけた。その決定的な違いが、逆に2人をあれほど強く結びつけたのかもしれない。『終点のあの子』は朱里のことであると同時に、彼女の対極にいて、それゆえ互いに補完し合っていた希代子のことでもある。
本作は色彩表現にもこだわっている。朱里の青、マリー・アントワネットのピンク、その2人に順番に染まり、しかし結局どちらでもないと気づいた希代子の緑、そして江ノ島の海の青を照らす光と、その影。それらの意味に思いを巡らすのも有意義な、絵画のような映画だ。
(ライター 河島文成)
2026年1月23日(金)よりテアトル新宿ほか全国公開。
©2026「終点のあの子」製作委員会