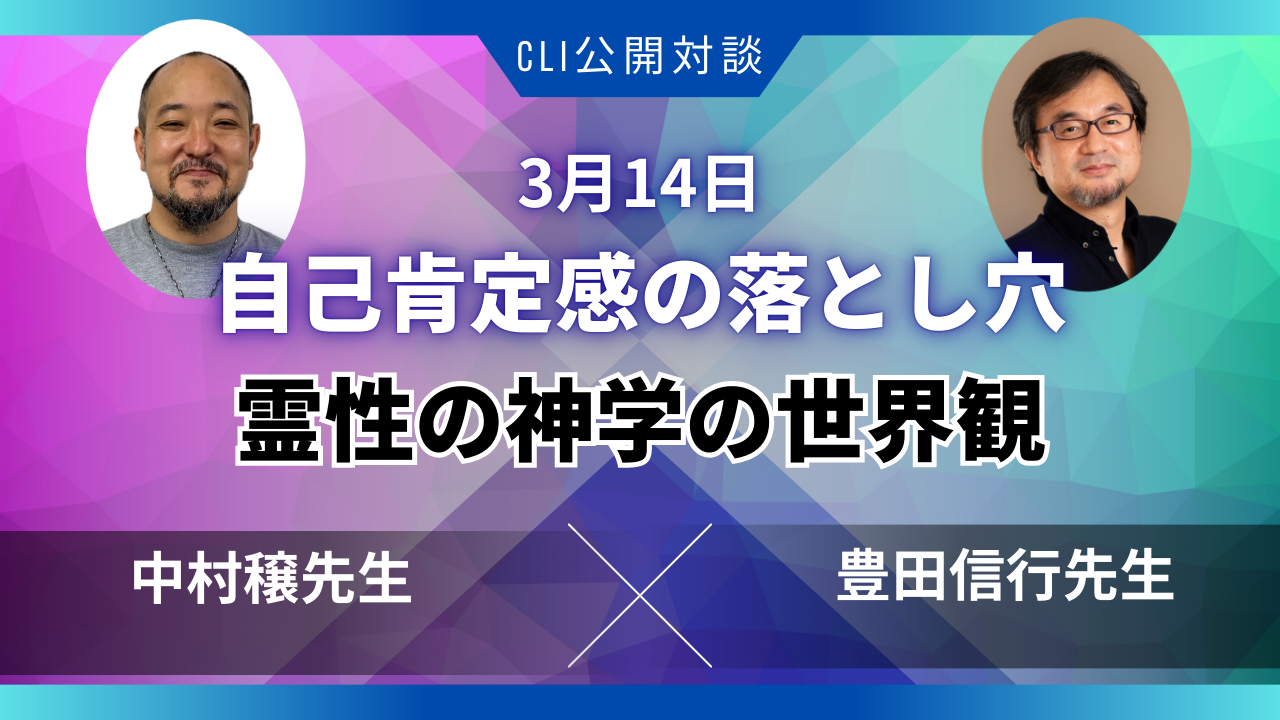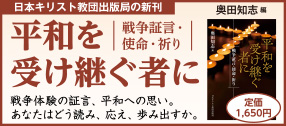【映画短評】 恐怖の陰謀論、陰謀論に至る恐怖 『ブゴニア』 2026年2月13日

製薬会社のカリスマCEO、ミシェルはある日突然拉致される。犯人は会社の末端労働者テディと、その従弟で引きこもりのドン。ミシェルが地球侵略にきたアンドロメダ星人だと信じるテディは、「宇宙船との連絡を断つため」に彼女を丸刈りにし、自宅の地下に監禁。「地球から撤退せよ」と迫る。ミシェルはあの手この手で脱出を試みるが、事態は思わぬ方向へ進んでいく。
『ブゴニア』は2003年の韓国映画『地球を守れ!』のリメイク。大筋はオリジナルとほぼ同じだが、陰謀論がより身近に喧伝されるようになった昨今、この物語の衝撃は2003年当時よりはるかに大きい。陰謀論は人類の歴史の陰に日向にいつも存在してきたが、今その影響が再び顕著となり、本作がリメイクされるに至った背景を思うと、安易に笑うこともできない。
しかしこの物語にとって重要なのは、予想外の結末でなく、陰謀論の真偽でもなく、テディのような弱者を陰謀論に走らせるほど追い詰めた、この社会の不正義と分断を描くことにある。テディを演じたジェシー・プレモンスは言う。「多くの人が陰謀論に染まっていく時、その人の中に恐怖心を起こしている『種』自体は、誤りではない」陰謀論は結果であって、そこに至る「恐怖心」こそが問題なのだ。
前半、視聴者はミシェルの「恐怖心」に共感し、彼女がなんとか脱出できるようにと応援するだろう。テディが明らかに加害者であり、ミシェルが明らかに被害者だからだ。しかし後半にかけて、その印象は徐々に変化していく。実は被害者はテディであり、テディの母親であり、ドンではないのか。テディを突き動かしているものこそ「恐怖心」ではないのか、と。
本作は証言の信用性の問題も指摘している。社会的成功をおさめたカリスマ経営者の証言と、その企業の末端で働く孤独な労働者の証言のどちらに重きを置くべきか、視聴者はほとんど考えることなく判断してしまっているからだ。その偏見と先入観が巨大な不正義へと繋がっていくことを、『ブゴニア』は陰謀論を使って、逆説的に喝破している。
ラストに流れるマレーネ・ディートリッヒの『Where have all the flowers gone』(直訳すると「花はどこへ行ったのだろう」)は反戦フォークソングとして有名だ。「いつになったら分かるのだろう」というフレーズが、人類への警鐘のようにリフレインされる。衝撃の結末に、このフレーズが繰り返されることの意味を考えるのも興味深い。
(ライター 河島文成)
2026年2月13日(金)TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。
配給:ギャガ、ユニバーサル映画
🄫2025 FOCUS FEATURES LLC.