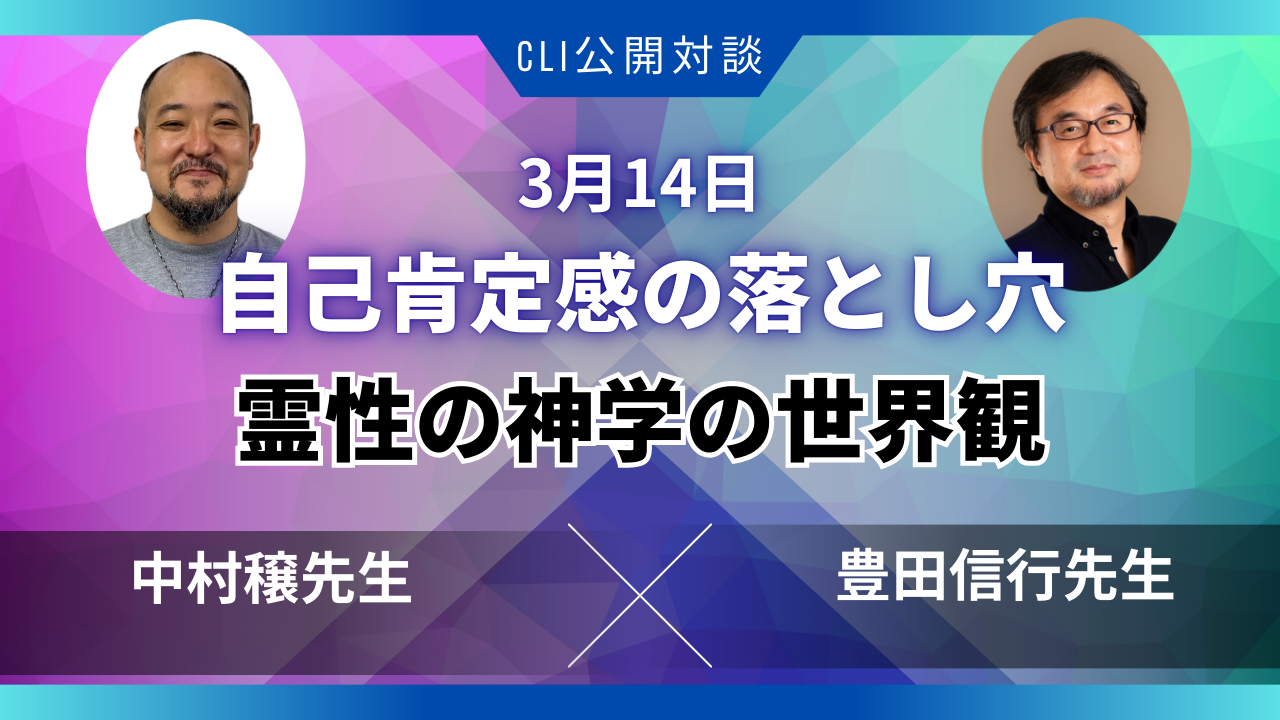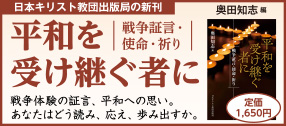【Web連載】ボンヘッファーの生涯(11) 弟子を飲み込む嵐 福島慎太郎 2026年2月14日

「説教」は何を語るかと同時に、〝どこで〟語るかという時間と空間も重要な構成要素となる。特にボンヘッファーの説教を読み解く上で、語られた時代背景を知ることは一層彼の言葉と神学が立体的になる。
1933年1月15日、ベルリンの教会で行われたボンヘッファーの説教はマタイ福音書8章23〜27節の物語。キリストに従おうと舟に乗り込んだ弟子たちが嵐に見舞われる場面だ。当時ボンヘッファーは26歳、そして説教の2週間後にはヒトラーが首相に就任するという時期でもあった。変わりゆく国家の姿を前に、彼は何を思いながら語ったのだろうか。
まず、この説教では「恐れ」について鮮明に描かれている。
恐れは人間の心の中に入り込み、人間をうつろにする。そしてある日突然、人間は無抵抗になり、力なく破滅してしまうのだ。
「まずい、近づいてくる」と思えば、ある程度の危機や困難も対処できる。しかし「恐れ」は人間の想定を超えてくる。気づけば、目を上げれば、もう目前にまで迫ってきている。その時、僕たちは「今さら何をしても意味がない」と全身の力が抜けてしまう。荒れ狂う湖を目の前に、弟子たちもまさにそうであったのだろう。
この物語を読むと思い出す出来事がある。名誉のために名前をアントニーと伏せておくが、彼は神学校時代からの友人で、大学院生の時は同じ教会に通っていた。そのころ、僕はなけなしのお金で中古車を買ったのだが、ある日免許を取り立てのアントニーが「明日は僕が運転するから助手席で休んでいてよ!」と教会までの送迎を申し出てくれた。
しかし、これが大きな間違いであった。いざ運転をさせるとさながら映画のレースシーンのように彼は操縦し始めた。なぜ空いている高速道路でわざわざ高級車の近くに車を寄せるのか、なぜ信号もないところで急停止をして左右確認をするのか。
「待て! 止まれ!」――そんな声をかける余裕もない。どんどんと迫ってくる危険に僕は「神様、今日までありがとうございました」と気づけば祈りをささげていた。
この時、僕は「恐れ」に包まれていた。流れるように進む車と変わりゆく景色の中、もはやなすすべもなく身を委ねることしかできない、無力な自分に失望していたのだ。なお教会に到着した後、彼は満足そうに「帰りはどうする?」と尋ねてきた。今思えば僕の人間不信はここから始まったのかもしれない。
弟子たちもまた(車の比ではないが)未曾有の恐れに見舞われていた。しかも、彼らの中には漁師出身の者もいた。海に慣れ親しんだ者であれば風向きや波の高さから1時間後の水位を予測できる。しかしここで「激しい波」と訳されているギリシャ語は直訳すると「大地が揺れる」であり、もはや自分の経験や知識など、一切通用しない混沌とした空間に追いやられていたのであった。
だが、ここでボンヘッファーは語る。「人間は恐れてはならないのだ」と。なぜか。
解決を見いだすことができないような状況や不明瞭で罪悪に満ちた状況のただ中にあっても、希望を持っているということが、人間をすべての被造物から区別する点である。
世界は今、大波に覆われている。いや、この世界自体がもはや大波のように人間に襲いかかる。自然も諸秩序も、すでに飲み込まれて何の役に立たない。一体誰が、何が、この状況から僕たちを助け出してくれるのかと嘆きたくなる。しかし、そんな時こそ人間は希望を抱くべきだと語る。
では、その希望とは何なのか。なぜ人間には希望があると言い切ることができるのか。続けてボンヘッファーは言う。「キリストが舟の中にいましたのだ」
嵐の中、すべてが崩れ去ったように見える時、そこにこそキリストはおられる。「この方の前では、僕たちの最大の不安さえ、子どもが親の前で抱く不安のようなものに過ぎない」。なぜなら彼は救い主だからである。
とまぁ、頭で分かったとしても、やはりこの場面を見るとあまりに弟子が不憫で仕方がない。夢と希望を握りしめキリストへ従ったにもかかわらず、目の前の現実は経験したことのない悲惨さ。それならいっそのこと従わない、信じない方が楽なのではないか。しかしキリストは弟子たちに語る。「信仰の薄い者たちよ」
信仰が「薄い」とは何か。反対に「厚い」「大きい」信仰とは何だろうか。嵐に耐え抜く精神力か、あるいは船を漕ぎ進める腕力か。しかし、それであれば「信仰」と何の関係があるのか。
ここでふと頭をよぎるのが、キリストの活動初期の物語だ。マタイ福音書3章でキリストは洗礼を受ける。しかしその直後に待っていたのはマタイ福音書4章、悪魔からの強烈な誘惑であった。「お前は神の子なのだろ?」「お前は神を信じているのだろ?」。嘲笑うかのように、悪魔はキリストを挑発し続ける。洗礼を受けたのに、神に従うと決心したのに、むしろひどくなる現実を前にここでもまた、それなら信じない方が良かったのではと思ってしまう。
しかし、ここでキリストは人間の予想を超えてくる。戦ったのだ。「神の言葉」を悪魔に突きつけた。3回行われた問答の中で、キリストはすべて「〜と(聖書に)書いてある」と言い、足しも引きもせず立ち向かった。すると最後は悪魔の方から引き下がっていったのだった。
この物語が意味するところ。それは、信じれば幸せになりますよとか、あるいは洗礼を受けた瞬間にすべて思い通りなりますよとかの陳腐なお伽話ではない。むしろ想定しうるあらゆる宗教神話をすべて木っ端微塵にする。そんなもの超えていこうと。たとえ目の前の現実が混沌と混乱に満ちていても、神と神の言葉はあなたを守る。この現実の中に立ち続けることが「信仰」なのだと。
飛んで申し訳ないが、ルカ福音書10章のマルタとマリアの物語で最後に、慌てふためくマルタにキリストは「それ(神の言葉)が取り上げられることはありません」(10章42節/新改訳2017)と語った。
この「取り上げる」は、マタイ福音書26章でキリストが十字架にかけられる前日、彼を捕まえようとした大祭司のしもべに対して、弟子が耳を「切り落とした」(26章51節/新改訳2017)と同じギリシャ語である。つまり、キリストはマルタに「たとえあなたに何があろうとも、神の言葉はあなたの血肉にまで染み込んで離れない」ということを伝えたかったのではないだろうか。そしてこの事実に気づくことこそ、信仰ではないだろうか。
だからボンヘッファーは語る。「どうか、嵐と没落の時をよく理解してほしい。それは神がいまだかつてなかったほどに近くいます時であって、まさに遠くにいます時ではないのである」。彼にとっての信仰とは、嵐がなくなることを信じることではなく、嵐の中でこそ、キリストが最も近くにいるという神的現実に立つことであった。
嵐の時、大波の時、予測できないことが起こる時、人々は――僕は、あなたは――恐れに身を委ね、もはや誰も助け手はいないのだと嘆きを超えた嘆きを経験する。しかしボンヘッファーは、聖書は、そしてキリストは語る。「よく覚えていなさい。その時こそ、神はかつてないほどあなたの近くにいる。あなたという舟に今、一緒に乗り込んでいるのだ」と。その神的事実に気づく瞬間、僕たちの信仰はより大きな、豊かなものへと実っていくのだろう。
人間は生きている中で、むしろ予想外のことしか起こらないのではないだろうか? 自分の生活にしろ、あるいは社会を眺めていても。そして時間が経つにつれ強烈な無力感を溺れる。絶望とはまだ痛みを感じている状態だが、ある一定量を超えるともうどうでもよくなってしまう。人生も社会もなるようになる、行き着くところに行き着くのだと。
しかし、もう一度思い起こしたい。この世界の被造物で唯一、希望を持っていることが人間とその他を区別するのだとボンヘッファーは語る。そしてその希望とは、絶望の時になお、救い主がかつてないほど近くにいることなのだとキリストは語る。
そう思うと、まだまだ僕たちにはすべきことがあるのかもしれない。恐れることはない、キリストが舟の中にいる。
【参考文献】
・ディートリヒ・ボンヘッファー、大崎節郎他訳『ボンヘッファー説教全集2』(新教出版社、2004年)

福島慎太郎
ふくしま・しんたろう 名古屋緑福音教会ユースパスター。1997年生まれ、東京基督教大学大学院を卒業。研究テーマはボンヘッファーで、2020年に「D・ボンヘッファーによる『服従』思想について––その起点と神学をめぐって」で優秀卒業研究賞。またこれまで屋外学童や刑務所クリスマス礼拝の運営、幼稚園でのチャプレンなどを務める。連載「14歳からのボンヘッファー」「ボンヘッファーの生涯」(キリスト新聞社)を執筆中。