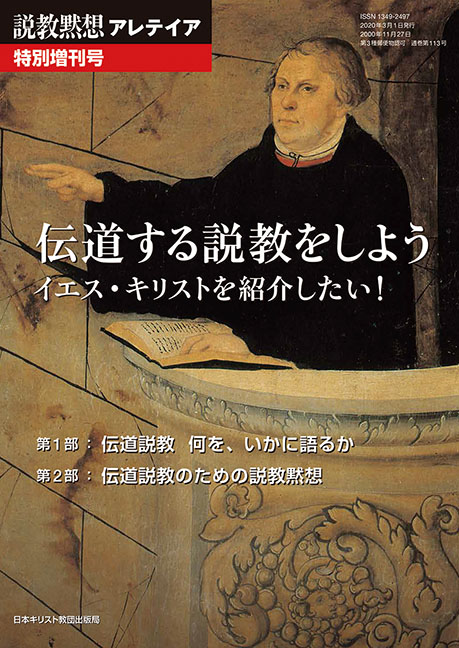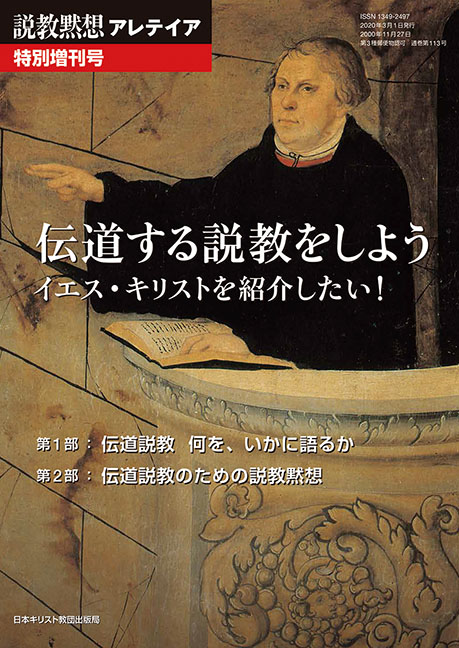「伝道する説教をしよう――イエス・キリストを紹介したい!」を主題に、「何を、いかに語るか」「説教黙想」の2部構成。
「編集後記」を毎号記している加藤常昭が、今号では「説教を課題とするこの雑誌は、このような企画を当然のこととして立てるが、同時に日本伝道史研究とも言うべきものが必要ではないか、ということである。既にほぼ一六〇年に達する日本プロテスタント伝道史を、今生きる教会のパースペクティヴにおいて捉え直すとともに、すぐれた伝道をした人びとの個人史に至る研究があってもよいと思う。特に、キリスト者もおらず、教会も建設されていなかった日本各地で、どのように伝道開拓が行われたのか。今あまり顧みられなくなっている宣教師の働きをも含めて吟味しながら、先輩伝道者、また教会の歩みを捉え直したい。そのひとつの理由は、今われわれは再開拓伝道を始めなければならないからである」と。
そして「このような再開拓の経験を既にしている。敗戦後の伝道である。国土が廃墟となっただけではなく、『虚脱』という言葉が多用されたように、日本のこころも廃墟のようになったとき、戦争の時代に息を潜めて生きてきた教会は生き返ったように開拓伝道を行い、この時期に生まれた教会も多いのである。私もこの時期に伝道者となり、陸軍の元兵舎に住んだ大陸からの引揚者の町に住んで教会を生む働きに挺身した。開拓伝道の楽しみを全存在で味わった。敗戦後ほぼ二○年の間に生まれた教会員が今、年老いて、逝去して、教会を去りつつあり、教会の弱体化を生んでいる。特に六〇年代末からの若者たちの反逆に始まる紛争が教会の伝道をひどく弱体化した。今もなお、その痛手を癒し終えたとは言えないのである」と。
「教会が弱体化し、専任の伝道者を置けなくなった教会が増えている。礼拝を維持することができなくなった教会がある。そういうところで伝道開拓など考えられないという声も聞こえる。老化しつつある教会が開拓伝道などできるであろうか。伝道開拓は生気溢れる若者のわざではないか。高齢になって弱くなる者には重荷でしかないのではないか。……しかし、伝道は神の意思であり、計画であるということを今こそわれわれは納得するのではないか。人間のわざが果てると思われる今日の状況においてこそ、われわれは神のわざに生きるのではなかろうか。われわれの言葉は聖霊に用いられてこそ伝道する神の言葉になることを信じてこそ、伝道の冒険を敢行し得るのではないか」