【書評】 『キリスト教思想史の諸時代Ⅵ 宗教改革と近代思想』 金子晴勇
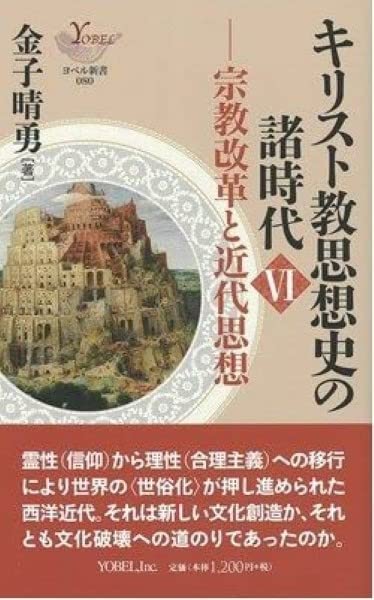
キリスト教思想史家の著者による渾身の著作集『キリスト教思想史の諸時代』。第6巻の主題は「宗教改革と近代思想」。信仰が後退し世俗化が推し進められた1600年から1800年、人間理解はどのように変化したのか。過渡期となるこの時代を把握することは、現在のキリスト教がいかにして現代社会へアプローチすべきかの示唆も与える。
ルターやカルヴァン、エラスムスといった中世の宗教改革者たちはそろって「霊性」を重要視した。これをルターは、「教義学的ではない実験的な知恵」と述べた。またそれを踏まえた人間観として、霊・魂・身体からなる「キリスト教の三分法」も積極的に主張された。
しかし時代が進むにつれ、人間観は宗教的要素を排除し、合理的・哲学的思考から理解されるようになった。それはデカルト、カント、ヘーゲルの登場によって幕開けする。
近代思想の特徴として著者は、以下の3点を挙げる。「近代自然科学の成立による自然の発見」「中世教権組織の社会的絆を断ち切った自主独立する個人による自我の確立」「自我が自然に働きかけて創造した近代文化の理念」。もちろん、これらがすべての思想家たちに完全に共通するわけではない。しかし、教会や聖書の権威から一定の距離を保つことにより、人間各自が有する「自我」の概念が自明になったことは明らかであり、ここから近代思想は産声を上げた。
ヘーゲルを例に挙げれば、彼はキリスト教の有する「神の摂理が歴史を支配している」との歴史観を「理性が世界の支配者である」と言い換え、神的存在による操作・介入の軌跡ではなく世界精神の理性的で必然的な行程こそが世界史であると述べた。ここにもまた人間の理性を中心とする「自我」の牽引が見られる。
その近代思想は、時代を経て啓蒙思想へと変化する。両者の相違点について著者はカント(近代)とシュライエルマッハー(啓蒙)の議論を比較させる。前者が「人格性は人間に共通するもので、すべての個人に認められる尊厳をもっており、万人に妥当する普遍性があっても、他でもないこの普遍性のゆえにかえって抽象的になってしまう」のに対し、後者は「具体的な人格は抽象的なものではなく、個性的なものである」と説いた。ここでの個人とは「(各人が)特定の役割を分担し、相互的な間柄に立つもの」を意味する。
中世から近代にかけて人間理解は神的要素(宗教的表現)が排除され、教会や聖書の権威から影響を受けず自己自身によって規定する営みがなされた。そこには、自我の初穂と脱権威化の潮流が存在する。本書はその歴史を振り返りつつ、人間の精神的営みをひも解く貴重な1冊である。
【1,320円(本体1,200円+税)】
【ヨベル】978-4909871374













