【書評】 『創価学会 政治宗教の成功と隘路』 櫻井義秀、猪瀬優理
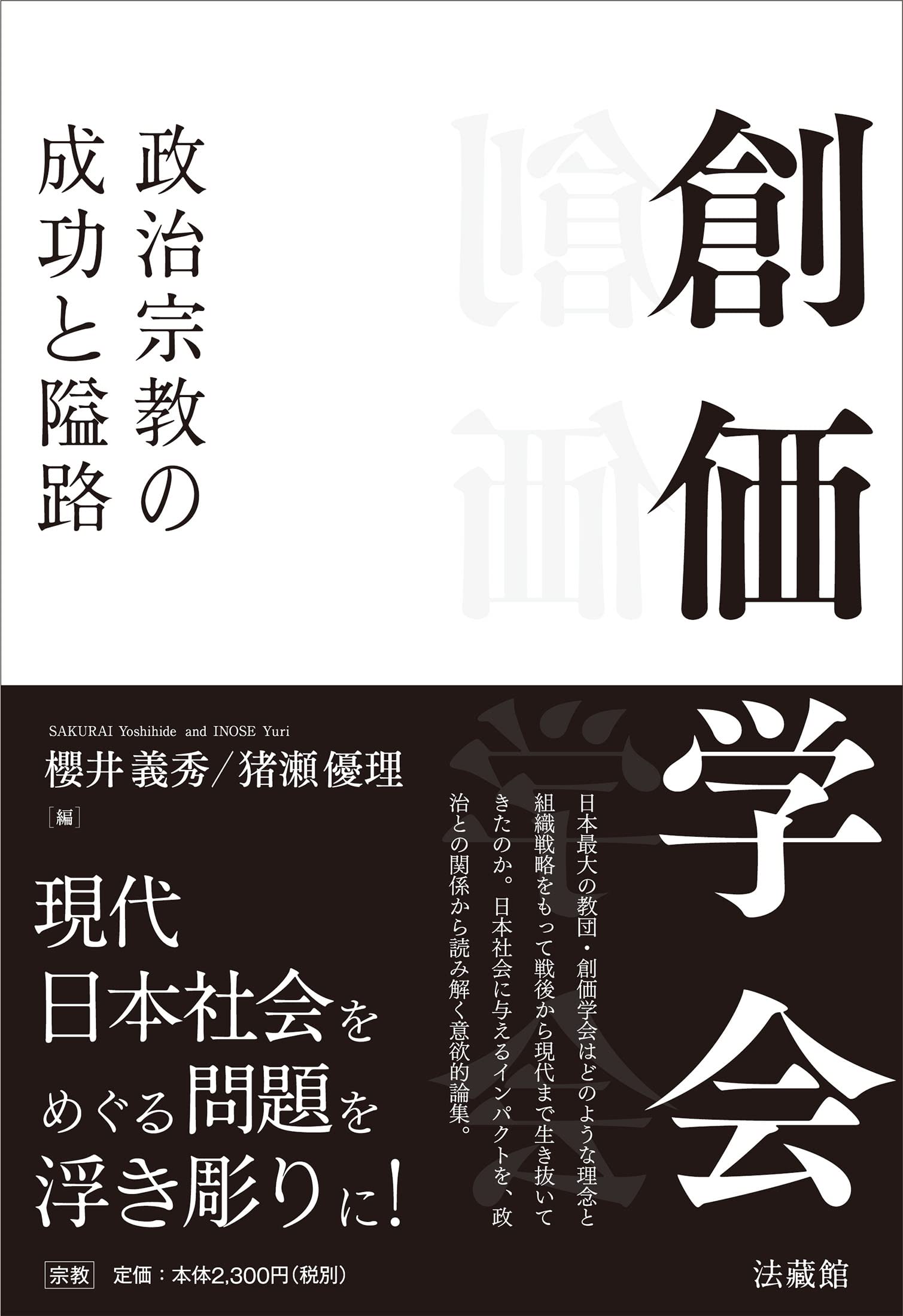
昨年の安倍晋三元首相銃撃事件以来、政治と宗教をめぐる議論が尽きないが、公明党を立党した創価学会に関する論集が出版された。執筆にあたったのはカルト問題・宗教社会学を専門とする3人の研究者。編著者の櫻井義秀氏が提唱する「政治宗教」という分析概念を用いて、宗教集団による政治参加を論じる。
本書の定義によると「政治宗教」とは、教団の組織体制や運動形態、あるいは教説や信仰のあり方を社会変革と結びつけ、政治参加を強力に指向する宗教集団のこと。
「はじめに」で櫻井氏は、政治宗教と政教分離について概説する。
「憲法第一九条で思想・良心の自由と、同第二一条で結社・言論の自由を保障し、同第四四条において国会議員と選挙人を信条によって差別することを禁じている以上、宗教人が政党を結成し、政治参加することを憲法は認めているとみなすことができる。ただし、宗教的理念を前面に出した政治家や政党が特定の宗教団体に利するような政治活動を国政や地方政治において行うことがあれば、関係する宗教団体は権力行為を行ったものとみなせるので、政教分離の原則に違反していると言える」
一般に「政教分離」というと、政治と宗教を分けることだと考えられがちだが、宗教(団体・個人)が宗教的理念を前面に出して政治活動をすることは合憲であり、国家が宗教団体に利益供与をすると政教分離違反となる。したがって、「政治家や政党」が「宗教的理念を前面に出」すことは何ら問題がない。国家が「特定の宗教団体に利するような政治活動を国政や地方政治において行うこと」こそ政教分離原則に抵触する。ポイントは、主語が「国家」である時に政教分離違反となるということだ。
実は、政教分離の「政」とは政治でも政党でもなく「国家」を指しており、慣用句的に「政教分離」といわれているものの、本質的には「国家と宗教の分離」を意味している。最高裁判例でも、「政教分離原則」とは「国家の非宗教性ないし宗教的中立性」を意味すると示され、これは日本の憲法学界の通説(多数説)として定着している。
櫻井氏は本文で二つの文脈を連結し、「政治家や政党」が「特定の宗教団体に利するような政治活動を国政や地方政治において行うこと」が政教分離に違反するとする。さらに、「宗教的理念を前面に出した政治家や政党」が行った違反行為を、「関係する宗教団体」による「権力行為」と「みなせる」と述べる。
キリスト教徒あるいは仏教徒であると公言する政治家が国政に参与していても、その政治家の行為が必ずしも「関係する宗教団体」の「権力行為」になるわけではない。個人と教会・寺院・宗教団体は、常にイコールで結べる関係ではないからだ。また、所属する宗教団体と「関係する宗教団体」とが異なるケースもあれば、政治家が複数の宗教団体と「関係」しているケースもあり得る。
第二章で櫻井氏は、モーリス・アルバックスの「集団的記憶」論を引き、創価学会の創設期における抑圧経験が政治志向性に結びついたことを、時代背景を読み込みながら跡づける。
「実のところ、国家総動員体制に組み込まれた知識人・大学人活動家が、自由に思想信条を表明し活動できなかったにせよ、みなが生命を脅かされるほどの抑圧を経験したわけではない。宗教団体も国家神道や天皇制に適合した皇道宗教となる道を選択したところがほとんどであり、指導者や信者の拘束と教団施設の破壊や私有地の収用まで経験したのは大本くらいである」(第二章 集合の記憶としての「勝利」への道筋)
確かに教団本部を爆破されたのは大本だけだが、「みなが生命を脅かされるほどの抑圧を経験したわけではない」と言い切れるかは議論の余地がある。
第三章では猪瀬優理氏が、創価学会における選挙活動を取り上げる。1961年に結成された公明政治連盟は、創価学会内部の組織であり政党ではなかったが、政治活動の本格化にともない、64年、公明党が結成された。60年代後半に、創価学会を批判する書籍の出版を創価学会・公明党の幹部が差し止めしようとした「言論出版妨害事件」が起こり、社会から批判が浴びせられた。そこで、公明党は党の基本理念を「国立戒壇」「王仏冥合」「仏法民主主義」といった宗教的なものから、「人間性尊重の中道主義」へと変更し、公明党議員は創価学会の幹部役職を兼務しないなど、両者の分離を図った。
1999年、自民党・自由党・公明党の三党による連立政権に参画することとなった。民主党政権を経て、2012年、安倍首相の下で再び自民党との連立政権に参加し、現在に至るまで自民・公明の連立与党体制が続いている。猪瀬氏は、現役学会員へのインタビューや関連書籍等の調査をふまえて以下のように考察する。
「宗教団体に所属する信者は教団の意向に盲目的に従っているわけではなく、教団組織も 多様な反応を示す可能性のある信者たちに対して、如何にしたら組織運営側が思うとおりの行動をしてくれるのか、試行錯誤しながら対応している。……
対する一人ひとりの信者も、日々の宗教活動の中で常に何らかの形で自分自身と教団との関係性や距離を測りながら教団活動に参加している。具体的なそれぞれの場面においては、信者全員が教団の意向と自分自身の信ずるところ、大切にすることをすり合わせながら、自らの行動を選んでいる」(第三章 創価学会の選挙活動と信仰)
第四章を担当した粟津賢太氏は、創価学会の世界観をフェスティンガーの千年王国運動(Millenarianism)の概念で捉え直す。
「創価学会には千年王国運動的な性質がある。立正安国論が一種の予言書であったように、日蓮の仏教を引き継いだ創価学会にはこうした予言的要素は色濃く刻印されている。戸田が折伏大行進という大規模で集団的な折伏活動を推進して教勢を伸ばし、王仏冥合、国家(国立)戒壇を唱え政界に進出したのも、敗戦、民主化、信教の自由の保障という戦後世界において広宣流布が実現するという確信のもとに行われた」(第四章 「破られた契約」――路線変更とその現在)
第五章では猪瀬氏が創価学会における家族像・ジェンダー像を扱い、第六章では櫻井氏が創価学会の成長戦略とその先にある隘路を見すえる。
本書のいずれの論考でも先行研究が参照されているが、猪瀬氏・粟津氏が引用するレヴィ・マクローリン氏の創価学会研究が、日本と海外の先行研究を総覧した櫻井氏の「創価学会研究の視点」(28~54頁)では挙げられていない。何をもって「研究」とするかの基準が論者によって異なるのかもしれない。
執筆陣が宗教社会学の第一線で活躍する研究者であることは疑いないが、「政治宗教」という分析概念が妥当か否か、「政教分離」に関する考え方など、異論を挟まれかねない点も少なくない。本書を機に、他の識者をも交えた活発な意見交換がなされることが期待される。
【2,300円(本体2,530円+税)】
【法蔵館】978-4831877659













