【書評】 『なぜ子どもは神を信じるのか? 人間の宗教性の心理学的研究』 J・L・バレット
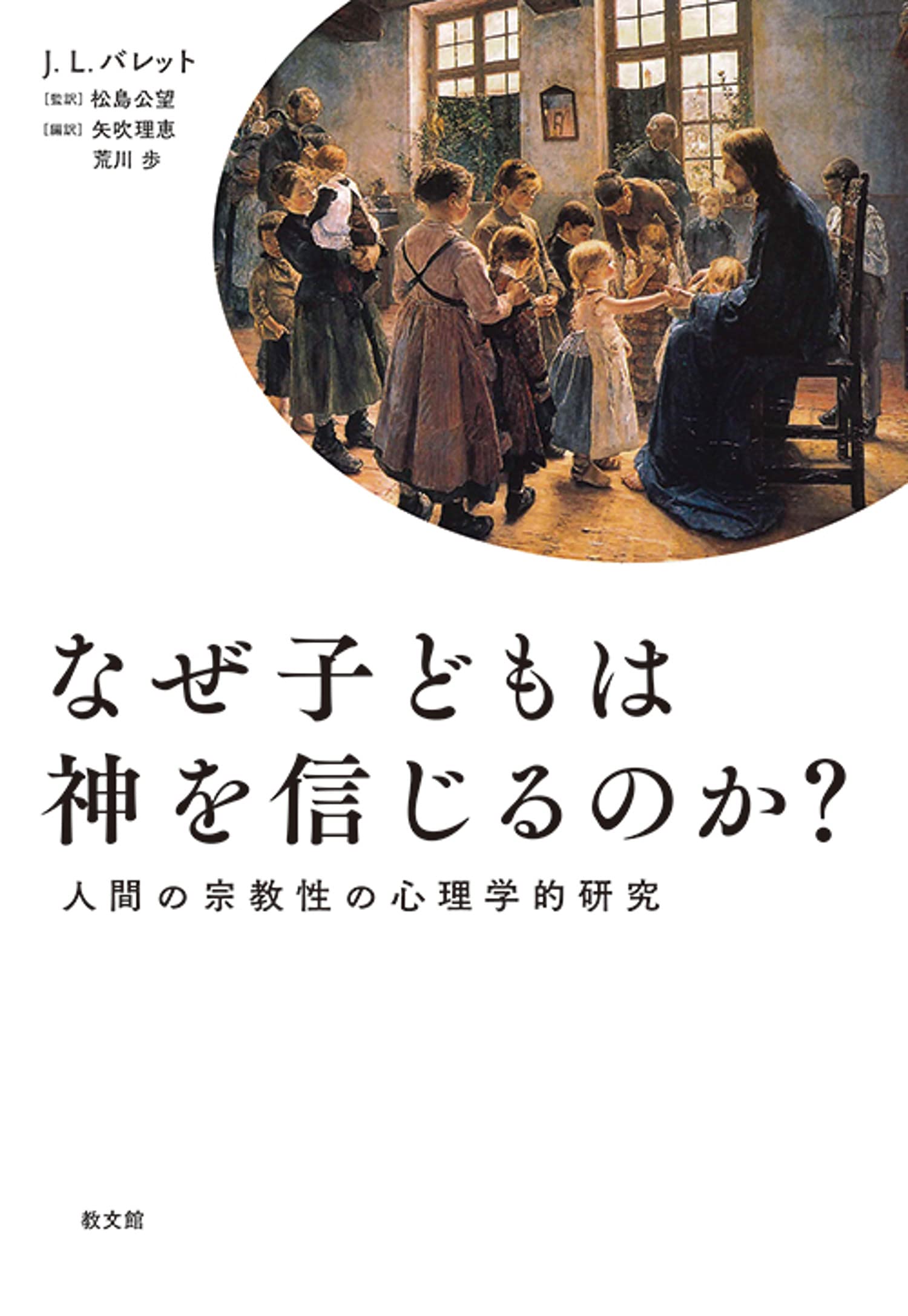
幼い子どもが、無邪気に神について語ることがある。「花や虫は神さまが作ったんだよ」「神さまが見てる」などと大真面目に話すのを見て、大人たちは「両親がそう教えたのだろう」と考える。しかし、両親はそんなことを教えた覚えがないと言ったりする。実際、多くの親たちは子どもに何かを「教え込むこと」が非常に困難であることを体験的に知っている。にもかかわらず、子どもたちは容易に宗教を信じ、時には神への信念を諦めさせるのが難しいことさえある。このような宗教的信念を、子どもはいかにして持つのか。宗教認知科学者である著者が、宗教性の発達に関する研究成果をまとめた。
「私の前の共同研究者一は二人の娘(一番上の子ですらたった8歳)の母親であったが、『私はキリスト教徒ですが、夫は無神論者です。だから子どもたちにはどちらの考えも押しつけないようにしてきました。でも、うまくいかなかったようです。三人の娘は全員、熱心に神様を信じています』……これらを含め、多くの事例は、子どもは生まれながらの信仰者であると私が主張するために挙げたものではなく、偶然や教え込み以上の何かがあることを示唆するものである」(序章)
なぜ子どもが神を信じるのかという疑問に対する、最も単純な回答は「教え込み仮説」である。しかし、親が子どもには何でもたやすく「教え込める」わけではない。そこで考え出されたのが「擬人化仮説」で、1世紀以上にわたり宗教心理学の理論的中心にあった。この考え方によれば、子どもは人間について学び、そこから神を推論する。子どもの推論能力が向上すると、今度は神が人間に似ていないように思えてくる。そのため最終的に、神はあらゆる場所に遍在する、不変の、時空を超えた全知全能の存在として認識されるに至るというものだ。
一方、著者は、子どもが神に関する考えを容易に形成することができるのは、子どもの心のメカニズムが神についての学習に有利な二つの特徴を持つからであるといい、これを「準備仮説」と名づける。このような「準備」メカニズムがあるために、それを土台として子どもはキリスト教など一神教や他の宗教の神概念を理解できるようになっていくと考える。
「近年得られた科学的なエピデンスは、子どもが多くの主要な宗教的信念――とりわけ超自然的存在に関する信念――ヘの受容性を自然的に発達させることを示している……周囲の環境の助けがほとんどなくとも、子どもは超人間的行為者を信じるようになるのだ」(第3章)
「多くの研究の中でも、これまでに述べてきた研究から導かれる宗教性発達の図式は、まず子どもは自然的に、ある基本的な宗教的考えと、それに関連する実践(自然宗教)に惹きつけられ、その後両親が教える宗教的・神学的伝統が徐々にその骨組みに肉付けを行う、というものである」(第6章)
こうした説に対して、宗教を信じることは幼稚であるという見方もある。かつてフロイトが、神への信仰は幼児期の不安が自然界に投影されたものだと主張した。現代では、「教え込み仮説」に立脚し、子どもに神を信じるように教えることは児童虐待に等しいと非難する学者もいる。
クリストファー・ヒッチンスは聖職者について「何世紀もの間、大人はこのように子どもたちを怖がらせて、お金をもらっている。……(地獄について教える逸話があるが)幼い者に向かってこのように嘘をつく人は、きわめて邪悪だ」と述べる。イギリスの心理学者ニコラス・ハンフリーはアムネスティでの講演で以下のように述べた。「子どもには、ナンセンスなことによって心を奪われない権利がある。そして社会として私たちには、子どもをそれから守る義務がある」
オックスフォード大学における著者の同僚リチャード・ドーキンスは、「教師や司祭は、道徳上の罪を犯しておいて、告解による赦しを受けなければ永遠の地獄で罰せられるぞといった類のことを子供たちにいかにももっともらしく吹きこむ。彼らのこうした行ないを『児童虐待』と呼んでもけっして大げさではない」といい、教え込みの代わりに保護者はどうすべきかを提案している。それは、「何」について考えるかよりも、「どのように」考えるかを教えるべきだというものだ。このような見解に対し、著者は反論する。
「しかしながら、若い人々に何を考えるかを教えず、どう考えるかだけを教えるとすれば、 ……幼い子どもたちには困難が生じる。子どもの『人は死んだらどうなるの?』とか『私は生まれる前はどこにいたの?』とか……の質間に、親はこうしたことへの自身の信念に触れずにどうやって答えるのか。教室にいる大学生なら、こういう理由でこう考える人たちもいれば、ああいう理由でああ考える人もいると説明して、『しかしあなたは自分で決めなければならない』と結論づけることができるだろう。……自分の道徳観や形而上的な価値観、またそれらへの関与を、直接的にであれ間接的にであれ、子どもに教えないという理想は、まったくの空想であり、その試みは情緒的にも心理的にも有害であることが証明されるだろう。子どもの心からの質問に答える際に、自分は何を信じているかを親が答えるのを拒否するなら、子どもは愛されて肯定されていると感じるだろうか」(第10章)
著者は、「もし、親たちが自らの宗教的信念をよく考え、それは真実で重要であると考えるなら、愛情のこもっていない方法でそうするのでなければ、子どもたちにこれらの宗教的信念を受け入れることを勧める親に対して、『道徳に反する』または『虐待だ』などと非難することは正しいとは言えない」という。さらに、信仰を持つことは弊害よりも益になることが多いとエビデンスを挙げる。
本書は、子どもの宗教性の発達について12章にわたり詳しく論じた上で、以下のように結ばれる。
「子どもは宗教的思考や実践への強い自然的性向を持った、生まれながらの信仰者かもしれない。……(しかし)あらゆる最善の教育方策が適切に行われ、最善の努力、最高度の誠実さ、保護、愛をもって伝えられたとしても、それでも子どもは無信仰者に育つことがある。……教師として、適切で万全の注意を払ってなすべきことを遂行したら、あとは安心して休みなさい。子どもが生まれながらの信仰者であるとしても、その子どもたちが信仰者として死ぬかどうかは、子どもたちと神の間のことなのだから」
昨年来、元首相の銃撃事件を機に注目された「宗教2世」問題。高額献金による貧困や一家離散、親の世界観に同意しないからと身体的罰で脅すことは言うまでもなく虐待に該当する。親のそうした行為が子どもを篤信者どころか無神論者にさせるという研究も報告されている。しかし、宗教によるすべての教化が排除の対象とされるなら、親は自分が最高の価値を置く信仰や世界観を子どもに一切伝えてはならないことになる。果たしてそれが理想的な子育て・教育なのか。子どもたちが神を信じやすい心のメカニズムを持っていることは、「宗教2世」をめぐる議論に新たな視角をもたらすに違いない。
【2,970円(本体2,700円+税)】
【教文館】978-4764274648













