【書評】 『キリシタン1622 殉教・列聖・布教聖省 400年目の省察』 川村信三、清水有子 編/キリシタン文化研究会 監修
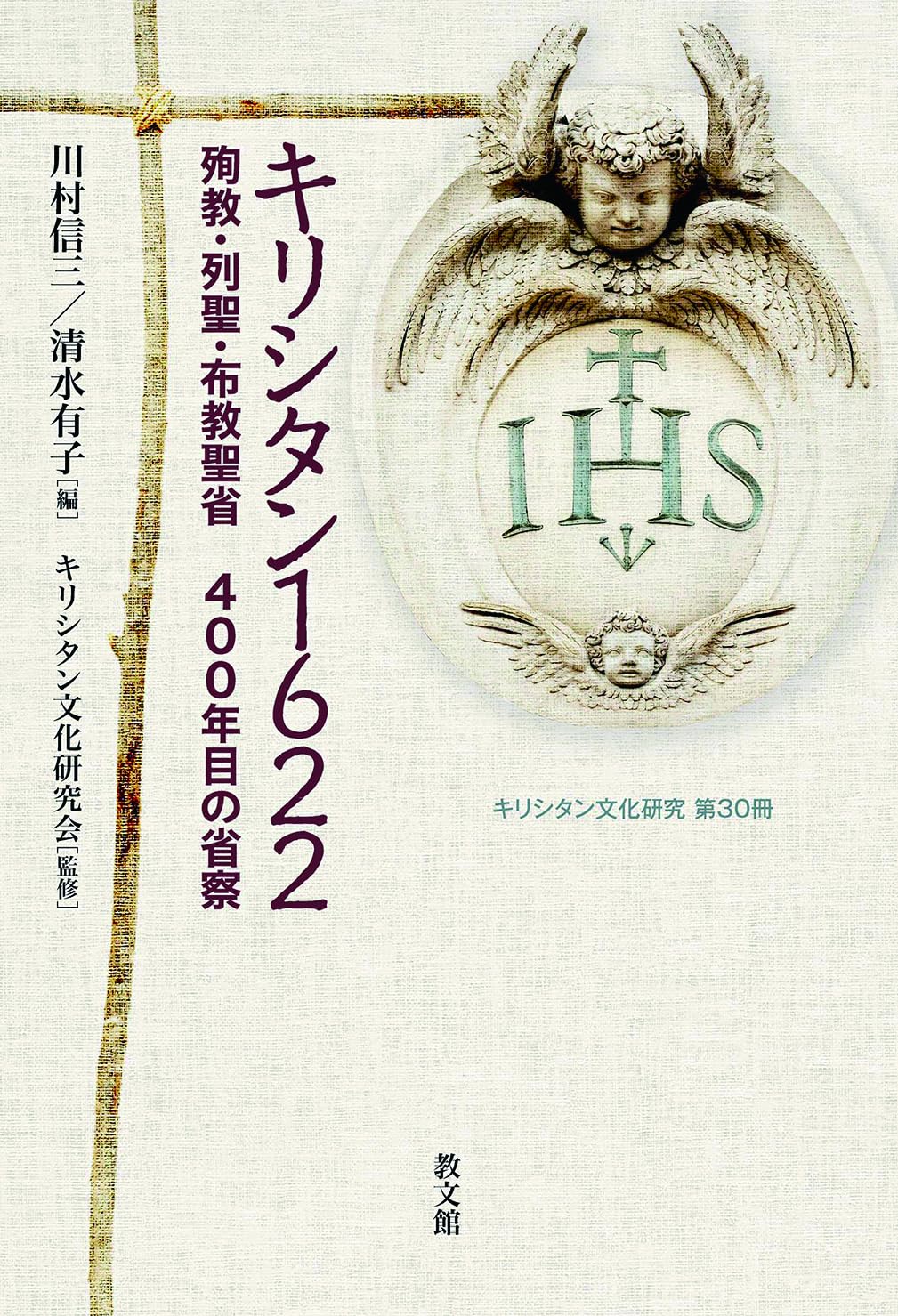
1622年、日本では元和の大殉教が起こり、ローマではイグナチオ・デ・ロヨラとフランシスコ・ザビエルの列聖、教皇庁布教聖省創立がなされた。それから400年となる2022年、キリシタン文化研究会ではこれらの出来事に着目した大会・シンポジウムを行い、そこで研究成果をまとめ本書を刊行した。第一部から第四部に各3本ずつ、計12本の論文が収められ、複眼的な視点によるキリシタン史の再考が試みられている。
第一部では、元和の大殉教に関連して、デ・ルカ・レンゾ、清水有子、竹山瞬太の各氏が論じている。
「日本における托鉢修道会の宣教は、一般信徒に殉教を奨励する点に最大の特徴があった。その教えは在来のイエズス会のそれと比較すると大変厳しいものであったが、一部の篤信の信徒により実践され、殉教の現場を目の当たりにした信徒の間では殉教者を崇拝し、信心を深める傾向が見られた。
しかしそのような信徒の様態は、幕府がキリスト教を『神国』の統治秩序に相反する『邪法』と断定する根拠となり、慶長・元和期の禁教令を誘発するにいたった。この意味において托鉢修道会の来日の重要性は、強調してなお余りあるものがある。しかし幕府はイベリア両国と修道会間に生じた対抗関係ではなく、托鉢修道会の宣教により明確化した、統治秩序に相反するキリスト教の浸透そのものを問題視していたのである」(清水有子「慶長・元和期の禁教・殉教と托鉢修道会」)
竹山瞬太は、最初の日本人司祭である木村セバスチャンを取り上げる。木村セバスチャンは日本人信徒の告解を直接聞き届けることができる貴重な人材であったが、同時に、イエズス会と托鉢修道会との間に繰り広げられた布教論争の主要人物でもあった。
第二部では、元和期の宣教活動に関連して、阿久根晋氏がアントニオ・フランシスコ・カルディンの弘報運動、木﨑孝嘉氏が布教聖省設立を扱い、小俣ラポー日登美氏がロヨラ列聖の意義を考察している。
カルディンといえば、殉教録の著者として知られているが、なぜ日本人殉教者の記録をつぶさに報告したのかは、彼の職責と活動を追わなければ十分に理解できない。
「リスボンを離れた後、カルディンは一六四四年以降一六四六年までローマに滞在した。そこでは……日本管区の歴史と現状の弘報にも力を注いだ。
この取り組みの一環を成す出版物としては、一六四六年の殉教録『血染めの日本の花束』が有名であるが、前年の一六四五年にもカルディンは著作を公にしている。すなわち管区の旧・新双方の布教地を取り上げた嚆矢的作品で、時の教皇インノケンティウス一〇世(在位一六四四~五五年)に献呈した布教史『日本管区報告』である」(阿久根晋「アントニオ・フランシスコ・カルディンの弘報運動をめぐる文脈――イエズス会日本管区と聖ザビエルの『遺功』」)
この頃には、日本は禁教となり、イエズス会の活動の舞台はマカオ以南に移っていたにもかかわらず、「日本」の名が保持された背景には、日本管区代表であるカルディンが、日本における成果を挙げ、管区の健在ぶりを示す目的があったと推察される。
小俣論文ではロヨラの生涯と列聖までの道のりを追う。ザビエルと並びロヨラの名も日本で知られているが、彼が生涯にわたり計8回も異端裁判を受けていたことはほとんど知られていない。ロヨラの列聖はイエズス会にとって特別な意味を持つものであった。「かつてその異端性を疑われていた創立者を、その対極にある聖人の地位にまでいたらしめることは、カトリック世界のみならずイエズス会がヨーロッパ社会全体において立場を確立するために必要であるとみなされていた」からである。
第三部では潜伏キリシタンの信仰に焦点を当てる。宮崎賢太郎氏は、以前から「カクレキリシタンは隠れてもいなければキリシタンでもない」と主張してきたが、その理由を詳しく述べている。中園成生氏は、長年取り組んできた生月島などでのフィールドワークをふまえて、「キリシタン・かくれキリシタン信仰の本質的理解のためには、そのような宗教とムラ・イエ共同体との関係性を歴史的状況として肯定しながら検証を行う必要がある」と指摘する。東馬場郁生氏はモノ(マテリアリティ)という観点から潜伏キリシタンの信仰について考察する。
三人の論者が使う用語が、「カクレキリシタン」(宮崎氏)、「かくれキリシタン」(中園氏)、「(潜伏)きりしたん」(東馬場氏)と異なるところにも、それぞれの考え方の違いが現れているが、論考を読むと、三者の考えはそれほど隔たってはいないことがわかる。それぞれが独立して主張するのでなく、むしろ今回のようにパネルセッションという形で意見を交わすことが、建設的な研究に結びつくのではないかという考えがわく。
第四部では、天下人の自己神格化とキリスト教について、川村信三氏が信長を、タイモン・スクリーチ氏が秀吉を、野村玄氏が家康を、資料をもとに考察している。天下人の宗教やキリスト教観はこれまでも多くの論者によって語られてきたため、決して新しい論点ではないが、独自の観点から改めて深く掘り下げている。
「信長が独特の天下国家論を展開し、そのイデオロギーとしての『自己神格化』を提示し、さらにそれを安土城において目に見える形にしてみせた。あらゆる宗教的、思想的要素を想起させる安土城の内装は、信長が従来考えられていたような宗教破壊者ではなくその統合者として君臨する意志のあらわれとみてまちがいない。統合者にはこれまでにない破格の『神格』が必要となる。その意味では、『自己神格化』と安土築城は天下統一目前の並行現象であったと考えられる。フロイスの記述は、単なる外国人の観察ではなく、天下人の理念の構築の深層を明らかに伝えているものとして貴重な証言とみるべきである」(川村信三「信長『自己神格化』問題の再考」)
所収された論文はいずれも力の入った研究の成果であり、最新の論考であるため、定説とはいえないものも含まれるが、だからこそキリシタン研究の「いま」を物語る格好の論文集となっている。「あとがき」で清水氏が、「キリシタン史研究は確実に変化と進歩を遂げている」と読後の所感を述べているが、そのことを強く感じさせる一書である。
【3,520円(本体3,200円+税)】
【教文館】978-4764261792













