【書評】 『長崎平戸の宗教地誌 キリシタンカトリック在来信仰』 今里悟之
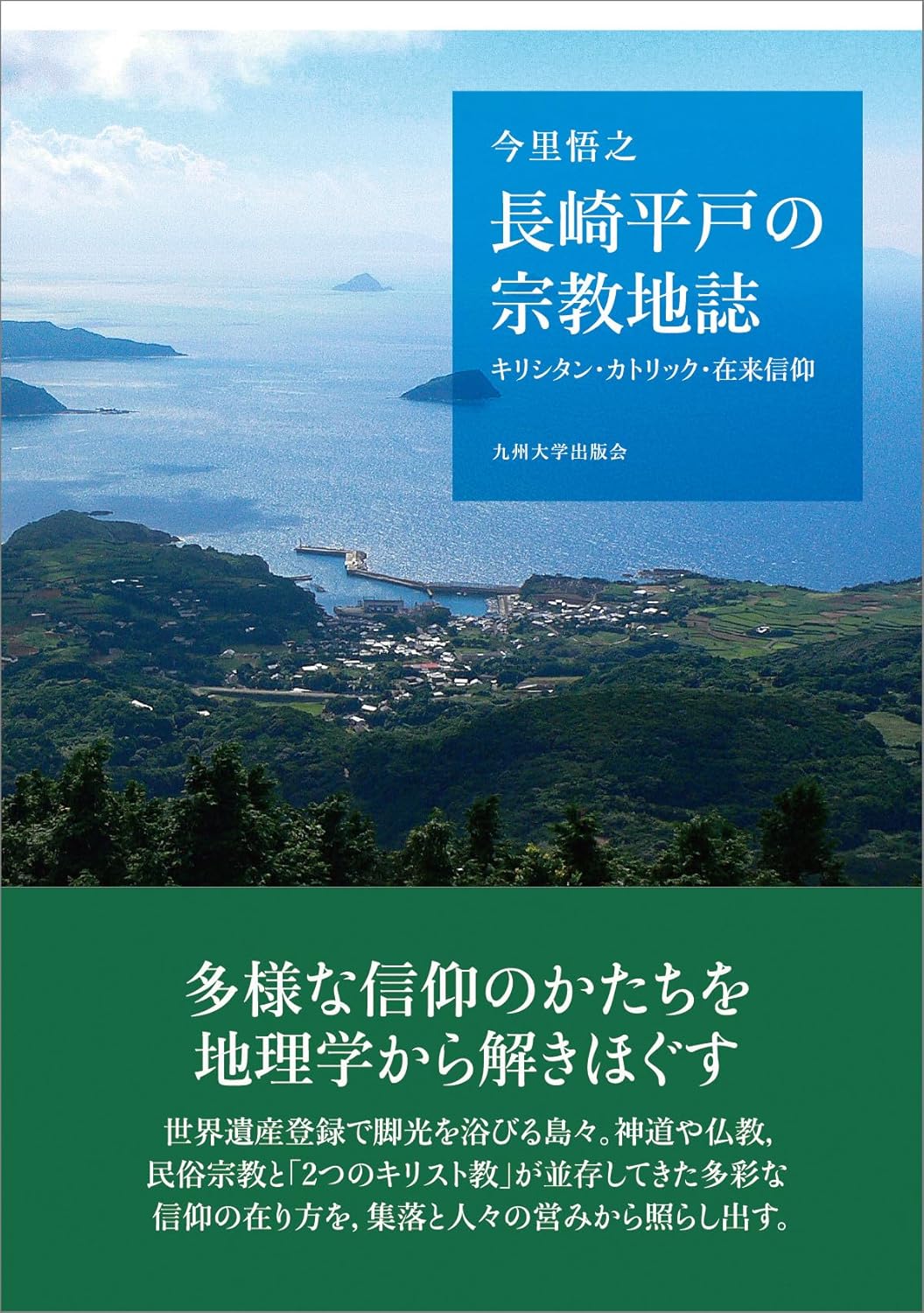
長崎県平戸は、世界遺産の構成要素を持つ他の地域とは違うキリシタンの歴史が刻まれてきた。ひと言で「潜伏キリシタン」といっても、「平戸・生月」系と「外海・五島・長崎」系があり、南島原や天草ではまた異なる歴史が刻まれてきたとされる。さらにはそれぞれが独自にその地の風習や文化と融合し、地域に根差した信仰のかたちを作り上げてきた。本書では、その中で平戸にスポットを当てるが、著者の専門は人文地理学。地理学の観点から平戸の宗教的景観を読み解いていく。
「本書では、神道や仏教の諸宗派はもちろんのこと、かつての潜伏キリシタン、カトリック教会、修験道の山伏、琵琶法師、祈祷系の巫女(シャーマン)、あるいは複数の新興宗教など、実に魅力的な多数の宗教的要素が混在する長崎県平戸地域を対象として、一方では地域の内外を広く俯瞰しながら、他方では個々の集落や人々に深く接近したい。このような一見すると極めて混沌とした、外部者から見ればしばしば驚嘆せざるを得ないような現状を、可能な限り体系的に把握することで、生活者の次元における日本宗教一般の包括的な理解に、 特に地理学の立場から貢献することが、本書の第1の目標となる」(序論)
日本の宗教地理学は、宗教学・歴史学・民俗学などの諸分野による研究蓄積の基盤の上に展開し、具体的には宗教都市、巡礼・参詣、村落の宗教組織、墓制、聖域、信仰圏などといった観点から研究されてきた。しかしそこに占めるキリスト教の割合は小さく、地理学×キリスト教という研究はあまり活発に行われてこなかった。
「本章では、……平戸地域の大きな特徴の一つとなってきたキリシタン信仰に着目し、組 織編成の原理とその空間構造の型について検討する」(第5章 キリシタン信仰組織の編成 原理と空間構造)
著者は調査対象として平戸の三つの町をピックアップし、綿密な実地調査を通して宗教分布を地図にまとめる。また、宗教的景観を形作る要素(寺社や教会、祠や石造物、墓地、キリシタン伝説地など)がどのような信仰上の原理によって、その土地に矛盾なく統合されている(あるいは矛盾を抱えながら散財しているのか)を分析する。
「各事例の検討を踏まえて、3つの町の社会地理的条件が影響を与え得る、それぞれの宗教共同体の領域性を比較し、3つの町の事例を互いに位置付ける。具体的には、①宝亀町の在来信仰戸、②宝亀町のカトリック戸(宝亀教会)、③ 木場町木場区の矢保佐神社の在来信仰戸、④ 同じく八尾神社の在来信仰戸、⑤ 木場町神馬区の在来信仰戸、⑥ 木場町全区のカ トリック戸(紐差教会)、 ⑦根獅子町のキリシタン戸、以上の総計7つの宗教共同体である。
まず宝亀町は、対照的な二つの宗教共同体が共存する事例と位置付けられる。宝亀では、既存の在来信仰の共同体に加えて、特に近代に入ってカトリックの共同体が成長した。宝亀の先住者として、猿田彦神社によって統合されてきた在来信仰の共同体は、村境を保持して強い領域性を示してきたが、後の移住者としてのカトリックの共同体は、領域性を表徴する ものは全く保持してこなかった。宝亀町の自治組織は、この宗教区分に従って編成されて きたが、在来信仰戸の多くは町内の中心部に集中し、ほとんどのカトリック戸は周辺部に散在している」(第6章 民俗的填界の領域性と社会的地理的条件)
「結論」では、以上のような緻密な調査結果をもとにした考察が述べられている。平戸には、16世紀のキリシタン時代と19世紀の開国期の二度にわたりキリスト教が伝来したわけであるが、それをヨーロッパの事例に即して解している。
「ヨーロッパのカトリックは、その歴史の中で土着信仰の神々を取り込み、キリスト教に収飲させて聖人に置き換え、一神教の枠内で諸聖人が機能を分担する『多信仰』(多神教ではないとして発展し(会田・谷1969)、場合によっては残存した土着信仰の並存も黙認して きた(竹下2023)。その点では、第4章から第7章まで検討した通り、神道や民俗宗教などの在来信仰要素と融合し、なおかつ在来信仰も並存させてきた平戸地域のキリシタンは、ヨーロッパのカトリックに類似する面が窺える。これに対して、江戸末期から明治初期にかけて再び伝来したキリスト教は、体系化がひとまず完成した形で受容され、キリシタン信仰の ように在来宗教と融合することなく、例えば在来の農耕暦とも全く繋がりを持たないまま、今に至っている」
ところで、本書の冒頭には、遠藤周作『沈黙』の中のフェレイラのセリフが掲げられている。「彼等が信じていたのは基督教の神ではない。日本人は今日まで」「神の概念はもたなかったし、これからももてないだろう」というものだ。そして、「結論」の最後はそれに対応する言葉で結ばれている。
「19世紀後半以降に成立した、九州北西部のカトリック集落では、パリ外国宣教会の組織的な指導によって、17世紀の元イエズス会宣教師のフェレイラが当初望んだように、人々がキリスト教の神の概念を持つに至り、教会建築を頂点とした集落空間構成を保持してきた。しかしながら他方で、フェレイラがおそらく目の当たりにした在来信仰集落、そしてキリシタン集落でさえも、キリスト教の神の概念に厳格に基づく信仰形態や集落空間構成を、少なくとも平戸地域においては今日まで持たなかったと考えられる。ある一面から見れば、 時空を超えた2つのキリスト教の断絶は、『神の沈黙』によっては表現できないほどに、あまりに大きかったと言うべきかもしれない」(以上、「結論」)
地理学的観点から宗教的景観の成り立ちを分析した本研究の意義は小さくないが、「結論」の結びの部分に関しては異論が出ることが予想される。遠藤の『沈黙』における「神の沈黙」と、著者が考えている「神の沈黙」は同じものなのだろうか。文脈からすると、宣教師が理想とした「キリスト教の信仰形態と集落空間構成」が昔から今に至るまで平戸には実現されなかった、と本研究では結論づけているようだ。その点に関して異論はない。
しかし、『沈黙』の「神の沈黙」に関するスタンダードな解釈は、神は沈黙の中で人の弱さに寄り添い、自分を踏みつける者を赦していたというものであり、遠藤自身、沈黙の中で語っている神の「声」を描いたのだと作品解説をしている。そうした解釈に立つと、「『神の沈黙』によっては表現できないほど」「断絶が大きかった」の本意が読めない。著者にはまた別の「神の沈黙」解釈があるのか。冒頭と結論で小説の世界を引き合いに出し、「神の沈黙」に関する記述で全体をはさんだことで、本研究で明らかにされたことが少々かすんで見えてしまったことは否めない。
【5,940円(本体5,400円+税)】
【九州大学出版会】978-4798503707













