【書評】 『隠された聖徳太子 近現代日本の偽史とオカルト文化』 オリオン・クラウタウ
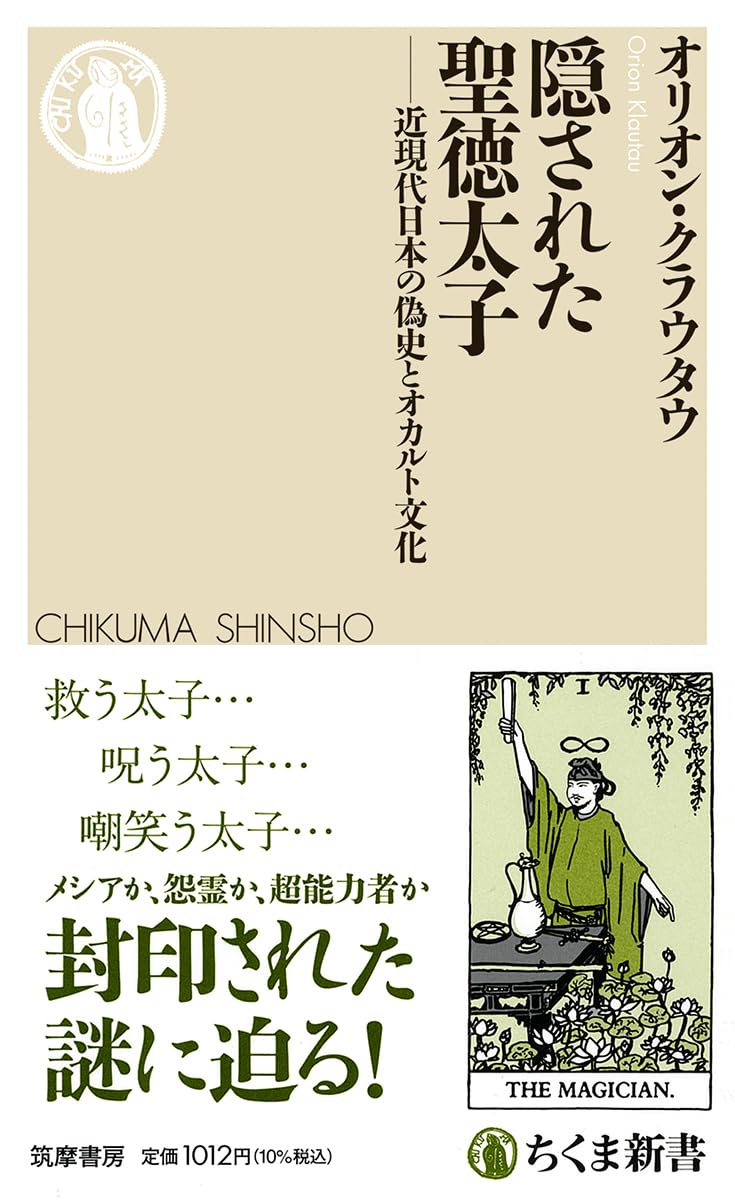
近現代の偽史・オカルト言説に焦点を当てた本が話題を集めている。著者は東北大学で教鞭をとる宗教学者。近代仏教やエソテリシズムに詳しいが、本書ではそうした幅広い知識を土台に「隠された(オカルト)聖徳太子」像を扱う。聖徳太子といえば、日本で最もポピュラーな仏教保護者であるが、その人気ゆえにさまざまな人々のインスピレーションを呼び覚まし、「トンデモ説」「トンデモ本」の源泉ともなってきた。
「いわゆるトンデモ本は、アカデミズム――あるいは「科学」――の権威を借り、その成果の意味を場合によって曲げつつも、自身の物語の根拠として好都合なところだけ用いる。これは、いわゆる『偽史』の特徴の一つであると言えるだろう。
しかし、これは偽史のみならず、アカデミズムの中で極めて水準の低い歴史研究に見られる特徴でもある」(まえがき)
聖徳太子という存在が人々の心を動かし、数多くの偉業が彼によるとされてきたことは事実である。近現代に形成された太子にまつわる偽史もまた、その時代の人々の何らかの表現だったといえよう。著者は、歴史的事実にそぐわない異説を単に「トンデモ説」と切り捨てるのではなく、その裏面に秘められた意図を考慮し、ある特殊なニーズに応えるために作られた太子像の「歴史」であったとしている。
オカルト聖徳太子像の形成に不可欠な要素は、古代日本にキリスト教が伝わり、太子の側近である秦氏がユダヤ人でキリスト教徒であったという話。日ユ同祖論と呼ばれる言説だが、まず、その発生から展開までを著者は丁寧に解説。イエスが馬小屋で生まれたことと「厩戸」皇子との近似性を最初に指摘したのは久米邦武だった。ただし久米は古代日本にキリスト教が渡来したとは言っていなかった。それを言い始めるのは佐伯好郎である。佐伯は1908年、古代の文献に現れる帰化人の秦氏は「百済人」でも「支那人」でもなく、「猶太(ユダヤ)民族」なのではないかと述べ、その証拠として広隆寺そばの大酒神社や「伊佐良井」(いさらい)と呼ばれる井戸、日本とユダヤ人の習慣等を挙げた。
「佐伯は当時の常識を覆す、かなり大きなことを述べたものの、史料的な根拠は上記のような非常に間接的なものであったため、当時の学界が佐伯説を真面目に受け入れることはなかった」(第一章 一神教に染まる聖徳太子)
この時点で佐伯は、秦氏が「景教徒」だとかネストリウス派のキリスト教徒だとかは述べておらず、ユダヤ人だと言っただけだった。しかし時間が経つにつれ、彼の説は拡張されて景教徒渡来説になり、似通った主張をするゴードン夫人の後押しを受けて、矛盾を突かれると微調整して、最終的に聖徳太子を巻き込んだ言説にまで発展していく。
「もちろん、キリスト教の知識を有する人間が日本列島に渡ってきたこと自体は可能性のあることで、佐伯が著作中で述べるように、『続日本紀』に名前が明記されるペルシア人の李密翳(生没年不詳)がその好例である。飛鳥時代から続いた大陸への朝貢使の人間が、キリスト教の知識を得て帰国した可能性も否定できまい。しかし、そのような可能性を根拠として、秦氏はユダヤ民族、空海の大日観にはキリスト教の唯一神からの影響がある、親鸞の妻帯も実はネストリウス派からの影響、といったような一連の結論を導くのは、また別の次元の話であろう」
「じつは、アカデミズムの主流から(やや)離れた聖徳太子の多くの異説は、彼の秦氏との関係が起原となる」
1911年刊行の佐伯の著作『景教碑文研究』以降、日本文化の起原をユダヤ教あるいはキリスト教の伝統に見出そうとする書籍が多く世に問われていく。木村鷹太郎、酒井勝軍、小田部全一郎、中田重治などである。ではどうしてこの時期に、これらの論者たちはなぜ古代日本への聖書的一神教の影響を主張したのだろうか。彼らにはどんな思惑と必要性があったのか。
「その基本的動機の一つとして、提唱者のキリスト者としての信仰があった。上記の人物はほぼ全員キリスト者であり、その主張は伝道の基盤形成を目的とした」(以上、第一章 一神教に染まる聖徳太子)
つまり、日本こそが〝真の〟キリスト教国であり、それを日本人自身が知ることでリバイバルが起こり、世界においても偉大な使命を果たすことができるというアイデアに、彼らは日本宣教の突破口を見出した。それゆえ、「古代日本への聖書的一神教の影響を主張しなければならなかった」のである。彼らの主張によれば、実は天皇家もユダヤ=キリスト教を奉じてきたのであり、キリスト教は外来宗教ではなく、日本古来の宗教とされる。ナショナリズムが高揚する社会のなかで、こうした主張はキリスト教を正当化するのに役立った。彼らの言説が一般の人々の関心を引きつけた所以もそこにあったと考えられる。
戦後になると、池田栄、山本七平、マーヴィン・トケイヤーといった人々が登場し、ユダヤ人とされた秦氏のイメージや太子像が、昭和戦前期とは違う形に変化。1948年には手島郁郎が「キリストの幕屋」を起こした。
「手島が最も探求していたのは、恐らく、西洋を介さないキリスト教の体験である。その信仰のルーツへ回帰する際に手島が着目したのは、『日本人』のアイデンティティのルーツであり、記紀神話など神道の古典がそこで重要な役割を果たすようになった。つまり、ユダヤ教への憧れと、日本精神への愛着という両要素をベースとしていた手島の思想は最終的に、多くの他の論者と同じく秦氏の正体性をめぐる思索へとつながっていった」(第三章 ユダヤ人論と怨霊説)
手島は佐伯の秦氏論に拠りながら、「秦河勝がユダヤ人の景教徒」であることの実証を試みた。また、「キリストの幕屋」では毎年、イスラエルへの大巡礼を行い、1967年の「六日戦争」(第三次中東戦争)の際には、イスラエル援助のため手島は弟子まで派遣する。
聖徳太子像に関しては、「法隆寺=太子鎮魂の寺院」と唱えた梅原猛の怨霊説も忘れることができない。1971年に発表された『隠された十字架』はベストセラーとなり、太子のイメージに計り知れない影響を与えた。オカルトブームに乗り、聖徳太子を題材とする超古代史本の発刊も相次いだ。さらに80年、梅原の本を読んだ山岸涼子が『日出処の天子』の連載を始め、ここに超能力者としての太子像が誕生する。超能力者の太子像は、91年、五島勉の『聖徳太子「未来記」の秘予言』によって予言者というバリエーションへとつながった。五島は元々キリスト教(正教)の家庭に生まれ、創価学会の活動を好意的に描く作品で世に出たが、73年にノストラダムス本で一躍有名になった。『聖徳太子「未来記」の秘予言』では、神が道を定めたキリスト教ではなく、人間が道を決めていく仏教に救いのカギがあるのではないかと締めくくられている。
最近では、「ユダヤ人埴輪」を提唱する田中英道(東北大学名誉教授)が聖徳太子に関する本を2023年に出版している。そこでは蘇我氏の出自をユダヤ系のキリスト教とし、秦氏は原始キリスト教であるとされている。
明治・大正期のキリスト者が、日本の古代史とユダヤ・キリスト教との間につながりを見出そうとした背景には、宣教を成功させたいとの願いがあった。それがどんなに純粋な思いからであったとしても、強い「願望」は、歴史的事実を等閑視してでも自分が望む方向に古代史を解釈したいという「欲」に発展することがあり、注意が必要だ。
本書は聖徳太子のオカルトイメージの変遷を追ったものだが、同時に、日本人のユダヤ・キリスト教に対する憧れとコンプレックス、キリスト者の抑えがたい「願望」を映し出す鏡ともなっている。日ユ同祖論は形を変えつつ、今も日本のキリスト教界の一角で主張されている。
【1,012円(本体920円+税)】
【筑摩書房】978-4480076212













