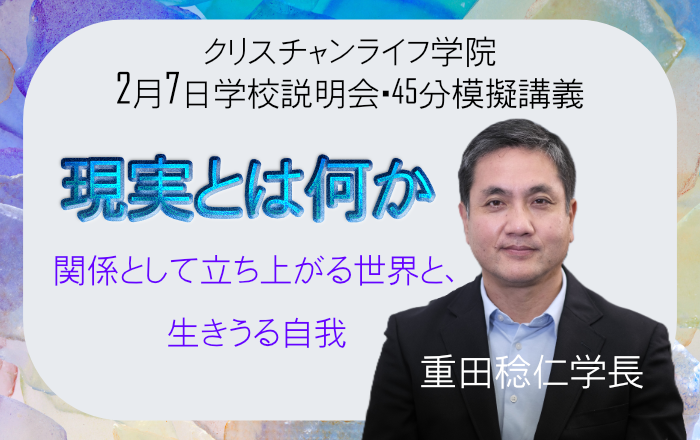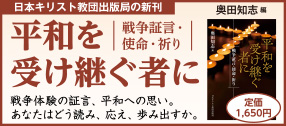【書評】 『キリスト教入門の系譜』 岡本亮輔

入門書が紡いだもう一つの日本キリスト教史
日本の近現代キリスト教史を「入門書」という独自のレンズから再構成した意欲作。キリスト教史や教会史の概説書はこれまでも数多く存在したが、入門書という読書文化そのものを軸に歴史を描き出す試みはありそうでなかった。内村鑑三を出発点に、賀川豊彦、遠藤周作、渡辺和子らを経て、現代のSNSを駆使する発信者までの系譜をたどる構成や、誰がどのようにキリスト教の信仰や思想を「紹介・翻訳してきたか」という受容史に光を当てた点、教会史・思想史・出版文化史を横断する独自性も際立つ。
著者は宗教社会学の研究者であり、信仰当事者ではない立場から日本のキリスト教を概観する適度な距離感が、教派や神学的立場に偏らない視野の広さを生む。カトリックとプロテスタントを横断し、入門書という共通項を通じて思想と人物を結びつけていく手法は、既存の教会史とは異なるダイナミズムを読者に提示する。随所に差し挟まれる「秀才、燃ゆ」「みんな悩んで大きくなった」「マリア様が見てる」「尊すぎてしんどい」などのキャッチ―な見出しも小気味よい。
内村鑑三を狂言回しのように据え、そこに連なる多様な書き手たちが登場し、まるで1本の大河ドラマを観ているよう。登場する人物の著作や思想は、単体でも膨大な研究対象にもかかわらず、それらの受け継がれてきた知的営みの連鎖が一筋の物語として理解できる。入門書の歴史をたどることで、結果的に近代日本の出版文化の変遷まで見えてくる点は、キリスト教関係者のみならず広い読者層にとって価値があるだろう。
同時に、今日のキリスト者にも新たな問いを投げかける。信者数が少数派である日本において、教会の外側に向けて語り続けてきた先人らの努力は正当に評価・継承され、直面する課題は克服されてきたのか。これだけ膨大な遺産を有効に活用してこられたのか。さらに、そうした入門書の数々に触れる読者がなおも敷居をまたげずにいる教会とは何なのか。
同じ中公新書で9刷を重ね売れ続ける加藤喜之氏の『福音派』現象と合わせて、キリスト教の動向に知的関心を寄せる「見えない『かくれ信徒』」「シンパ層」「ファン以上信者未満」をどう捉えるべきか、改めて考える機会としたい。
【1,155円(本体1,050円+税)】
【中央公論新社】978-4121028938