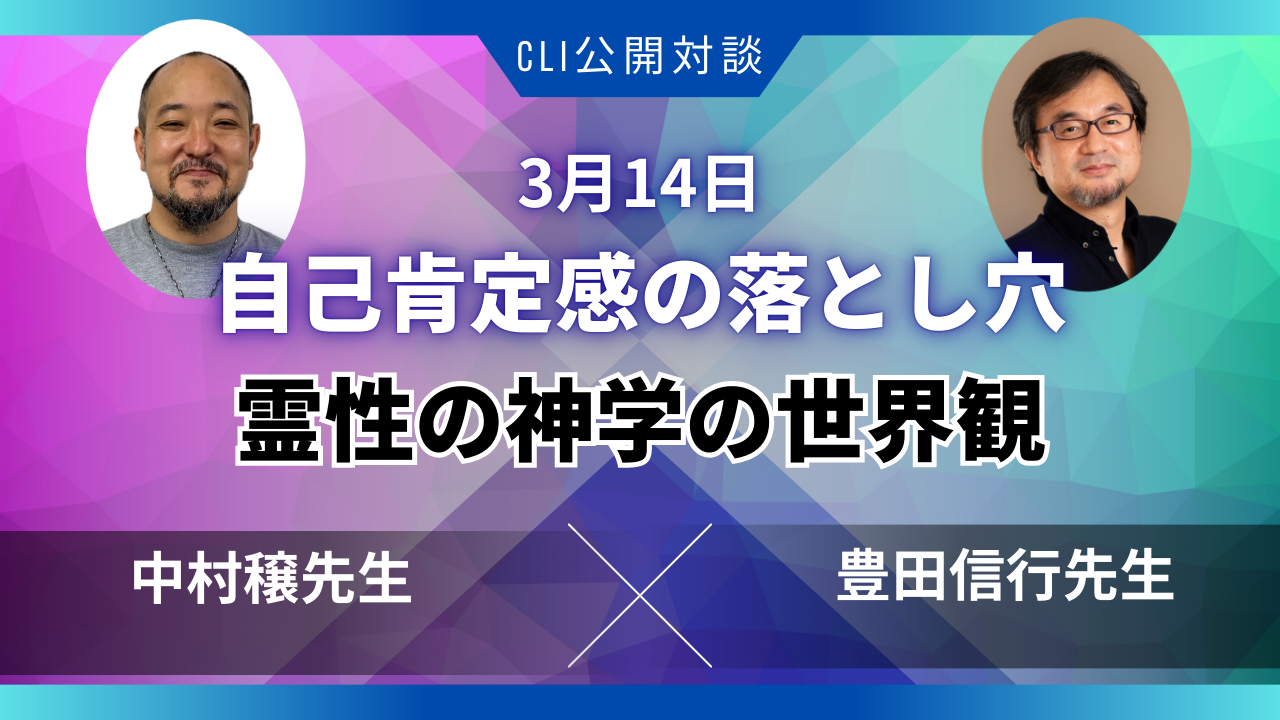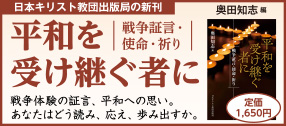【映画】 いま相対化される危機 第38回東京国際映画祭/第26回東京フィルメックス 2025年12月5日

東京都心ではこの秋、東京国際映画祭と東京フィルメックスが例年通り開催された。コロナ禍中には縮小開催や開催地移動、プログラミング・ディレクターの交代など目まぐるしい変化に晒された両映画祭も、この2、3年で各々に落ち着きを取り戻してきた感がある。昨年本紙では両映画祭をめぐり「《母と娘》に映り込むもの」という通底テーマを見いだしたが、今年も女性の内面や関係性に焦点化した上映作品は変わらず多く、女性監督の顔ぶれも多彩となった。これとはべつに、今年とくに感じられたのは、目前で起きている事象をいまこの瞬間から切り離し、距離を置いて見つめ直そうという試みが目立ったことだ。
例えば『パレスチナ36』は、1936年のパレスチナでユダヤ人の大量入植を受け、互いに宥和的であった人々の心情から民族的アイデンティティが芽生えだすさまを描く。本作が、今日停戦が宣言されながらも小規模な戦闘も報じられるガザの紛争を踏まえて制作されたことは言うまでもない。その緻密にして明解な秀逸構成は、1948年のイスラエル建国(ナクバ=大災厄)を超え現代史全体へ時間軸を十全と拡げており、今年の東京国際映画祭コンペティション部門グランプリ獲得も納得の充実作と言える。
時間軸の拡張という点では、実力派の監督たちが今回は揃って歴史劇を送り込んできたことも印象深い。東京国際映画祭の常連であり母国フィリピンの社会問題を題材としてきたラヴ・ディアス監督は今回『マゼラン』で文字通りに16世紀の世界周航を描き、スペインの名匠アレハンドロ・アメナーバル監督作『囚われ人』は、16世紀末アルジェで虜囚生活を送るセルバンテスを主人公に据えた。香港のピーター・チャン(陳可辛)による新作『She has No Name』では、日帝時代から国共内戦へ至る上海で夫殺しの容疑がかかる主婦をチャン・ツィイー(章子怡)が熱演する。『トンネル:暗闇の中の太陽』は、ベトナム戦争末期のベトコンによるトンネル網での戦闘をこのうえなく仔細に再現する。
列強の植民地主義から帝国主義、東西冷戦を背景とするこれらの題材がいま選ばれるのは無論、覇権国の野心がむき出しとなったコロナ禍以降の世界情勢を投影するものである。そしてこれらが今日現在の戦場や渦中の問題への焦点化といった直接的なアプローチを避ける趨勢には、誰の予想にも反して長引くロシア―ウクライナ戦争を始めとした、直の訴求が何の成果も挙げない事態への戸惑いを超え、より広い射程で見つめ直す必要とでも言うべき共通認識が感覚される。
4年前の東京フィルメックスで『ジョージア、白い橋のカフェで逢いましょう』により最優秀作品賞を獲得しているジョージアのアレクサンドレ・コベリゼ監督作『枯れ葉』は、古い携帯電話のカメラで全編が撮影され、解像度の低いその映像は個別の差異や現在と過去の境界をも曖昧にする。映像の質感を大切にする流れにおいては旧式の16mmフィルム撮影を採用する映画監督も少なくないが、3時間に及ぶ映像のすべてへ〝古いデジタル〟の質感を纏わせることで観客を未知の体験に誘う実験性は新しく意欲的だ。一方アメリカ映画『アトロピア』は、海外派兵を念頭に米国内で再現された架空のコーカサス都市を精細に撮る。そこで働く移民たちや訓練する若き米兵たちの醸すリアリティは、それ自体が未来の戦争を前提としておりどこか浮遊感を帯びている。
東京国際映画祭と東京フィルメックスでの上映作を、昨年まで同様に本稿では敢えて区別なく扱っているが、両映画祭はむろん相異なる歴史と文脈があり、個別の傾向性をもつ。それでも継続性や開催規模等の観点から日本を代表する存在と言える両映画祭に、共通する主題や徴候を読み取ることから得られるものは依然ある。この意味では中華系映画の興隆もまた、近年見逃せない傾向のひとつと言える。例えば今回の東京国際映画祭では《台湾電影ルネッサンス2025》、東京フィルメックスでは《プレイベント:香港ニューウェーブの先駆者たち》と題して各々特集企画が組まれた。これらはかつて1980年代から90年代にかけて日本でも映画ファンを賑わせた台湾新電影(台湾ニューシネマ)や香港新浪潮(香港ニューウェーブ)を受けたものだが、いずれも即時完売となる上映回が出る人気ぶりを示した。
こうした人気傾向は、開催都市である東京そのものの変容とも密接に関係する。というのも、実際に劇場で鑑賞すれば一目瞭然なことに、観客の過半を外国人が占めるケースはすでに珍しくなくなっている。映画祭会場ではしばしば監督や出演俳優によるQ&Aも催されるが、観客の質問が外国語で為され、通訳が逐次日本語訳する逆転現象も両映画祭では日常化して久しい。『黒衣の刺客』などで知られる人気俳優スー・チー(舒淇)の初監督作『女の子』(女孩)上映回などは、銀座マリオン上階の800席近い有楽町朝日ホールを満席で埋める観客の大半が中国語話者であったことが、劇中の反応からも如実に窺えた。また大陸中国の映画に関して言えば、中国本土では上映規制がかかる作品を、両映画祭で観るために来日する中国語/広東語話者も顕著な増加傾向にある。
中華映画という括りでは、華僑移民を描く作品の多様化も見逃せない。シンガポールやマレーシアの映画で日本へ来るものといえばかつては文化混淆をメインテーマとするものが主流であったが、息子の暮らすカナダへ移住するため愛車を手放す高齢男性を主人公とするシンガポール映画『老人と車』(老破車)や、父の葬儀のためマレーシアへ帰国する青年が価値観ギャップに苦心する『人生は海のように』(人生海海)など個の道行きを前面に出す作品群において、文化的な背景は小さな一要素へと退いた観が強い。華僑移民の苦境を質実に描く『ラッキー・ルー』(幸福之路)の舞台はニューヨークだが、台詞はほぼ台湾華語で占められる。台湾系米国人の監督ツォウ・シーチン(鄒時擎)が台北で撮った『左利きの少女』(左撇子女孩)は、夜市で働くシングルマザーとその幼娘の生き様を力強く映すが、異境に暮らす者の渇いた目線が夜市を換骨奪胎するからこそ可能な描写と言えるだろう。
パリに暮らすイラン人女性監督が、ガザで暮らす24歳女性ファトマとのビデオ通話を編集した『手に魂を込め、歩いてみれば』は、こうした作品群とは一見対極的な方向性をもつ。瓦礫の町で生き場をなくしながらも、諦めと無力感を乗り越えたファトマの笑顔はとびきりに明るい。しかし本作のカンヌ上映が決定した翌日、彼女はイスラエル軍のピンポイント爆撃を受け死亡した。ファトマは自身のSNS更新も注目されてはいたが、この映画撮影がなければ彼女はこの日に死んではいなかったのではないか。仮にそうだとして、映画が彼女を殺したのか。安易な評価を斥け、真に多くを考えさせるとも言える本作もまたこの意味で、眼前する現実を問いへと対象化し突きつける。答えはむろん、観客自身に問われている。
(ライター 藤本徹)
『手に魂を込め、歩いてみれば』Put Your Soul on Your Hand and Walk
公式サイト:https://unitedpeople.jp/put/
2025年12月5日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷ほか 全国順次ロードショー。
【関連過去記事】
【映画評】 ヴェンダースの冒険 『PERFECT DAYS』『アンゼルム』 第36回東京国際映画祭 2023年12月22日
【本稿筆者による言及作品別ツイート】
『パレスチナ36』فلسطين ٣٦🇵🇸2025
1936年のパレスチナでユダヤ人の大量入植を受け、互いに宥和的であった人々の心情から民族的アイデンティティが芽生え始める。
TIFFグランプリも納得の、緻密にして明解な秀逸構成。秀作『No Other Land』↓への、ナクバを超え現代史全体へ射程を拡げた応答作とも。 https://t.co/ENurfUr5mk pic.twitter.com/jvaeTTJO9P
— pherim|土岐小映⚓️ (@pherim) November 19, 2025
『トンネル:暗闇の中の太陽』🇻🇳
ベトナム戦争下クチのトンネル戦闘を描く大傑作。
虫との共生、そこにある物で闘うゲリラ戦術、全長250kmの重層構造、ベトコン内部の権力勾配など描写の解像度が逐一極上。
さらにブイ・タック・チュエン監督の妖気放つ性愛演出がビタ嵌る、TIFF2025極私ベスト。(続 https://t.co/2fI4wBQhoM pic.twitter.com/cvaHTeOn0V
— pherim|土岐小映⚓️ (@pherim) November 4, 2025
『愛殺』レストア版🔪1981
男女4人の描く心の波紋が、太平洋を超え錯綜する。
すっごい変、な譚家明監督作。王家衛映画の美術/張叔平デビュー作で、物語も演者も殺戮までもが画作りへ奉仕するこの美学、香港M+がrestored企画の端緒としたのも納得の、香港新浪潮一方の極。
そして林青霞の女神度MAX。 https://t.co/eSQvQvImCO pic.twitter.com/G4eJ0tCJtZ— pherim|土岐小映⚓️ (@pherim) November 15, 2025
https://twitter.com/pherim/status/1990660160470343877
『ラッキー・ルー』幸福之路🇺🇸🇨🇦Lucky Lu
NYで配達員の父さん頑張る。🚲
華僑移民の過酷なリアルを活写するロイド・リー・チョイ監督作。
張震/チャン・チェンが、自転車を泥棒され自転車泥棒へ成り行く顛末など展開の既視感を苦渋顔で突き抜ける。娘の無邪気さが切ない。https://t.co/thF4el5Qgg pic.twitter.com/ngzYvpgzef
— pherim|土岐小映⚓️ (@pherim) November 29, 2025
『手に魂を込め、歩いてみれば』🇵🇸🇮🇷
紛争下ガザに暮らす24歳女性ファトマとのビデオ通話。
その明るさに、しなやかさに惹き込まれる。本作カンヌ上映決定の翌日、彼女は爆撃を受け死亡した。安易な評価を斥け、本当に多くを考えさせる。
諦めと無力感を乗り越えたファトマの笑顔が深く刻まれる。 https://t.co/9muDZXoY2m pic.twitter.com/Djp9TD93zE
— pherim|土岐小映⚓️ (@pherim) December 3, 2025
©2025 TIFF