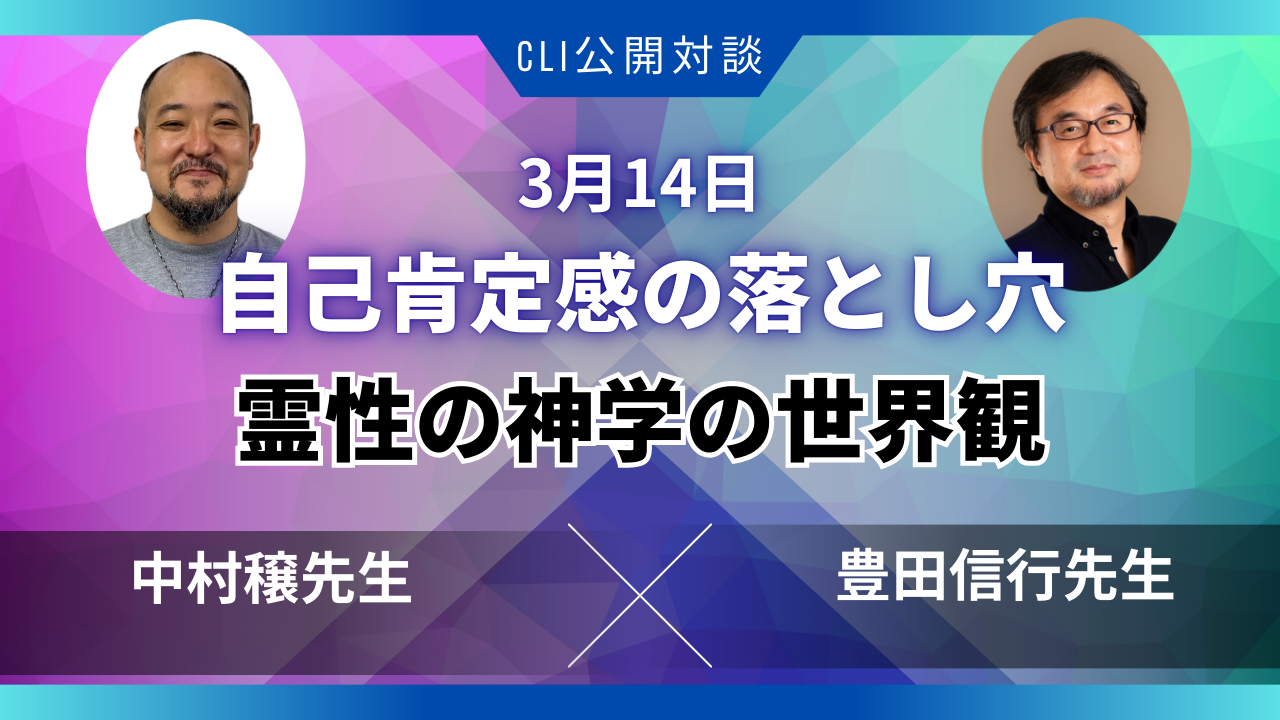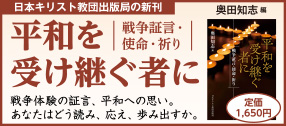【映画評】 躍動するマザー・テレサ 『マザー』 2026年1月3日

マザー・テレサの立志篇、とでも言うべき若き姿を描いた傑作映画『マザー』(Mother)が母国北マケドニアで制作され、昨秋の東京国際映画祭にてアジアで初上映された。本作は1948年、スコピエで生まれた修道女で当時38歳のアグネサ・ゴンジャ・ボヤジが、インド・コルカタで自ら立ち上げた修道会〝神の愛の宣教者会〟の教皇庁認可を受け、のちマザー・テレサとして世に知られることになる一連の活動を軌道に乗せるまでの葛藤と超克の歩みを描く。
信仰への懐疑や、シスターの妊娠と中絶をめぐる呻吟など、シリアスなテーマが扱われながらも小気味良いテンポで展開する物語は、実際にマザーが設立したコルカタの諸施設でのロケハンも含んで見どころが多く、一切の中だるみなしに進行する。
今ではよく知られた白と青のサリー修道服が誕生する瞬間も感動的に描かれ、主演ノオミ・ラパスの指先まで張り詰めた仕草や、信仰と懐疑と狂気の縁でギリギリ己を保つ表情に戦慄さえ覚える本作を撮ったのは、1975年生まれのテオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督だ。

©Ivan Blazhev
スコピエのマザー・テレサ生誕地から、わずか1kmほどの近所で生まれ育ったという同監督へ話を聞いた。
――本編の物語は、1948年のわずか7日間に集約され、1日を1章として進行します。マザー・テレサが全く無名のこの時期をなぜ選び、どうしてこのような構成をとったのかお聞かせください。
おっしゃる通り、当時の彼女は、のちに聖人となることなど誰ひとり想像もしない無名の存在でした。ひとりの名もなきシスターが自ら修道会を立ち上げることで、何を為そうとしていたのか、その動機は何だったか。どんな人物で、どのような迷いや困難を抱いていたのか、それらを象徴的に表すため、物語を1週間へ凝縮させることにしました。もちろんこのアイデアは聖書における創造の7日間を着想源としていますし、フランス映画『八日目』(1996)からの影響もあります。
すこし想像してみてください。38歳の女性がすべてを捨て一事へ打ち込むという選択は、女性の社会進出が相対的には進んだ21世紀の今日でさえ、決して生易しいものではないでしょう。地位と名声を得てからのマザー・テレサのことは、すでにいくらでも本や映画になっています。Wikipediaを調べればわかることを描いても仕方ないですよね。そして大英帝国からの独立を勝ち得たばかりの、飢饉など危機の時代でもあったインド・コルカタでの7日間に絞り、エネルギーを凝縮させることで、いずれは「マザー・テレサ」になる若いパワフルな女性をより鮮やかに描きだせると考えました。
――実は10代の頃に、当時まだ存命だったマザー・テレサのもとでボランティアをしていたことがあります。世界中から集まったボランティアたちは、夜明けのミサをマザーと共にしたあと各施設へ移動するため、彼女と直に触れる機会は日常的にありました。そしてすでに多く存在するマザー・テレサのドラマや劇映画化作よりも、本作でパンクロックをBGMに躍動するナオミ・ラパスの演じるマザー・テレサが、現に私が接した本人に最も近いと感じました。主人公をめぐる演出やナオミ・ラパスの役作りについて、経緯と監督の関わりかたをお聞かせください。
本当に嬉しいご指摘です、深く感動しました。ありがとうございます。私は彼女に直接会う機会を持てませんでした、とても幸運な経験をされたのですね。この作品には構想から17年もの歳月を経ており、集めた関連の資料や情報で必要なものはナオミとすべて共有してきました。彼女は役作りに1年半を充て継続的に話し合いもしてきましたが、それでもコルカタ入りした撮影直前の朝5時に「不安だ」と電話をかけてきたりした。ただ強い女性を描くだけでは興味をもつひとは限られます。マザーテレサの抱えた弱さ、誰しもそうであるような脆さをどうすれば表現できるのか。そのことをナオミもよく理解し、ずっと考え続けていたのだと思います。
パンクロックをメインのBGMとしているのは、マザー本人がパンクそのものだったからです。権威には反抗的で何に対しても意欲的、鮮烈な生き様です。彼女が自ら選んだ道を行ったこと、その自由さと覚悟の深さにパンク性を看取しました。ひとは今日、男性主人公の物語をたくさん読み聞かされ、たくさん観て育ちますよね。過去にあれだけ複雑で困難なことを成し遂げた女性がいたのだ、自信をもって自分のやりたいことをやりましょうという物語を盛り立てるのに、パンクロックはごく自然にふさわしいものと感じられました。そしてそんなマザーを演じる誰がふさわしいか、内心にそういうものを持っている役者として、ナオミはぴったりでした。またもっと素朴に、莫大なエネルギーを内に秘めた小柄な体のサイズがマザー役にぴったりだったというのもありますね。
――映画の中盤で、中絶をめぐりマザー・テレサは苦悩します。彼女の片腕であり後継者候補であったアグニシュカというシスターが不意の妊娠をしてしまい、マザーにだけ打ち明けて始まるシークエンスです。マザーは激怒し、絶望し、神父へ縋るなどして懊悩する。こうした出来事は実際に起こり、マザーを悩ませたのでしょうか。そうでないとすれば、この場面にはどのような意図があったのでしょうか。
アグニシュカという人物は架空のキャラクターです。マザーの手記など各種のリサーチや、マザーをよく知るシスターたちへの取材から読み取れる彼女の迷いや葛藤を鑑み、のちの「マザー・テレサ」のような聖人になりたい彼女、他のいろんなことをしてみたい一人の女としてのマザーを象徴的に表現するために着想しました。ですからアグニシュカというキャラクターには、ありえた「子どもを生みたかったマザー・テレサ」が象徴されると同時に、21世紀今日の女性が抱える問題も映画の中で扱いたいという想いが込められています。
ただ、中絶に対する実際のマザー・テレサの考え方は保守的なものでした。彼女はまず命を大切にしていました。時代状況が異なるなかでマザーの育んだ価値観にはもちろんリスペクトを抱きますが、その感情の部分では今の私と相容れないものがあるのも事実です。社会的に中絶を許すか許さないかという政治イシューをめぐっては、現代の欧州においてもなお緊張下にあるといえるなかで、この映画を土台に議論の場をつくっていければという動機づけもアグニシュカという人物造形には働いています。
――妊娠出産に限らず女性性は、信仰と並んで監督過去作でも中心的なテーマをつねに占めていますね。本作の「マザー」という呼称にはダブルミーニングの面もある。映画製作や監督自身にとって女性であること、母であることはどのような意味をもち影響を与えているとお考えでしょうか。
女性が誇りをもって生きること、この映画業界において女性であることは今なお容易でなく、昔はさらに難しいことでした。18歳の青年がごく普通に抱く自信を、50歳にしてようやく私は身につけられたように思います。いま私は実の息子にとっての母親であるように、スタッフやキャストにとっての母親でもあろうと心がけています。Mother is Love, まとめて言えば、愛を生きるということに尽きますね。
――信仰についてはいかがでしょうか。十字架が、世界観や画面構築のうえで重要な役割を果たしてきたことも、監督の作品履歴において顕著な特徴となっていますね。
私自身は、過去作『ペトルーニャに祝福を』でも描いたようなマケドニア正教の家庭に育っています。以前バチカンで取材した際、カトリックの総本山サン・ピエトロ寺院の上席神父と、とても良い議論を交わせたことがありました。刺激的で充実した時間を過ごし、知的に興奮もした。しかし「15年後には女性教皇、ポープではなくポーパが生まれるんじゃないですか」と私が言った途端、彼の態度は豹変し、それまでの議論がすべて消え去ったように親密な空気はシャットダウンされ、ステレオタイプで拒絶的な言明が始まって驚きました。バチカンだからこそ、女性の権利をめぐっては真摯な議論が交わせるようになることを望んでいます。
――女性でありクリスチャンであることの他に、監督とマザー・テレサの共通点としてはマケドニア出身であることが挙げられますね。現在は北マケドニアと呼ばれるこの地域の映画は日本でも近年上映機会が増えており、そこには何か通底する質があるようにも感じます。監督からご覧になって、マケドニア映画の特徴はどのようなものでしょうか。また、マザー・テレサはスコピエ出身でアルバニア系であることが知られていますが、どのあたりに同郷性をお感じになりますか。
例えば隣国セルビアの映画は、概してマッチョといえるかもしれません。クストリッツァに代表されるマチズモを私は問題に感じることが多く、マケドニア映画は相対的にソフトな印象があります。それは200万人という小国規模や、環境条件への適応性が影響してそうです。女性監督の表現性の点でも、クロアチアやスロベニアなどと並び、顕著に目立つと言えますね。ちなみに私の母はモンテネグロ人、父はマケドニア人です。マケドニアの民族構成は極めて多様なのです。
マザーの没したあとBBCがとてもネガティヴなドキュメンタリーを作って以降、マザーハウス(マザー・テレサが設立した施設群の本部)は長らくメディアに対しかなり閉鎖的に振る舞っていたのですね。しかしスコピエから来たということで、我々の撮影班はとても歓迎されオープンに迎えられました。そしてシスターらとの交流を通じて、我々とマザーが同じ大地で生まれたんだなと感じられることはよくありました。やはりインドとはさまざまな面で異なりますからね。
――本作では、コルカタ市街に点在する「死を待つ人の家」や孤児院、ハンセン病療養所などさまざまな施設が劇中に登場し、個人的にとても懐かしくも感じました。コルカタでの撮影で、特に困難に感じたエピソードが何かありましたらお聞かせください。
時間感覚の違いでは貴重な経験をしました。例えば「今」という概念。スタッフに「今やって」と言っても「今やります」と言うだけで動かない。そしてここに覗く溝には、植民地主義由来の無自覚な押し付けさえ機能しているのだと気づくようになりました。というのも自分たちの「今」が正しいんだという奢りが、なぜすぐに動かないのかという他者への苛立ちを生むことに気づかされたのです。その後インドやベンガルの歴史的変遷やインド式の「今」のプロセスを理解してくると、「今」のすり合わせの過程はとても豊かさに充ものとなりました。それから、末端のスタッフとして働いてくれたコルカタの映画学校生がとても優秀だったことは付け加えておきたいです。
――マザーが経理など数字の正確性にこだわるシーンや、男性神父との議論場面からは、実際のマザー・テレサがくぐり抜けた格闘と、現実的に採られた解決方法が反映されているようにみえました。脚本執筆や演出にあたって実像との兼ね合いや工夫のうえで何か留意したことはありましたか。
マザー・テレサ本人の日記をできるだけ反映したかったというのはありますね。彼女は個人的な野心や信仰への懐疑に煩悶し、つねに本当はどうすべきかを考えつづけていました。神への問いかけを読んでいると、いずれ聖人になるんだと計画していたのでは、とさえ思えてきます。さまざまな困難を描くひとつの題材として、アグネシュカというキャラクターもつくりました。厳しい時代を乗り越えていくために、時間への対処や、現実的な解決法の数々も自ら案出した。
観客のかたに単純ではない、マザーが選び取ったとても複雑な判断を共有し、映画という川の流れを泳いでいくことができるような展開となるよう心がけました。
――ありがとうございました。
(ライター 藤本徹)
『マザー』“Mother”2025
第38回東京国際映画祭2025年10月27日~11月5日上映(国内一般上映未定)
*注:語としての「マケドニア」「北マケドニア」について
テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ監督はインタビュー中、「北マケドニア」という表現を一度も使用しなかった。周知のように近年、ユーゴ紛争以降マケドニアと名乗ってきた国はギリシャ政府による経済封鎖を伴う要求もあり「北マケドニア」へと正式に改称した。しかし現下の政治状況がどうあれ、自認アイデンティティを指す語を変えない自由は誰しも有するため、本稿では他メディア記事でみられるような「北マケドニア」への表記変更は行わなかった。
**本稿は、来日中のミテフスカ監督に対し2025年11月1日に日比谷で行われた本紙単独インタビューを軸として、同日に催された一般向け本作上映後Q&Aおよび複数メディアによる合同取材での応答内容も一部取り入れ執筆した。
【関連過去記事】
【本稿筆者による関連作品別ポスト】
https://twitter.com/pherim/status/1983723289584549928
『ペトルーニャに祝福を』
北マケドニア映画。32歳独身の主人公女性は、母に促され就職面接へ向かうもセクハラに遭い、帰途遭遇した女人禁制の伝統儀式へ闖入する。
”神は在る、彼女の名はペトルーニャ”が原題直訳。十字架のゆくえを軸に、バルカン正教文化における性差別模様を炙りだす構成の鮮烈。 pic.twitter.com/tBFwbQddcI
— 土岐小映⚓️ρꛅᘿ𖦪ﺃ ʍ (@pherim) May 22, 2021
『何も知らない夜』🇮🇳A Night of Knowing Nothing
学生運動に揺れる映画大学で学ぶ女性が、恋人へ綴った想い。
叶わない恋、消えないカースト差別、表現の不自由、台頭するヒンドゥー至上主義とモディ政権。
パヤル・カパーリヤーの醸す詩性にシリアモナムールも想起され。 https://t.co/G5bVGeMWkE pic.twitter.com/8COJAQv88r
— 土岐小映⚓️ρꛅᘿ𖦪ﺃ ʍ (@pherim) August 7, 2025
『タゴール・ソングス』
極私的に大好きだけれど偉大すぎる存在だった詩聖タゴールを、ダッカ市中の若者がラップへとり込む自然さにときめく。ベンガルは詩の大地と直感した学生時の放浪体験を素敵にアップデートしてくれた。タゴールの足跡を追い、コルカタの溌剌女子大生が日本へ旅する展開胸熱。 pic.twitter.com/AQmI0ZMxNT— 土岐小映⚓️ρꛅᘿ𖦪ﺃ ʍ (@pherim) April 7, 2020
『ハニーランド 永遠の谷』
北マケドニアの渓谷で全盲の老母と暮らす、欧州最後の自然養蜂家ハティツェ。母娘の日々を脅かすトルコ移民一家の到来が象徴する消費文明の騒擾に差し向けられた、深く澄明な彼女の眼差し。その佇まいが放つ強靭な古代性、刻々と損なわれゆく世界の音なき叫びに震撼する。 pic.twitter.com/B730M33InZ
— 土岐小映⚓️ρꛅᘿ𖦪ﺃ ʍ (@pherim) June 26, 2020
『柳』“Willow” 🇲🇰2019
北マケドニア映画。不妊に苦しむ3人の女の物語。
『ビフォア・ザ・レイン』のマンチェフスキー監督作。中世から現代まで、物言わず彼女ら人間模様を見つめつづける一本の柳の樹を通し、現代都市のただなかに呪術的世界観を湧き起こさせる。時隔てる3話構成に『灼熱』を想起。 https://t.co/gakgTvh3r8 pic.twitter.com/Olc4T4O4qT
— 土岐小映⚓️ρꛅᘿ𖦪ﺃ ʍ (@pherim) March 13, 2022
『ハリーマの道』Halimin put🇧🇦2012
なんだこれ、って脚本の巧緻にたまげる。
ボスニア寒村で暮らすムスリム女性が、紛争時セルビア軍に連行された夫と息子を捜す中で、錯綜した過去が呼び起こされる。
一辺倒な登場人物は皆無で、各演者の風格と変化に富む田園景も見処。https://t.co/svaxQJL97Z pic.twitter.com/OE1AA6Y5aJ
— 土岐小映⚓️ρꛅᘿ𖦪ﺃ ʍ (@pherim) April 15, 2025
©Entre Chien et Loup, Sisters and Brother Mitevski