あたらしい性教育のはなし 聖カピタニオ女子高校/国際基督教大学 2008年3月22日
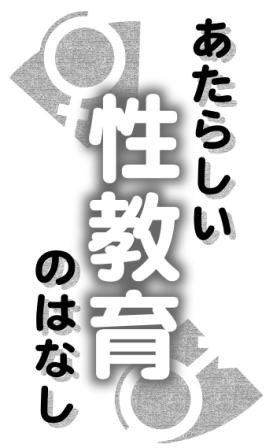
性教育の必要が叫ばれて久しい。日本では1972年、財団法人日本性教育協会が文部省(当時)の正式な認可を受けて発足、89年の指導要領改訂では小学校にも性教育が導入された。しかし、多様化・個人主義化のあおりも受け、性に関するモラルは崩壊の一途をたどり、性体験の低年齢化傾向は留まるところを知らない。そればかりか、教職者によるセクハラや不倫までが世間を騒がせる。それは、倫理的基盤を持っているはずのキリスト教学校においても決して例外ではない。神の愛を語り、隣人愛を説くキリスト教こそが、真の意味で「性教育」を成し得るのではないか。この難題に正面から挑む、数少ない学校の取り組みを取材した。
大窪順子さん(聖カピタニオ女子高校教諭)

■多角的な視点・多様な手法
愛知県瀬戸市の聖カピタニオ女子高校(ギュンタ・ケルクマン校長)で行われてきた性教育には、20年以上の歴史がある。1982年、学習指導要領の改定に際し「女性学」が新設され、99年には、文部科学省による総合学習の導入にあわせて教科名を「ウマニタス(ラテン語)」に改称。カトリック学校として「人間の尊厳」を大前提に、週1時間の授業で、マナー、性教育、社会問題などの内容を系統立てて学ぶ。中でも性教育の授業では、月経、妊娠の仕組み、性感染症、男子の「性」、男女交際についてなど、かなり具体的な内容にも踏み込んでいる。
実際に授業をするのは担当教諭2人だが、養護教諭、家庭科、社会科、国語科の教諭らがスタッフとして加わり、さまざまな角度から内容を吟味、検討しながら授業を展開する。内容によっては、他の教科と連動して授業をすることも。また、婦人科の医師を招いた講演会も行っている。
授業方法は講義形式だけにならないよう、グループによる話し合い、調べ学習、ディベートなど、工夫をこらす。ある授業では、生徒自身が役割を演じる「ロール・プレイ」を取り入れ、「結婚における男女の人間関係」や「10代の妊娠」など、実際に起こり得る場面を想定し、身をもって考えさせる。自分が生まれた時のことを親にインタビューする宿題などは、親子で話し合うきっかけにもなっているという。
■生徒たちが危ない
現在3年生の授業を担当するのは、社会化教諭の免許を持つシスターの大窪順子さん。「宗教は神と自分との関係を考える。ウマニタスで考えるのは、人と人との関係です。自分が尊い存在であるなら、相手も尊い。その尊い相手といかに付き合っていくかを考えるのが最大の目的です」
大窪さんが担当してきたのは、主に女性史。「からゆきさん」や従軍慰安婦などの歴史をはじめ、明治から昭和にかけて活躍した女性たち、日本国憲法の「男女平等」条項を起草したベアテ・シロタ・ゴードンなどの人物に焦点を当て、時代背景をおさえながら、女性の置かれてきた境遇を事実として教える。教科書に取り上げられることの少ない女性たちの存在を知り、彼女らの生き方を学ぶというのがねらいだ。
また、社会に巣立つ前の学年ということもあり、出会い系サイト、デートDV、同性愛など、今日的な課題にも力を入れる。その根底には、生徒たちを取り巻く現状への危機感と、「幸せになってもらいたい」という教師としての願いがある。
「女性は、歴史的に見ても性の奴隷になりやすい。結局、最後に責任を取るのは女性です。生徒達にはしっかりした『自己決定』の力を持ち、本当の愛とは何かを分かってほしい。やはり女性が賢くならなければ」と大窪さん。
特に高校に入学したばかりの1年生を担当する小平木ノ実さん(宗教科教諭)には、その思いが強い。小中学校での話を聞くと、ほとんどが共学校出身者だが、しっかり性教育を受けたという生徒は40人中1人か2人。とりわけ「月経指導だけ女子にして、男子は別メニュー」というケースが圧倒的に多い。
■「性=生」教育
では、生徒の反応は――。小平さんによると、やはり授業を始めた4月当初は「自分の体のことさえ知りたくないのに、なぜ男の子の体のことまで」という抵抗もあるという。しかし、3年間かけて学ぶ中で、生徒たちの姿勢は大きく変わる。
この3月に卒業する3年生の感想にも、数多くの確かな手ごたえが見てとれる。「正直初めのうちは『超めんどくさい、嫌だなぁ』と好きになれなかった……今までは気づけなかった本当の自分の気持ちを冷静に見つめ直し、『人間』についても考え方、見方がだんだん変わってきて、様々な角度から見て深く考えることが増えました」「いろんな問題の起こっているこの世界で自分は何をすればいいのか、どういう生き方が正しいのか、たくさん学んで悩んだ」「もしウマニタスがなかったら、今の自分には会えてなかった……この3年間をふり返ったら、知識が増え、少し自分が好きになることができました」……。
「女性学」の開講当初からスタッフとして関わってきた養護教諭の宮本信代さんは、むしろ自分自身の成長にもつながったとふり返る。「『今の自分をありのまま受けとめて』『一人ひとりが大事』というメッセージを送りたいと思ってきましたが、生徒から教わることの方が多いような気がします」
大窪さんは、「性教育は、『生き方教育』です」ときっぱり。生徒と共に悩みながら授業を作り上げ、実践と研究を積み重ねてきた教師の実感だ。
■本音で語る「性」
生徒たちが置かれている現状を考え、妊娠や中絶の問題も避けられない大事な事柄として模索しながら取り組み、命について考えている。
大窪さんがもう一つ気をつけているのは、ややもすると「男性が悪い」「男性が怖い」という結論になってしまうこと。命を生み出す女性だけでなく、男性にとっても、自分の性とどう向き合っていくかは大きな課題である。中絶がどんな手術かを知らずに、簡単に「堕ろせ」という男の子や、「やめてやめても好きのうち」などという誤った情報を真に受ける男の子を見るにつけ、「同じ授業を受けさせたい」との思いも募る。
修道服を着たシスターが、包み隠さず、本音で訴えかける姿は印象的だ。「ダメなものはダメ」――。飾らない気さくな雰囲気が、生徒たちを惹きつけるのかもしれない。恋愛相談を持ちかけられることも少なくない。卒業生の中には、「時々シスターの顔が浮かぶ」と話す子もいるという。
「自分の〝女性性〟と生涯向き合い続けるシスターだからこそやるべき」と語る大窪さんだが、「わたしも初めは抵抗がありました」と照れ笑い。「自分の人間性が試されるときでもあり、辛い思いをする年もある」。それでも、「『性』はわたしたちを豊かな人生に導くキーワード」とのメッセージを送り続けている。
町田健一さん(国際基督教大学教授)

■脱「避妊教育」「脅し教育」
国際基督教大学で町田健一さん(教養学部教授)が担当する「教職原論:中等教育研究入門」は、中学・高校の教師を目指す学生向けに開講されている年間18時間の授業。そのうち、最後の5時間分を性教育に費やす。そこには、キリスト教主義大学における教員養成課程でこそ、「より良い性」のための正しい知識を学ぶ機会が必要との思いが込められている。
授業は、教師になった時のためでもあり、学生自身のためでもある。その内容は、「教師として性教育を扱う際の留意点」から、「性に対する考え方の歴史的変遷」「性教育をめぐる主張の相違点」「男女の欲求の違い」に至るまで多岐に渡る。性教育というと避妊や中絶の問題と考えがちだが――。「避妊法は完全でないとか、エイズや性感染症が怖いというのは一つの警告になるが、もっと大事に扱うべき根本的問題がある」というのが町田さんのスタンス。
「付き合うなら肉体関係を持つのは仕方がない」「一生で1人だけなんて考えられない」「事前に練習しておかなければ……」など、学生たちの認識には毎年愕然とする。「今日、恋愛が非常に薄っぺらなものになっています。お付き合いをしても別れる率が高く、期間も短い。その中で、多くの若者が性体験をしている。大人も、なぜダメなのか、説明できるものを持っていない」
そうした現状をふまえ町田さんは、「まず小学校から、しっかり『恋愛論』を教えるべき」と強調する。「好き」という感情だけでなく、理性で相手を思うこと、「人を愛する」とはどういうことかというアプローチ。まさに、「恋愛論」で始めて「人生論」の中で語る性教育だ。
学生によるディスカッションも行うが、「町田の主張」と題する講義の時間では、マスコミの情報や「周りがやっているから」という「仲間道徳」にも真っ向から対峙してみせる。理論武装と同時に、「より良い」モデルを提示することも必要だという。「特に高校から大学1年までの最も危険な時期に、どう価値観形成をするか、周りに対してどう自分を主張できるようになるかが課題」
■10年遅れのアメリカ追随
教育改革では、およそ10年遅れでアメリカの動きを追うことが多い日本。性教育も同様で、日本性教育協会の見解をはじめ、日本の性教育は、アメリカの非営利団体SIECUS(Sexuality Information and Education Council of the United States)による「包括的性教育」を参考にしてきた。それは、「セックスは愛し合っている者たちにとっての自然な関係・権利、たとえ10代でも」とうたい、性の生理的な仕組みと共に避妊の知識と技術を教えながら、他方、若者の「自己決定権」を尊重し、「納得していれば」と「責任ある選択」を促す。
しかし、「性の自由化」が進行した1970年代以来、アメリカがたどったのは、10代の妊娠、中絶の増加、家庭崩壊、性感染症の蔓延など、悲惨な末路。そうした反省に立ち、90年以降は、国をあげて「自己抑制の性教育」への転換がなされ始めている。
もともと欧米のキリスト教社会には、あらゆる「不品行」を戒める聖書の教えに基づき、体と心の純潔性を説く伝統があった。そうした基盤のない日本が、同じ過ちを犯そうとしていることに大きな危惧を抱いている。「土台となる価値観がなければ、『自己決定』などできない」
■バルトの結婚観
授業では、キリスト教の倫理観として、カール・バルトの主張も対比的に取り上げている。バルトによれば、結婚とは「主に従う全人的決断において一つになった男女の関係」であり、「性的関係は、結婚による夫婦の永続的・排他的関係、魂と体の全的な関係の中においてなされるべきである」とされている。
しかし、カトリックのように、具体的問題まで規定したカテキズムを持たないプロテスタント教会では、教派によって教理的な縛りが異なり、多様な捉え方がされてきた。今日では、離婚も婚外の性交渉も許容する「ラディカルな」牧師も少なくない。聖書の原則と現実とは分けて教えているという学校もある。「『神に対する誠実さ』とか、『導かれた2人』という側面がもっとアピールされていい。キリスト教学校は、自信を持って自身の原則を高く掲げるべき」と町田さん。
このような内容は、むしろ信徒でない学生には新鮮に聞こえているようだ。「わたしはクリスチャンでないが、バルトのいうように神を中心に据えた2人は本当に幸せだろうと思った」という感想もある。他方、信徒の家庭で育ったという学生からはこんな声も。「罪悪感を感じながら何度か(体を)許してきた。この授業でこれからは改めることを決心した。同じような問題で苦しむ生徒に活かしたい」
■成果と課題
講義を続けて16年。授業を終える度に、「やってよかった」との思いを強くしている。これまで、かなりの割合で受講した学生の中に態度変容、行動変容が起こってきた。「自分の生きる姿勢を問いただされた」「ノートを見せながら2人でこれからのことを話し合った」「自責の念にかられ、検査を受け、自分の過去を恋人に話し、謝った」「もう少し早くこの授業を受けていれば、あの嫌な体験はしなくてすんでいたのにと悔しい」などなど。自分の過去をふり返り、講義を聞きながら涙する学生もいる。
いま直面している最大の課題は、現役の教師自身が受けてきた性教育と、育った社会環境の壁だという。20~40代の教師は、婚前交渉が当たり前になってきた時代の影響を多大に受けている。教師向けに行った講演での反応は、性教育を扱うことへの恥ずかしさに加え、自分の過去の体験から「生徒に教える資格はない」というものまでさまざま。倫理的問題を含む価値観の指導に困難を覚えるという学校教育の風潮もある。
現在、東京神学大学でも同様の講義を担当する町田さんは、キリスト教学校の教員研修、教員養成において、『性教育のあり方』を議論することの必要性を訴えている。「科学的に正しい知識を避けずにいかにきちんと伝え、……断罪するのでなく、また世の中的な価値観に譲歩するのでもなく、どのように美しい『性』を理解し、体験させられるか」「キリスト教主義学校こそが語るべき、そしてキリスト教主義学校だけしか語れない性教育がある」
















