文学作品を通して見える宗教性 島薗進氏が上智人間学会で基調講演 2016年10月1日
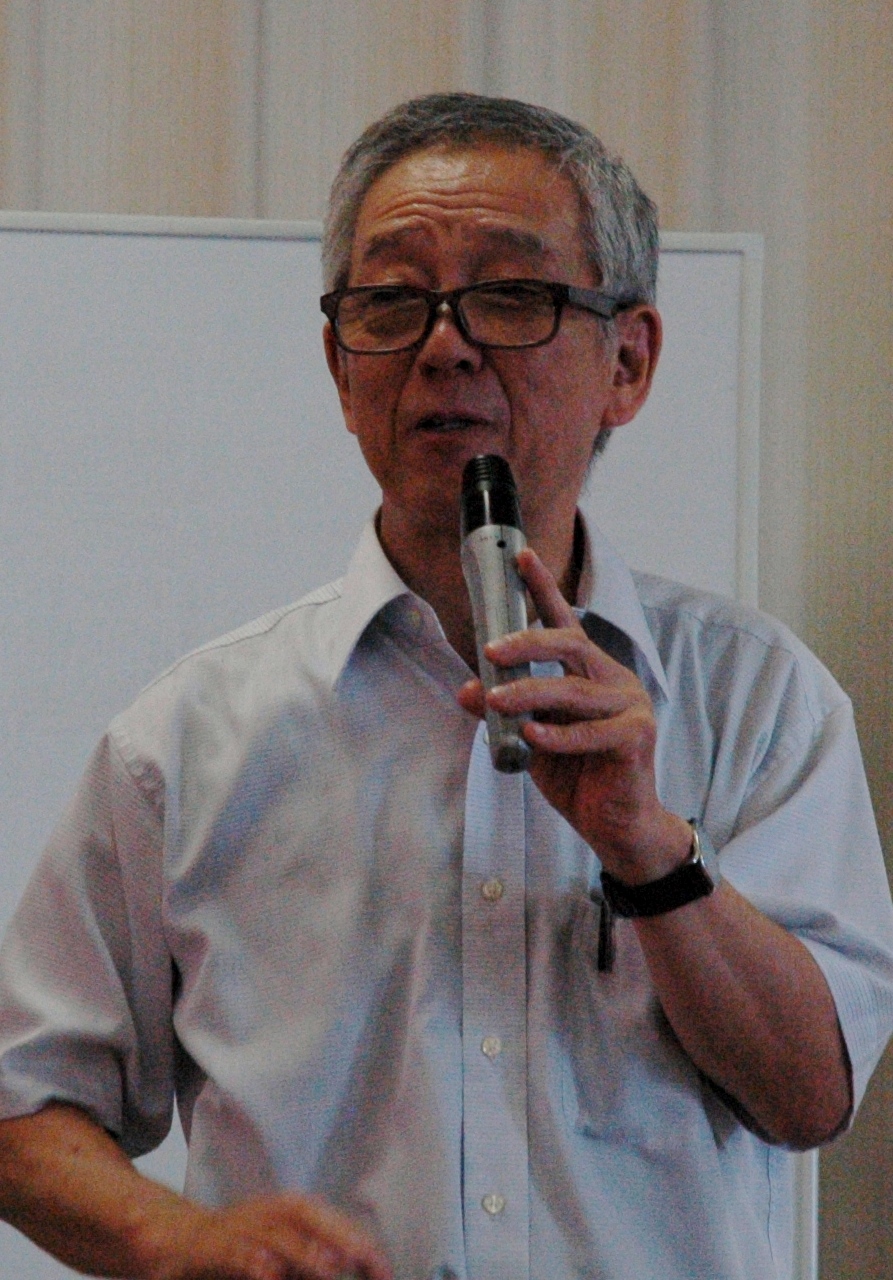
「人間学とキリスト教」をテーマに上智人間学会(瀬本正之会長)の第44回学術大会が9月9~10日、上智大学(東京都千代田区)で開催された。初日の島薗進氏(宗教学者、同大学グリーフケア研究所所長=写真)による基調講演は一般にも公開され、会員を含む約50人が参加した。
「宗教と文学――近代人の自己理解とキリスト教」と題して講演した島薗氏。これまで宗教学、死生学の研究に取り組んできたが、「物語」を通して宗教心、スピリチュアリティ、死生観を考えるようになったという。近著『宗教を物語でほどく――アンデルセンから遠藤周作へ』(NHK出版新書)と、2012年刊行の『日本人の死生観を読む――明治武士道から「おくりびと」へ』(朝日選書)に基づき、「文学作品を通して見える宗教性」を考察した。
まず、アンデルセンの『人魚姫』を取り上げ、キリスト教の教義そのものではないが、「キリスト教が伝えてきた『目に見えない尊い何か』を伝える物語」であることに注目した。
次に内村鑑三に言及。『基督信徒のなぐさめ』と『後世への最大遺物』は文学作品的な性格があると述べ、前者は「近代日本のグリーフワークの本と言ってもよいかもしれない」と指摘。グリーフワークとは、大事な対象を喪失した悲しみを償うことで、新しいものに心が向けられるようになるプロセス。同書は、「どうすれば救われるか」ではなく、「どうしてこのような悲しみ、苦しみの中に自分はいるのか」という言葉が優勢な文献だと述べ、現代的であり、グリーフケアに通じると指摘した。
さらに、志賀直哉が死に向き合うことを通してアイデンティティを獲得していったことを、『城の崎にて』から解説。同書に「悟りの境地」が書かれているとし、これによって志賀は小説家としての表現の基盤を得ることができ、人間としての自信も得ていったのだと説明した。
これら三つの例は、それぞれに宗教性をはらんだ文学作品であり、市民それぞれが死に向き合う時の参考になると主張。「近代人の自己理解にとって、宗教と文学を隣り合わせに考えることが大きな力となる」と語った。
















