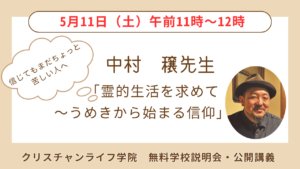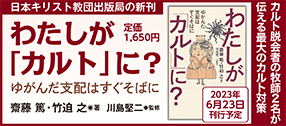【書評】 『神の三位一体が人権を生んだ 現代思想としての古代・中世哲学』 八木雄二
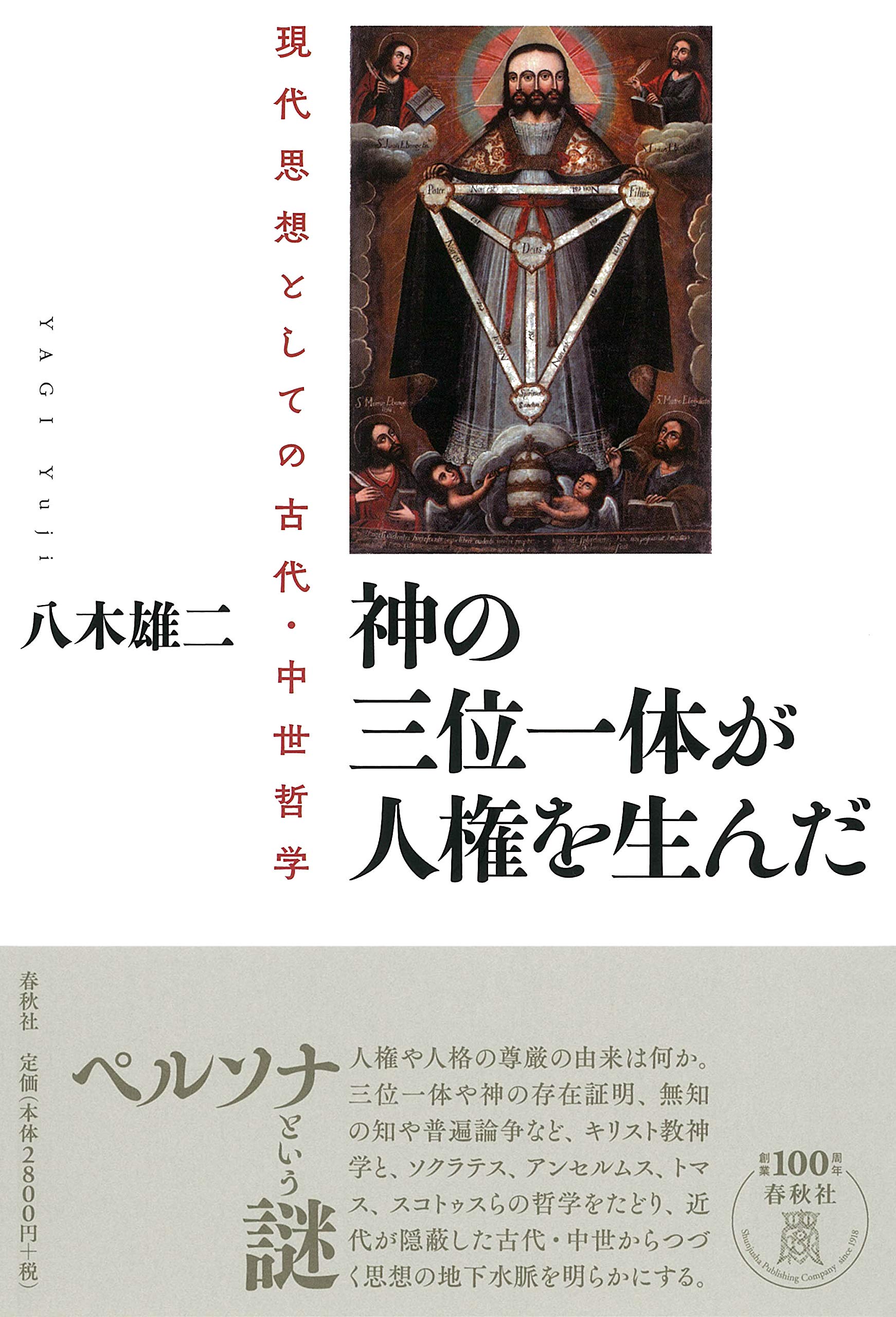
神学書として面白い。ドゥンス・スコトゥスによる三位一体論やアンセルムスからトマス・アクィナスそしてドンス・スコトゥスに至る神の存在証明の変化の流れを学ぶことができる。三位一体論は究極的には神の領域、人間が知り得ぬ奥義ではある。しかし、父と子と聖霊とが区別されるペルソナ(パーソン)であるが、神であることにおいて一つであるということは、太郎や次郎や花子がそれぞれ同一化されないパーソンでありながらも同じ人間であるということと、ある意味において比較可能である。著者はまずそこから個別の人間における、今日「人権」と呼ばれるもののルーツを語り始める。
著者の語りはやがてソクラテスへと収斂してゆく。それも、我々がよく知っているプラトンを経由しない「ソクラテス自身」へと著者は肉薄しようとする。著者によれば、ソクラテスが無知の知を語るとき、プラトンが「無知を恥じて、そこから探求が始まる」と理解したのは誤りであったとする。知らないことを知らないと認めることは、哲学的思惟において恥でも何でもないはずで、恥を原動力に知的探求を始めるのはおかしいからである。著者はクセノポンが伝えるソクラテス像などを手掛かりに、無知の知は「知らないことを知らないと思う」という素直な、アンセルムスが正直(せいちょく)とした態度であったとみる。
知らないことを知らないと認め、そこに踏みとどまることは、世の情報に煽動され生きづらくなり、生きる意味を見失う現代に対する知恵である。それを三位一体論から論じ始めるところが、本書のユニークさである。
【本体2,800円+税】
【春秋社】978-4393322314