【書評】 『キリシタン歴史探求の現在と未来』 川村信三 編 キリスト教史学会 監修
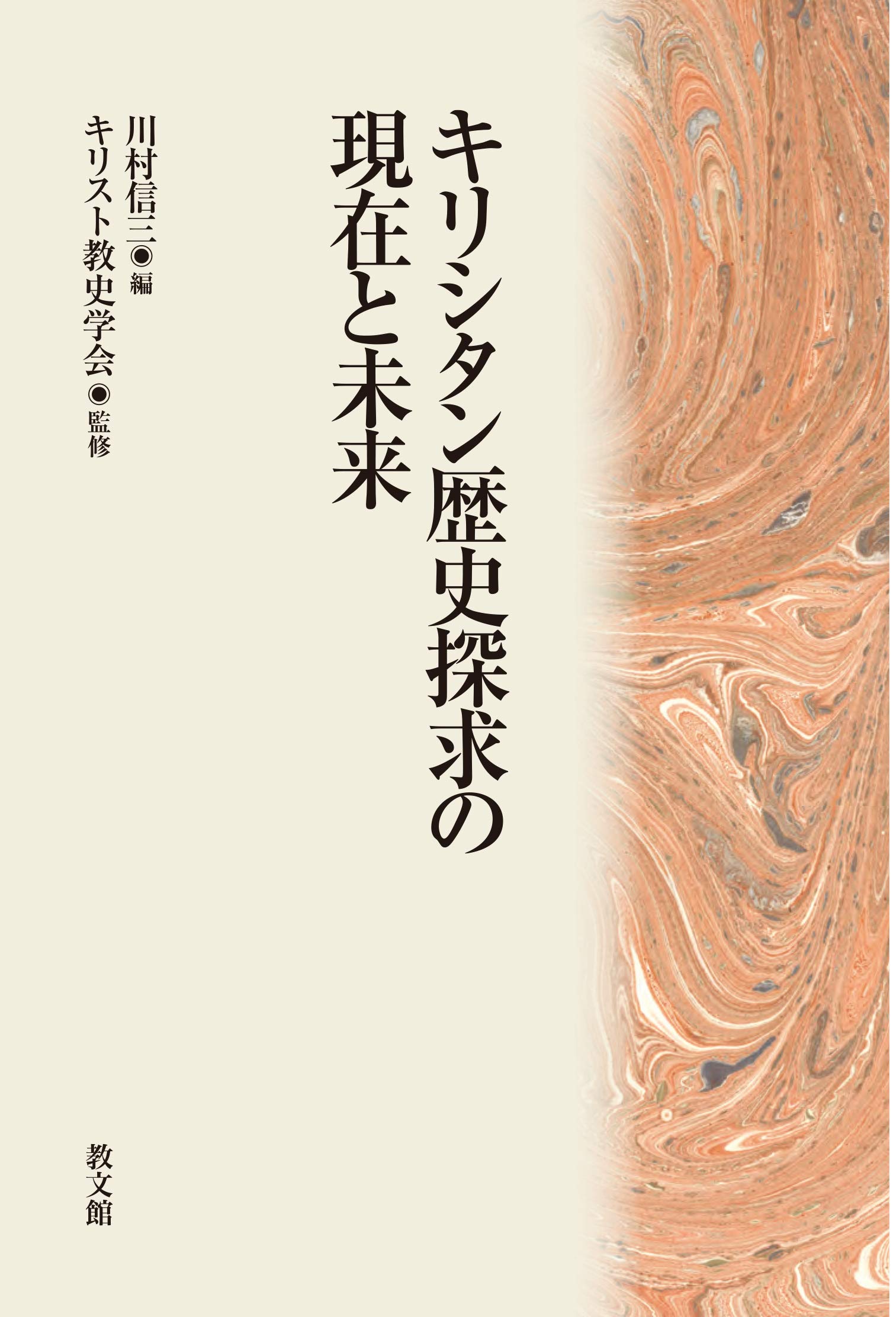
1970~80年代、キリシタンに関する新史料・新発見によってキリシタン研究は活況を呈した。1978年に放送されたNHK大河ドラマ「黄金の日日」の影響もあり、「南蛮」や「キリシタン」は一般にも広く浸透し、ブームとなった。2000年を前後して、そのようなブームは過ぎ去ったが、いま新しいステージを迎えている。
本書は、2019年のキリスト教史学会大会シンポジウム「キリシタン研究の再考―過去・現在・未来」を元に、シンポジウム登壇者5人の論稿のほか、4人の研究者に執筆を依頼し、一般の人にも手に取りやすく読みやすい形で出版された。
序章とあとがきで、川村信三(上智大学教授、イエズス会司祭)が本書の意義とキリシタン研究の過去から現在までを俯瞰。「キリシタン研究はかつて盛んであり、今は下火となった」という言説の当否を検討する。第一章では、東馬場郁生(天理大学教授)が、きりしたん受容者の研究を提唱。1977年に出版され日本学士院賞を受賞した高瀬弘一郎著『キリシタン時代の研究』への批判を試みる。
第二章で村井早苗(日本女子大学名誉教授)は、従来「美しい物語」として語られがちであったキリシタンの信仰を、教外者(キリスト教者でない者)として向き合い、キリシタンが日本近世史に如何なる刻印を与えたのか検討する。第三章において清水有子(明治大学教授)は、キリシタン禁制史の先行研究を整理し、キリシタン史研究者が日本側史料に十分踏み込めていない現状を指摘。これら史料問題の解決に向けてキリシタン史と日本史の双方から改善を進めることが未来につながるのでないかと述べる。
第四章で、キリシタンを民衆史として研究してきた大橋幸泰(早稲田大学教育・総合科学学術院教授)は、属性論で潜伏キリシタンを読み解く。属性論とは、一人の人物も一個の集団も、一つの属性だけで完結していないことを意識して歴史を見る方法。キリシタンがいた地域でも、キリシタン単独では村社会は成立せず、キリシタンもキリシタンという属性だけで生きていたのではなかった。信徒を取り巻く諸属性を意識して多角的に議論する必要性があると主張する。
第五章で浅見雅一(慶応義塾大学教授)は、「適応」という観点からキリシタン時代の神学と良心問題を検討。良心問題は社会における問題なので布教地によってその性質が異なる。日本布教とその延長上にある中国布教とは相互に比較することができる点も明確化する。第六章では、狭間芳樹(大谷大学特別研究員)が、イエズス会が使用、あるいは使用を禁止した仏教語を挙げながら、キリシタン民衆の死生観、祖先供養と一神教的思惟、洗礼の理解などを論考。キリシタン信仰の民衆化が認められるとしている。
第七章で安廷苑(青山学院大学准教授)は、細川ガラシャに関する自著に対して、他の研究者が行った批判に反論する。興味深いのは、ソウル出身の安だけでなく、反論相手であるフレデリック・クレインスや郭南燕も海外にルーツを持つ研究者であることだ。活発な議論それ自体が、キリシタンがグローバルヒストリーの重要項目となってきていることの傍証となっている。第八章では、森脇優紀(東京大学大学院特別助教)が料紙研究の最前線を報告。史料に「書かれている内容」と「モノ」から得られるデータを対照させることで、宣教師と紙との関係が浮き彫りにされる。最新鋭機器を用いた分析はまだ始まったばかりだが、キリシタン研究の未来の一翼を担っていくものと希望を抱かせる。
前世紀のブームをけん引した新発見に拘泥することなく、それらを踏まえて分析と解釈を深化させ、多角的な検討がされるようになったキリシタン研究。海外からの研究者も加わり、活発な議論が巻き起こっている現状は、決して「下火」とは言わないだろう。ロマンチシズムから脱し、多様なアプローチを通して、「量」から「質」へと転換した研究が、キリシタンの新たな魅力を見せてくれるのではないか。「黄金の日日」世代にも触れてほしい新たなロマンが現在進行中だ。
【2,640 円(本体2,400円+税)】
【教文館】978-4764261501













