【映画評】 神はアウシュヴィッツを赦しうるか 再監獄化する世界(5) 『ユダヤ人の私』『ナチス・バスターズ』『アウシュヴィッツ・レポート』『ホロコーストの罪人』『沈黙のレジスタンス』『復讐者たち』ほか 2021年11月30日
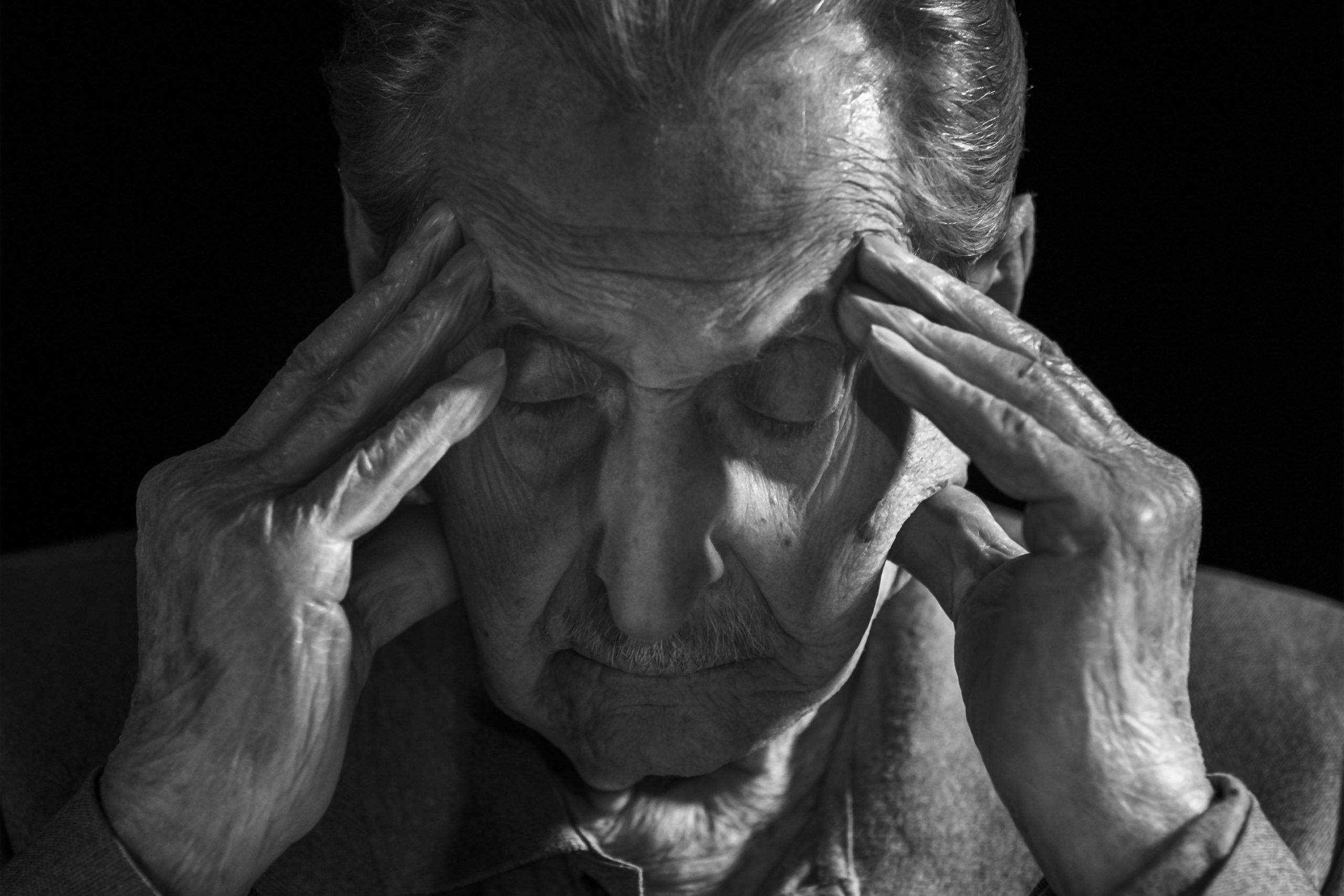
ホロコースト、すなわちナチスによるユダヤ人迫害を主題とする映画は、ドイツを中心に世界各地で毎年新たに撮られ、公開され続けている。ことに近年顕著なのは、視点や描写の多元化傾向だ。この11月、世界に先駆け日本公開となった『ユダヤ人の私』をはじめ、今夏から今冬にかけての日本公開新作7編を軸にこの潮流を概観する。なお本稿表題「神はアウシュヴィッツを赦しうるか」は、直接的には後段で触れるイタリアの思想家ジョルジョ・アガンベン著『アウシュヴィッツの残りもの アルシーヴと証人』より引用した。
ナチスドイツ宣伝大臣ヨーゼフ・ゲッベルスの元秘書女性が独白し続ける映画『ゲッベルスと私』を前作にもつ、クリスティアン・クレーネス監督の新作『ユダヤ人の私』。この新作で、前作と同じ一個人へのインタビュー形式により独白するのは、1913年ハンガリー生まれウィーン育ちのユダヤ人男性マルコ・ファインゴルトだ。彼は戦時下にアウシュヴィッツ他四つの強制収容所を体験し、戦後は無数のユダヤ難民をパレスチナへと逃がす役職に就き、また自国オーストリアの責任を訴えて続けてきた。
マルコ・ファインゴルトの語る強制収容所での体験は無論過酷を極めるが、『ユダヤ人の私』の白眉はさらに後半部、戦後のオーストリア社会で受けた無視や非難をめぐる語りにある。本編中には、同じオーストリアの市民から彼へと宛てられた中傷や脅迫の言葉が度々挿入されている。それらのうちにはごく最近のものも含まれており、“ナチス支配を受けた被害国”像などとひと括りにしてはとても語り切れない戦後社会の複雑さが垣間見える。この複雑さはしかし、往々にして大戦期ファシズムの影響下にあった欧州各地域では「すべてナチスが悪い」と巧妙に粉飾を施され、責任転嫁のうえ処理されてきた。そこで見過ごされてきたもの、敢えて目を背けられてきたものへの着目が、近年のホロコースト言及作品における多元化潮流の一傾向を示している。
【映画評】 『ヒトラーを欺いた黄色い星』『ヒトラーと戦った22 日間』『ゲッベルスと私』 アウシュヴィッツの此岸 Ministry 2018年8月・第38号
『ユダヤ人の私』のような映像表現は前作『ゲッベルスと私』と同様、言うまでもなく近似テーマを扱う多くの過去作を前提に初めて登場しうる。撮影時すでに100歳を超えていたゲッベルスの元秘書ブルンヒルデ・ポムゼルを語り手に据える『ゲッベルスと私』の前段には、ヒトラーの元秘書トラウドゥル・ユンゲの回想録『私はヒトラーの秘書だった』の刊行があり、これを基にブルーノ・ガンツがヒトラーを熱演した劇映画『ヒトラー 最期の12日間』(2004年)や、ユダヤ人生還者を含むホロコースト関係者へのインタビューで構成されるクロード・ランズマンの超長編『ショア』(1985年)などの存在があって初めて、『ユダヤ人の私』や『ゲッベルスと私』のように取材相手の皮膚の陰翳をも克明に捉える映像的肉薄は表現として力をもつ。
こうしたホロコースト関連映画をめぐる大きな流れのもと近作・新作群の俯瞰を通し、その今日性と今後の方向性を見定めるのが本稿の大目的となる。『ユダヤ人の私』については、終盤に再度言及する。
『アウシュヴィッツ・レポート』が描くのは、絶滅収容所のユダヤ系スロバキア人がその実態を世界へ知らせるべく脱走し、結果12万人の移送を防いだ実話劇だ。アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所を舞台とする作品は数多いが、本作ではスロバキア国境至近のポーランド南端部という地勢が物語の鍵となる。主人公らの脱走先となるスロバキア描写を通したナチスドイツ傀儡下の小国模様や、虐殺認知に鈍重な赤十字の消極姿勢が描かれる点は新奇だ。なかでも善きサマリア人のたとえを実践する名もなき人々の佇まいや、赤十字幹部の「あなたがたの話は、信じるには恐ろしすぎる」というセリフは本作を象徴する。それはまた、紛争最前線への救護者派遣を使命とする同時代の赤十字幹部をして信じがたいと言わしめる体験を、後の世はどのように語り、表象できるのか、という私たち自身への問いへと直に連なる。
日本社会にとってこの2021年は、コロナ禍と東京五輪とにより長く記憶されるだろう。スキャンダルを連発させた東京オリンピック・パラリンピック開催へ至る過程では、開幕前日段階での小林賢太郎・開閉会式ディレクター解任劇も記憶に新しい。過去のコント中につぶやいた一言を指弾するこの解任劇は、中山泰秀防衛副大臣(当時)の通報を受けた米国のユダヤ人人権団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター」のクレームに即日対応するものだった。一言の軽率さはもとより、国防の要職に就く人物が教師へ告げ口をする優等生のような挙動を外国民間組織に対し為す浅薄さも含め、日本社会におけるホロコースト表現を巡る認識と態度の稚拙さを再度露呈した。こうした政府・組織委の反応自体もまた、言うまでもなく属す社会のホロコースト表象を構成する。しかも臭いものに蓋という以上の議論は何ら為されず、したがって同類の事象が今後繰り返されることは免れない。
一方、世界においてホロコーストをめぐる表現は、今こうしているあいだにも着々と深化、変容を遂げている。
『ホロコーストの罪人』の舞台は、『アウシュヴィッツ・レポート』のスロバキアと同様にナチスの保護国とされたノルウェーで、幸福な日々から強制収容の地獄へと突き落とされたユダヤ人一家の面々が主人公となる。ナチス侵攻から逃れた王室がロンドンで亡命政権を樹立し、連合国側に立ってレジスタンス運動を始めるなか、本土の傀儡政権下では警察官や民間人がナチスへの服従を強いられた。北欧においても長らくタブー視されてきた対独協力問題を、正面から扱うノルウェー映画人の気概に感服する一方、一般市民が人情を保ったままユダヤ人の絶滅収容所送致へ手を貸す描写は心が凍てつく。
なお間一髪でナチスの手を逃れた戦時下のノルウェー王室を描く映画としては、直近にエリック・ポッペ監督作『ヒトラーに屈しなかった国王』(2016年)がある。過去記事「敵対と猜疑のゆくえ 再監獄化する世界(2)」で触れた、大戦中にナチス高官とスウェーデン諜報部の両方から登用され二重スパイとして活動した実在のノルウェー人女優ソニア・ヴィーゲットを描く『ソニア ナチスの女スパイ』(2019年)は、視点の多元化潮流そのものを体現する良作だ。また、当時のノルウェー国王ホーコン7世の孫にあたる現国王ハーラル5世へ宛てたクルド難民からの手紙がテーマとなるヒシャーム・ザマーン監督作『国王への手紙』(2014年)は、ナチス期を生き延びた王室という観点を経由し、テロと紛争の現代を逆照射する点で注目に値する。
視座の多様化は、視点個別の深化をもたらす。『沈黙のレジスタンス~ユダヤ孤児を救った芸術家』では、戦後パントマイムの神様として称えられ、マイケル・ジャクソンらポップアイコンやコンテンポラリーダンスシーンなど20世紀後半の身体芸術全般へ絶大な影響を及ぼしたマルセル・マルソーによる、知られざる大戦下の格闘が描かれる。ナチス傀儡のヴィシー政権下フランスで、恐怖に強張ったユダヤの子らを笑わせ活路へ導く姿を、実母がクラウンであった経歴をもつという若き名優ジェシー・アイゼンバーグが熱演する。子どもたちを牽引しアルプス越えを試みる道程において、のち“沈黙の詩人”と謳われた身体表現のルーツが極めて精彩に描かれる。
若者や地元の羊飼いなどに率いられ、ユダヤ人の子どもたちが山を越えナチスから逃れる近作としては他に、スイスへと抜けるローラ・ドワイヨン監督の2016年作『少女ファニーと運命の旅』、ピレネー山脈を越えるベン・クックソン監督の2020年作『アーニャは、きっと来る』などがある。
戦争が幕を閉じた瞬間、子どもたちの心のなかでもう一つの闘いが始まった。自分は何者なのか、どんな人間になるよう期待されているのかという意識そのものをめぐる闘いが、家族や親族、私的な生活空間といった親密圏で展開された。この闘いは、終戦の日からわずか数カ月で終わるとは限らない。数十年にわたり続く場合もある。(レベッカ・クリフォード 『ホロコースト最年少生存者たち』)
ナチスからの逃避行がテーマとなる映画は、古典的名作『カサブランカ』(1942年)以来数多いが、ここに挙げた当時の子ども世代へ焦点化された近年の作品群はまた別の様相を含み込む。レベッカ・クリフォードの近著『ホロコースト最年少生存者たち 100人の物語からたどるその後の生活』に詳しいが、戦後の混乱を経たその後の人生は多くの場合、強制収容所を生き残った子どもたちにおいてさえ戦時中より過酷と感じられたし、自身は収容体験がなく親をホロコーストで失った子どもたちにとってもそれは同様だった。こうした観点への着目もまた視点の多元化の一形態と言え、これは同時に大戦直後に始まる欧州へのトルコ移民や北アフリカ難民から最近のシリア紛争へと至る、移民/難民をめぐる2世3世問題への社会的関心の深まりとも同期する。
こうしたホロコースト映画の多様化や深化と軌を一にするのが、ナチス表象およびヒトラー像の多面化だろう。とりわけ『帰ってきたヒトラー』や『ジョジョ・ラビット』、『アフリカン・カンフー・ナチス』など、ここ数年のヒトラー描写は以前では考えられないほど戯画化され今日的な批評性を有したり、過度にキッチュへと堕し反倫理的であったりする。これはそのような表現を許容する空気が社会に増したことを意味する一方で、シリアスな再現描写以外は受け入れがたい生の体験記憶を有する世代の人々が順次寿命を迎え、極少数化しつつあることをも意味する。ホロコースト表現の深化は、この忘却の兆候へ抗う流れのようにも思える。ここで重要なのは、多くの場合その抵抗の主体を現代ドイツ社会、もしくはドイツ人自身が担っている点だ。西ドイツ時代のワイツゼッカー大統領は1985年の演説で、「過去に目を閉ざす者は現在にも盲目となる」と述べ、過ちを繰り返さないためにドイツ人は己の非人間的な行いを自ら直視する責任があると結論づけた。これが単なるその場限りの謝罪に終わらない内容をもつことは、今回言及した作品の多くに出演や製作のみならず、出資者としてドイツの人々や私企業・公共団体が名を連ねることからもうかがえよう。
ロシア映画『ナチス・バスターズ』は、1941年冬のロシア大地で猖獗を極めた独ソ戦の前線において伝説化した狙撃兵“赤い幽霊(Krasnyy prizrak:原題)”をめぐるボルシチ・ウェスタンだ。大部隊による激戦ではなく、モスクワ攻防戦を控え広大な大地に全面展開した小隊レベルの寒村描写がつづき、タランティーノやマカロニ・ウェスタンの奥向こうに黒澤明の呼び声さえ響く画作りが映画ファンの目を愉しませる。その一方で、“赤い幽霊”本人として描かれる男は終始寡黙で、たとえ重傷を負っても無表情を貫くため何を考えているか、どんな履歴をもつ人物なのか謎は一向に解き明かされない。本作は、ナチスによるホロコーストへの直接言及がない点で本稿の趣旨からは外れるものの、序盤と終盤がヒトラーに扮するロシア人旅芸人の目線を通して描かれる点はチャップリン監督作『独裁者』(1940年)を前景に感じさせる。また死や幽霊といった問題軸へ直に触れるにも関わらず「赤い幽霊とは誰なのか」に応えるその終幕は、特に爽快な仕上がりとなっている。
ちなみに『ナチス・バスターズ』という邦題は、ナチス幹部の暗殺を企む連合軍側の潜入兵士やユダヤ人映画館館主女性らを主人公とする、クエンティン・タランティーノ監督作『イングロリアス・バスターズ』(2009年)に由来する。ナチスが登場する多くの劇映画同様、本作にも己の愉悦のために敢えて残酷な仕方でユダヤ人を惨殺するナチス高官が登場する。オーストリア出身の名優クリストフ・ヴァルツが演じるこの親衛隊将校の造形は、そうした“残酷なナチス高官”像の史的文脈を十全と踏まえたうえその更新が企図され、成功している点で特筆に値する。
2021年11月末には他に、同じ1941年冬の独ソ戦をテーマとする『1941 モスクワ攻防戦80年目の真実』(2020年)も日本公開となった。本作では、モスクワ郊外ポドリスクの士官候補生3500名投入中2500名戦死というモスクワ攻防戦の泥沼描写が、近年機密解除された文書に基づき、戦車軍装ほか博物館保存物まで動員して実現された。両陣営に2500万人を超える犠牲者を出したとされる独ソ戦を、当事国の社会が今どう捉えどう描くかを見渡すうえでもこうした作品は興味深い。
日本で「終戦の日」と称される8月15日を境に、第二次大戦をめぐる日本人すべての戦闘行為が終わったのではまったくないように、ドイツ本国にはナチス政権崩壊を戦争完結とは受け取らない人々がいた。『復讐者たち』(2020年)が映しだすのは、妻子を強制収容所で殺された男が導かれゆく血の隘路だ。男は終戦直後の混乱下ナチス残党を狩るユダヤ旅団へ入団、さらには一般ドイツ人の600万人虐殺計画を発動させた地下組織ナカムへと所属する。『イングロリアス・バスターズ』では主人公らを潜入者と見抜く聡明にして悪辣なナチス高官を演じ、2019年にはテレンス・マリック監督作『名もなき生涯』で信仰に殉じナチスに処刑されのち列福されたオーストリア人農夫に扮したアウグスト・ディールが、この『復讐者たち』ではホロコーストにすべてを奪われ復讐の鬼と化した男の悲しき道行きを熱演する。
ナチスやホロコーストを扱う近作のなかでもテレンス・マリック『名もなき生涯』は、ヒトラー像が孕む今日的脅威を具現化する『帰ってきたヒトラー』(2015年)やアウシュヴィッツ収容所内部を独創的に視覚化した『サウルの息子』(2016年)などの最重要作群に次ぐ位置を占めながら、日本語圏ではホロコースト映画を概観する文脈上でさえ言及されることの少ない奇特な状況が現出している。これは全編が「天路歴程」の影響下にあるテレンス・マリック過去作『聖杯たちの騎士』を、単にハリウッドスターが競演する映像詩としてのみ宣伝・消費した日本の映画業界、映画市場の精神的貧困を示すものにまずは他ならない。同監督作に通底するキリスト教文脈の高い抽象度を割り引いても、このこと自体がホロコースト表象をめぐる日本社会の受容態度を露わとする点ではまた、上記東京五輪の顛末とも通じている。(上掲『名もなき生涯』記事内に、『聖杯たちの騎士』記事へのリンクあり)
ひとは、彼を創造したところのもののシンボル、彼がそこからやって来て、またそこに帰還することを望んでいるその無限なるもののシンボルとして神がみを創造する。この一体化の先取り〔予期〕と、この先取りの宗教的な芸術表現において、彼はみずからの有限性と、みずからの有限性の不安とを自分自身に引き受ける勇気をかちとる。彼は有ることの勇気〔存在への勇気〕をかちとる。(パウル・ティリッヒ 『芸術と建築について』)
『復讐者たち』については、イスラエル人の兄弟監督ドロン・パズとヨアブ・パズによる映像表現も特筆に値しよう。この兄弟は、ユダヤ教の伝承に登場する泥人形由来の怪物を主題とする『ゴーレム』(2018年)を前作、聖都エルサレムの地底から悪魔たちが地上を襲う“JeruZalem”(2015年)を前々作にもち、元来ホラー映画のフィールドで台頭してきた監督コンビである。史実をベースとする『復讐者たち』には、前作までのオカルト怪異要素こそ皆無であるものの、精神の闇や恐怖のヴィジュアライズに特化してきた彼らの素養は、ホロコーストによって不条理に家族や帰るべき土地をも奪われた絶望状況の視覚表現へ十全と活かされている。
スピルバーグ『シンドラーのリスト』(1993年)は世界的にヒットした一方で、強制収容所の惨劇をハリウッド技術により見世物化したことが強く批判もされた。しかしいまや、ホラー技術を活かした『復讐者たち』へのこうした観点からの酷評は事実上機能しがたい。それはホロコーストを扱う映画の多様化が、一般通念として社会に受け入れられている証左ともいえるだろう。たとえば『ショア』(1985年)の監督ランズマンはかつて、「『シンドラーのリスト』を観た多くの人たちに、あなたの作品は観ることができないと言われた。きっと『ショア』を観ても涙を流せないからだろう」と語ったが(*1)、『ユダヤ人の私』のクレーネス監督が『復讐者たち』を挙げて同じように嘆く事態は考えにくい。実は『復讐者たち』のある場面で、主人公の精神的孤立と戦時中のフラッシュバックをめぐる表現があまりにも烈しすぎたため、筆者は目を背けたくなるような思いに駆られたが、そのことを以て製作陣への個人的評価は上がりこそすれ、そのモラルを問う種の判断軸は心の内に不思議なほど生じなかった。
では、こと現代にいたっては、ホロコーストをめぐるあらゆる表現が可能になったのか。無論そうではない。またもしそうだとすれば、それは「すべてが可能になった」という一元化に過ぎず、多様化とは真逆の事態といえる。ならばかつてアドルノが「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」と述べた前世紀後半の逼塞状況から何が変わり、あるいは変わりつつあり、何が変わらず存続しうるのか。
この問いを考えるうえで、『サウルの息子』はやはり重要な鍵となる。本作のような手法をとる主流ジャンルとしてはホラー映画が該当すると述べる美学者・田中純は、「『サウルの息子』がもたらすのは、全体的な展望を欠いて局所的なものにとどまる触感的(ハプティック)な感覚経験――ネメシュ監督の言葉によれば、『内臓的=直感的(viscereal)な経験』――のリアリズムである」という指摘を紹介したあと、息子の葬送をめぐる一見古風な物語形式を下敷きとするこの映画の本質的な達成を中動態的な「脱ナラティヴ化」に求め、その中核表現として主人公サウルの「無表情」を挙げている(田中純「ホロコースト表象の転換点」 渋谷哲也 夏目深雪編『ナチス映画論』所収 *2) 。終盤までサウルの顔面には一貫して感情表現が無いようにみえるからこそ、観客はそこに「微細な表情を読み取ることをつねに強いられている」と田中はいう。そして終幕の直前、サウルが不意にカメラ目線となって洩らす微笑みが意味をもつのもそれゆえだと結論する。
この結末について、『サウルの息子』監督ネメシュ・ラースローの次作『サンセット』(2018年)をめぐる記事「翳りの鏡像、帝都の夢」のなかで、筆者はかつてこう述べた。
ラースローのデビュー長編『サウルの息子』では、主人公の囚人サウルがラストで不意にカメラ目線となり、笑みを洩らしたあとナチス兵士による銃殺の音が空へ響く。『サンセット』において主人公イリスは、ラストショットで第一次大戦下の独軍塹壕の暗闇からサウル同様こちらを見据える。その表情にはしかし一切の感情がよみとれない。その屹立した、烈しくも冷徹な両の瞳が厳しく映し返すものは言うまでもなく、100年後を生きるこの私たちのありさまだ。
わたしたちの政治は今日、生以外の価値を知らない。このことがはらんでいる諸矛盾が解決されないかぎり、剥き出しの生にかんする決定を最高の政治的基準にしていたナチズムとファシズムは、悲惨なことにも、いつまでも今日的なものでありつづけるであろう。
沈黙のうちの、不安に満ちた決意は、みずからの終末を先取りし、引き受けるのだから、現存在の癲癇的なアウラのようなものだろう。そのアウラにおいて、現存在は、「生の横溢であるとともに源泉でもある過剰としての死の世界に触れる」のである。(ジョルジョ・アガンベン『アウシュヴィッツの残りもの アルシーヴと証人』)
映画におけるホロコーストの表象不可能性ということを考えるとき、プリーモ・レーヴィやヴィクトール・フランクルといった直接の生存者が遺した言葉とは別に、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンの著作群から得られるものは極めて大きい。そのアガンベンによる著作『実在とは何か マヨラナの失踪』はムッソリーニ政権下の1938年3月、パレルモ発ナポリ行きの郵便船に乗船したあと忽然と姿を消した当時31歳の天才数学者エットレ・マヨラナの生涯とその業績を考察する。ハイゼンベルクから認められ、フェルミから「ガリレイやニュートンのような天才」と讃えられた若き理論物理学者の失踪を、ハイゼンベルクの不確定性原理に代表される、量子論物理学における現象の確率論的性格へと絡めて語るところに、当代随一の思想家アガンベンの膂力を感じてやまない。
その一方で、「もし量子論力学を支配している約束事が、実在は姿を消して確率に場を譲らなければならないということだとするなら、そのときには、失踪は実在が断固としてみずからを実在であると主張し、計算の餌食になることから逃れる唯一のやり方である」というその結語には、ラースロー『サウルの息子』『サンセット』で終幕に差し向けられた視線の奥向こうに息づくもの、徹底して無表情を貫く“赤い幽霊”の正体にも通じるものが強烈に予感される。
ここに、映画におけるホロコースト表象をめぐる可能性/不可能性の今後を考える意味は、決定的な強度を以て横たわる。ゆえにホロコーストを考えることは、1940年代前半のユダヤ人大量虐殺を歴史的事象として特権化する仕草とは無縁の今日性を、なお強靭に有している。中国の強制労働施設の実態を描いた『馬三家からの手紙』(2018年)の華僑系カナダ人監督レオン・リーは、現代中国において監獄がもつ意味を尋ねる筆者に対し、かつて「中国という国家体制にとって、強制収容所は必要不可欠のシステムとして存在する。それが中国そのものだといってもよい」と答えた。この問答が為されたのは2019年初頭のことであり、同年4月末をもって平成の時代は終わりを迎えた。他国を例示するだけでは不足だろう。平成の終わりに近い2018年7月、日本の監獄ではオウム真理教事件への政治的決着として麻原彰晃ら13人の大量死刑が執行された。これを明治末に起きた幸徳秋水らの大逆事件になぞらえる作家・高橋源一郎の指摘は、その一面性を踏まえてもなお興味深い。
2019年夏、筆者は反中国デモで沸騰する香港へ滞在した。それは香港の若手監督らへの取材目的であったが、滞在中にも交通は幾度も遮断されつづけ、暴行事件は頻発し、街路に催涙弾の煙や薬莢を見かけるのは日常だった。街全体が監獄化されゆくかのような感覚に、レオン・リーの言葉を幾度も反芻せざるを得ず、この社会における自由の意味を考え直さざるを得なかった。慣れ親しんだバンコク都心でのクーデター勃発を目撃したあと、すでに丸6年が経過していた軍事政権下タイでの生活を切り上げようと考え始めいた筆者にとって、それは他人事ではまったくなかった。
2020年1月、ポーランドのアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所跡地やエルサレムのホロコースト記念館で、相次いでアウシュヴィッツ解放75年周年式典が催された。ドイツのシュタインマイヤー大統領はその場で「私は歴史的な罪の重荷を背負ってここに立っている」として、1985年のワイツゼッカー演説を引き継ぐ姿勢をみせた。かたやガザとヨルダン川西岸の監獄化を私たちはどう捉えるべきか。そのパレスチナへ飛び、エルサレムでアイヒマン裁判を傍聴して“悪の凡庸さ”を見いだしたハンナ・アーレントが言う意味での「人間」は、そのようにして各人が個を引き受けることからしか始まらない。明治の終わりと平成の終わり、そこでは統治機構により本当のところ何が殺されたのか。そこにエットレ・マヨラナはまだ立っている。生死をめぐるあわいから、なお私たちを見つめている。
『ユダヤ人の私』のクレーネス監督前作『ゲッベルスと私』は13カ国で公開され、監督ら制作陣の期待を遥かに超える反響を得たという。それはつまり、あらかじめ限定された観客受容に留まることを監督らが覚悟のうえ取り組んだ先鋭的実践が、当人たちの予想を超えて広範な人々へ受け入れられたことを意味する。本国以外での本格的な劇場公開は日本が初めてという『ユダヤ人の私』は前作同様、精彩に映しだされる顔面の皺や手の皮膚が、映画の語りを一層際立たせる。いや、ここでは語りという言葉遣いに注意深くあるべきだろう。音楽には音楽独自の論理体系があるように、映像は映像独自の言語体系をもつ。口先から縷々放たれる日常言語とはその構造が根本的に異なっている。顔面の皺や手の皮膚が、語るのだ。
資料は実証主義者たちが信じているように開かれた窓でもなければ、懐疑論者たちが主張するような視界をさまたげる壁でもない。いってみれば、それらは歪んだガラスにたとえることができるのだ。ひとつひとつの個別的な資料の個別的なゆがみを分析することは、すでにそれ自体構築的な要素を含んでいる。しかし、構築とはいってもそれは立証と両立不可能なわけではない。また、欲望の投射なしには研究はありえないが、それは現実原則が課す拒絶と両立不可能であるわけでもないのである。知識は(歴史的知識もまた)可能なのだ。(カルロ・ギンズブルグ『歴史・レトリック・立証』)
現存するイタリアの歴史学者を代表する一人、カルロ・ギンズブルグ。その両親、とりわけカルロの母である小説家ナタリア・ギンズブルグは、筋金入りのコミュニストであり反ナチだった。ファシズム政権下にあってもユダヤ人の保護支援に積極的で、プリーモ・レーヴィら強制収容所体験をもつ作家たちの文章にも、彼女の名はしばしば登場する。フランクフルト学派を例に挙げるまでもなく、欧州を揺籃とする近代的知の大系はナチスの暴虐により大きく傷つき、限界を象られ、その軛をいまだ脱しきれてはいない。論理体系としての知のみならず、同じことは音楽であれ映像であれまた経済行為であれ、人の織りなすあらゆる表現・行為に言えるだろう。あるいは詩であれ。
人はどこまで無力なのか。アガンベンの問いかけは一層鋭さを増し、アドルノの言明はいまだ効力を失わない。
驚くべき変化。力強く行為する手がお前に結ばれる。
無力さと孤独のうちに、お前は自らの行為の終わりを見る。
しかし、お前は深く息を吸い、静かに、そして心安らかに、
より強い御手に正しさを委ね、満足する。
ただ一瞬でも、幸せにも自由に触れたならば、お前はそれを神にゆだねよ。
彼が自由を美事に完成するために。
(ディートリヒ・ボンヘッファー『獄中書簡集』)
神はアウシュヴィッツを赦しうるか。
アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である。
(ライター 藤本徹)
『ユダヤ人の私』”Ein judisches Leben” “A Jewish Life”
公式サイト:https://www.sunny-film.com/shogen-series
全国順次公開中
『アウシュヴィッツ・レポート』”Správa” “The Auschwitz Report”
公式サイト:https://auschwitz-report.com/
全国順次公開中
『ホロコーストの罪人』”Den største forbrytelsen” “Betrayed”
公式サイト:https://holocaust-zainin.com/
全国順次公開中
『沈黙のレジスタンス』”Resistance”
公式サイト:https://resistance-movie.jp/
全国順次公開中
『ナチス・バスターズ』”Krasnyy prizrak” “Red Ghost”
公式サイト:https://nazisbusters.com/
12月3日(金)全国ロードショー
『1941 モスクワ攻防戦80年目の真実』”Podolskiye kursanty” “The Last Frontier”
公式サイト:https://1941.jp/
全国順次公開中
『復讐者たち』”Plan A”
公式サイト:https://fukushu0723.com/
全国順次公開中
【主要参考引用文献】
ジョルジョ・アガンベン 『アウシュヴィッツの残りもの ― アルシーヴと証人』 上村忠男・廣石正和訳 月曜社 2001
レベッカ・クリフォード 『ホロコースト最年少生存者たち 100人の物語からたどるその後の生活』 山田美明訳 芝健介監修 2021
パウル・ティリッヒ 『芸術と建築について』 前川道郎訳 教文館 1997
ジョルジョ・アガンベン 『実在とは何か マヨラナの失踪』 上村忠男訳 講談社 2018
カルロ・ギンズブルグ 『歴史・レトリック・立証』 上村忠男訳 みすず書房 2001
D. ボンヘッファー E. ベートゲ 『ボンヘッファー獄中書簡集』増補新版 村上伸訳 新教出版社 1988
渋谷哲也 夏目深雪編 『ナチス映画論』 森話社 2019 *2
四方田犬彦 『テロルと映画』 中公新書 2015
飯田道子 『ナチスと映画』 中公新書 2008 *1
【関連過去記事】
【本稿筆者による言及作品別ツイート】(言及順)
『ユダヤ人の私』
アウシュヴィッツ他4つの強制収容所を知る男。
戦後無数のユダヤ難民をパレスチナへ逃がし、自国オーストリアの責任を訴えてきた相貌と声音の軋み。ナチスへ転嫁した人々との共生、止まない脅迫。
ホロコーストの今日性巡る表象の可能性と不可能性が、その皮膚の翳りを象りゆく。 https://t.co/D1yjmHwHfb pic.twitter.com/pK3aWUBRDc
— pherim⚓ (@pherim) November 20, 2021
『アウシュヴィッツ・レポート』
絶滅収容所のユダヤ系スロバキア人が、その実態を世界へ知らせるべく脱走、結果12万人の移送を防いだ実話劇。
既存のホロコースト作と比べ、アウシュヴィッツの地勢やナチス傀儡下の小国模様、虐殺認知に鈍重な赤十字が描かれる点は新奇。終幕の醸す今日性が衝撃的。 pic.twitter.com/mmt8OGuNVX
— pherim⚓ (@pherim) July 28, 2021
『ホロコーストの罪人』
ナチスドイツ保護下のノルウェーで、幸福な日々から強制収容の地獄へ突き落とされたユダヤ人一家。
一般の警察官や民間人が、人情を保ちつつ絶滅収容所への送致に手を貸す姿は心が凍てつく。長らく看過されてきた対独協力問題を、正面から扱うノルウェー映画人の気概に感服。 pic.twitter.com/ZGHb7MnDaU
— pherim⚓ (@pherim) August 14, 2021
ちなみに現国王のお爺さん、ノルウェー国王ホーコン7世が主役の映画『ヒトラーに屈しなかった国王』が年末日本公開予定。ナチスの脅迫に対し抵抗を貫き、現ノルウェーの基礎を築いた人々の物語。舐め切ったナチスの巡洋艦を、老朽要塞の老司令官が新兵を率いて沈めてしまう冒頭部から圧巻の良作です。 pic.twitter.com/HaKfgQ1B6o
— pherim⚓ (@pherim) September 21, 2017
『ソニア ナチスの女スパイ』
大戦下ノルウェーで女優ソニア・ヴィーゲットは、ナチス高官とスウェーデン諜報部から登用され二重スパイとなる。
女優として戦後も長く活動したソニアの、暗躍の軌跡。描かれる情報リスクに対する身体感覚が、監視社会化の進行するいま形を変え再来しつつあるリアル。 pic.twitter.com/uc3etDcbb4
— pherim⚓ (@pherim) August 30, 2020
『国王への手紙』
郊外の難民センターからオスロへ向かうバスへ乗り合わせた5人のクルド人。各々の抱える屈折と苦渋の全てが、映画の扱うたった一日のうちに、そして国王へ宛て老人のしたためる手紙の内に結晶する。故国での過酷な尋問、爆撃を受けた故郷の村、ノルウェーに降る雪の遠さと冷たさ。 pic.twitter.com/iK9ETucEBh— pherim⚓ (@pherim) March 8, 2017
『沈黙のレジスタンス~ユダヤ孤児を救った芸術家』
パントマイムの神様マルセル・マルソーの、知られざる大戦下の格闘。
ナチス傀儡下フランスで、恐怖に強張ったユダヤの子らを笑わせ活路へ導く姿を、ジェシー・アイゼンバーグが熱演。沈黙の詩人と謳われた身体表現の源が、極めて精彩に描かれる。 pic.twitter.com/0R2iky0Jwe
— pherim⚓ (@pherim) August 20, 2021
『少女ファニーと運命の旅』
子供達がかくれんぼする、ユダヤ人と知られないように。野山を駆け巡る、銃口に狙われて。ホロコーストの惨劇下、13歳で逃避行を率いた少女ファニーの勇気と決断、命を張って彼らをかばう大人達。子供なりに機転を利かせ明るさを保つ努力の健気さ。中立国スイスの遠さ。 pic.twitter.com/G5ZUWFRtge— pherim⚓ (@pherim) August 8, 2017
『アーニャは、きっと来る』
ピレネー山麓に暮らす羊飼いの少年が、ナチス占領下のフランスからスペインへのユダヤ人逃亡を助ける。『戦火の馬』他のマイケル・モーパーゴ原作。
ナチス将校との情深い交流、父役ジャン・レノなど見処で、移牧を装いユダヤ人の子らと敢行するピレネー越え空撮は圧巻。 pic.twitter.com/2tPvtYlX63
— pherim⚓ (@pherim) November 23, 2020
『ナチス・バスターズ』
冬のロシア大地、独ソ戦前線で伝説化した狙撃兵“赤い幽霊(Krasnyy prizrak:原題)”巡るボルシチウェスタン。
戦線拡大後の寒村描写が続き、タランティーノやマカロニウェスタンの奥向こうに黒澤明の呼び声さえ響く画作りが楽しい。赤い幽霊とは誰か、に応える終幕は格別爽快。 pic.twitter.com/UIfG0jBt0B
— pherim⚓ (@pherim) November 29, 2021
『帰ってきたヒトラー』
ヒトラー本人がタイムスリップし現代へ、TVスターとなる。良質コメディ風の序盤から、危険領域へと風刺が踏み込むシリアス展開へ。無名の主役俳優に拍手、ラスト震撼。笑いが形を変えず恐怖に転化する。良作。6/17公開。https://t.co/9Rm1i5ATq8— pherim⚓ (@pherim) June 14, 2016
『ジョジョ・ラビット』
ヒトラーユーゲントで奮闘する少年が、自宅屋根裏にユダヤ人少女を見つけ恋する成長譚。逞しき母役スカーレット・ヨハンソンとやさぐれナチス士官役サム・ロックウェルが、夢見がち少年の道行きを両脇できっちり締める。マオリに血筋もつ監脚タイカ・ワイティティの好距離感。 pic.twitter.com/W4kEoFlE6f— pherim⚓ (@pherim) January 5, 2020
『アフリカン・カンフー・ナチス』
ヒトラーと東條英機はガーナで生きていた。
“イタ公がだらしないので”ガーナ加入の真三国同盟、打倒総統の酔拳修行を経て奇人変人集う天下一武道会化する抱腹絶倒の本作、なぜ書き始めたか監督は思い出せないらしい。
意味と無意味が転倒しまくる魅惑困惑の84分。 pic.twitter.com/Y6TLwlb6Kd
— pherim⚓ (@pherim) June 11, 2021
『1941 モスクワ攻防戦80年目の真実』
激戦必至の独ソ戦天王山。ポドリスクの士官候補生3500名投入2500名戦死の泥沼描写、その迫真。
近年機密解除された文書に基づき、戦車軍装ほか博物館保存物動員の物量規模と古風な青春ドラマの並走する、大作量産期突入のロシア映画わが道ゆく感が味わい深い。 pic.twitter.com/Run77Mx2AZ
— pherim⚓ (@pherim) November 16, 2021
『名もなき生涯』
オーストリア山村に暮らす農夫が、ヒトラーへの忠誠を拒んで処刑されるまでの日々。無名の男が貫く魂の誠実を圧倒的な風景描写により語らせる、テレンス・マリック孤高の達成。夫婦の覚悟を畏れつつ見捨てる司祭や判事(ブルーノ・ガンツ)の苦悶と、排斥する村人らの相貌に戦慄する。 pic.twitter.com/ESCsoLQk4a— pherim⚓ (@pherim) February 20, 2020
『聖杯たちの騎士』において心の底で進行するこの別次元の旅は、主にモノローグによって語られる。実はこの語り、日本語サイトや資料でこの点に触れる言及は皆無なのだけれど、基本的にバニヤン『天路歴程』からの引用朗読で構成されている。表層の《眠る世界》は光であり、言葉は深層を目指してゆく。 pic.twitter.com/caNKAwQ6vi
— pherim⚓ (@pherim) December 17, 2016
『JeruZalem』
イスラエル映画、地下世界ホラーの良作ktkr。エルサレムの聖地群がてんこ盛りで登場。ギミックとして電脳コイルばりのスマートグラスが登場するPOV作品でB級感も素敵、期待値を大きく超えて楽しめた。日本公開未定。 https://t.co/tpMtdUsnGG— pherim⚓ (@pherim) April 14, 2016
「このくるしみは、だれのもの」
映画『サウルの息子』をめぐるnote更新しました→ https://t.co/7KZ7FukNMP
ユダヤの葬送、儀式と執念。野火、アイヒマン、プリーモ・レーヴィ、フランクル、アガンベンetc. pic.twitter.com/dIgE1SIfGR— pherim⚓ (@pherim) April 3, 2016
『サンセット』
第一次世界大戦前夜のブダペスト。馬車の走行音や巻き立つ硝煙に焦点を合わせ五感を誘い込む、『サウルの息子』で見せたネメシュ・ラースロー監督独自の流儀健在。家族の謎追う娘の目を通し、帝国の腐敗や不穏な予兆が描かれる本作で、娘が真に凝視するのは観客席の私達に他ならない。 pic.twitter.com/aS97pvDs6D— pherim⚓ (@pherim) March 11, 2019
『馬三家からの手紙』
米国のスーパーで売られたハロウィーン飾りの箱に、“労働教養所”で使役される男性の告発英文が。世界の非難を浴び当該施設は表面上閉鎖、男性は解放される。しかし華僑系カナダ人監督が追うその後の展開は想像を超えていく。現代中国の収容所的側面を鮮やかに伐り出す衝撃作。 pic.twitter.com/EBNQ4NBSVr— pherim⚓ (@pherim) March 21, 2020
『ゲッベルスと私』
ナチス宣伝相ゲッベルスの秘書だった103歳の女性による告白。それは稀有の内幕語りであり、かつアーレント“凡庸な悪”の一典型にも映る。老化した皺の陰翳を過剰なほど仔細に捉えた映像が、「何も知らなかった」「私に罪はない」と語る時その深層に轟く晦渋の呻きを鮮明に響かせる。 pic.twitter.com/4UHyQPPDDk— pherim⚓ (@pherim) June 20, 2018
© 2021 Blackbox Film & Medienproduktion GMBH
















